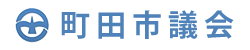
◎町田市議会申し合わせ事項
最終改正 令和元年11月22日
略 語 の 説 明
「法」……………………………………………………地方自治法
「条」………………………………………町田市議会委員会条例
「規」…………………………………………町田市議会会議規則
「災害対策委規約」………町田市議会災害対策委員会設置規約
目 次
第 1 章 会 議
第 1 節 総 則
1 議会の呼称…………………………………………………………12
2 一般選挙後最初の会議の運営……………………………………12
3 議席…………………………………………………………………12
① 議席の決定…………………………………………………………12
② 仮議席………………………………………………………………12
③ 議席番号……………………………………………………………12
④ 議席の氏名標………………………………………………………12
⑤ 議席の変更…………………………………………………………12
4 正副議長の任期……………………………………………………12
5 議会招集の申し入れ………………………………………………13
6 招集通知の送付……………………………………………………13
7 議案の配付…………………………………………………………13
8 出席要求に対する執行機関の報告………………………………13
9 応招通告書…………………………………………………………13
10 欠席届………………………………………………………………13
11 登庁表示板…………………………………………………………13
12 定例会の開議時刻…………………………………………………14
13 会議開始の放送及び号鈴…………………………………………14
14 会議中の呼び出し…………………………………………………14
15 会期中の文書配付…………………………………………………14
16 会期延長の時期……………………………………………………14
17 資料要求……………………………………………………………14
第 2 節 議案及び動議
18 意見書・決議の提出………………………………………………14
19 意見書・決議の提案理由…………………………………………14
20 請願の採択に伴う意見書・決議の提出…………………………15
21 委員会の議案提出…………………………………………………15
22 議案の用紙及び印刷配付…………………………………………15
23 議案の提出期限……………………………………………………15
24 類似趣旨の議案の調整……………………………………………15
25 議員の修正案………………………………………………………15
26 委員会条例及び会議規則の改正…………………………………15
27 事件の撤回及び訂正の申し出……………………………………16
28 特別委員会設置の動議……………………………………………16
29 議案の整理番号……………………………………………………16
30 正副議長の議案提出………………………………………………16
第 3 節 議事日程
31 議長の選挙までの議事日程………………………………………16
32 議事日程の配付……………………………………………………16
33 常任委員会へ付託した事件の議事日程…………………………16
34 議事日程の順序……………………………………………………16
35 議事日程の号数……………………………………………………17
36 議事日程の記載事項………………………………………………17
37 次回の会議日時の通告……………………………………………18
第 4 節 選 挙
38 立会人………………………………………………………………18
39 議場の閉鎖方法……………………………………………………18
40 議場の閉鎖後の出入り禁止………………………………………18
41 自席での投票………………………………………………………18
42 議長の投票…………………………………………………………18
43 当選の告知…………………………………………………………18
44 当選の承諾…………………………………………………………18
第 5 節 議 事
45 提案理由説明
① 市長の施政方針に関する発言……………………………………19
② 市長提出議案の提案理由説明……………………………………19
③ 議員提出議案の提案理由説明……………………………………19
46 議案説明会
① 開催日程……………………………………………………………19
② 傍聴…………………………………………………………………19
③ 説明順位……………………………………………………………19
④ 司会…………………………………………………………………19
⑤ 説明対象……………………………………………………………19
⑥ 質疑…………………………………………………………………19
⑦ 資料配付……………………………………………………………19
⑧ 資料要求……………………………………………………………19
47 全員協議会
① 全員協議会の議題の明確化………………………………………20
② 日程の協議…………………………………………………………20
③ 招集…………………………………………………………………20
④ 傍聴…………………………………………………………………20
⑤ 議事整理者及び代理………………………………………………20
⑥「その他」の議題表示 ……………………………………………20
⑦ 資料要求……………………………………………………………20
48 委員会付託
① 付託省略案件………………………………………………………20
② 契約案件の付託委員会……………………………………………20
③ 決算…………………………………………………………………20
④ 予算…………………………………………………………………21
⑤ 付託がえ……………………………………………………………21
49 委員長報告
① 委員長報告の作成…………………………………………………21
② 委員会の附帯決議…………………………………………………21
③ 委員会の中間報告…………………………………………………21
50 表決
① 表決の方法…………………………………………………………21
② 投票による採決……………………………………………………21
③ 委員会で否決された案件の採決方法……………………………21
④ 修正案の表決順序…………………………………………………21
⑤ 挙手採決……………………………………………………………21
⑥ 棄権…………………………………………………………………21
51 除斥…………………………………………………………………22
第 6 節 発 言
52 文書の朗読…………………………………………………………22
53 専門用語・外国語の使用…………………………………………22
54 資料等の印刷物の配付……………………………………………22
55 質疑
① 質疑通告……………………………………………………………22
② 委員会付託省略の案件に対する質疑……………………………22
③ 質疑通告書の要旨の記載…………………………………………23
④ 質疑の発言順位……………………………………………………23
⑤ 発言順位の交代……………………………………………………23
⑥ 質疑の回数…………………………………………………………23
⑦ 答弁漏れを指摘する発言…………………………………………23
⑧ 施政方針に対する質疑……………………………………………23
⑨ 質疑の自粛…………………………………………………………23
⑩ 継続審査申し出に対する質疑……………………………………23
⑪ 同一会派内の重複した質疑事項…………………………………23
⑫ 委員長報告に対する質疑…………………………………………23
⑬ 通告制による場合の無通告質疑…………………………………23
⑭ 直ちに答弁しがたい場合…………………………………………23
⑮ 質疑の方法…………………………………………………………24
⑯ 登壇…………………………………………………………………24
⑰ 説明員等の自席発言………………………………………………24
56 討論
① 賛否の明示…………………………………………………………24
② 順序…………………………………………………………………24
③ 討論通告者による無通告の討論の禁止…………………………25
57 質問
① 通告締め切り日……………………………………………………25
② 同一会派内の重複した質問事項…………………………………25
③ 一般質問通告書の要旨の記載……………………………………25
④ 発言順位……………………………………………………………25
⑤ 発言順位の交代……………………………………………………25
⑥ 登壇…………………………………………………………………25
⑦ 説明員の自席発言…………………………………………………25
⑧ 質問方法……………………………………………………………25
⑨ 直ちに答弁しがたい場合…………………………………………26
⑩ 関連質問の禁止……………………………………………………26
⑪ 時間制限……………………………………………………………26
⑫ 発言時間経過後の発言……………………………………………26
⑬ 緊急質問……………………………………………………………26
58 発言の取り消し……………………………………………………26
第 7 節 行政報告、事務報告
59 行政報告申し出の取り扱い………………………………………27
60 質疑の自粛…………………………………………………………27
61 事務報告の対象……………………………………………………27
第 8 節 会 議 録
62 会議録の用字………………………………………………………28
63 会議録署名議員……………………………………………………28
64 一般選挙後最初の議会における会議録署名議員………………28
65 会議録署名議員の署名……………………………………………28
66 議員が出席説明員として発言した場合…………………………28
67 発言取り消し部分の表示…………………………………………28
68 会議録付録の記載事項……………………………………………28
69 音声データの保存…………………………………………………29
70 音声データのコピー………………………………………………29
72 会議録の配付先……………………………………………………29
第 2 章 委員会
第 1 節 総 則
73 選任の方法…………………………………………………………29
74 常任委員の再選の禁止……………………………………………29
75 常任委員会委員の変更……………………………………………29
76 常任委員の選任の時期……………………………………………30
77 正副議長と議会運営委員、特別委員……………………………30
78 特別委員の交代……………………………………………………30
79 招集の優先権………………………………………………………30
80 議長への通知………………………………………………………30
81 会期中の招集通知の方法…………………………………………30
82 同時開催の常任委員会……………………………………………30
83 欠席の届け出………………………………………………………30
84 委員及び出席説明員の表示………………………………………30
85 議長席の位置………………………………………………………31
86 禁煙…………………………………………………………………31
87 説明員の指定………………………………………………………31
88 説明員の範囲………………………………………………………31
89 委員会開始の放送…………………………………………………31
90 委員会の傍聴………………………………………………………31
91 懇談会の開催………………………………………………………31
第 2 節 審 査
92 審査順序……………………………………………………………31
93 連合審査会
① 連合審査会の開会…………………………………………………32
② 連合審査会の座長…………………………………………………32
③ 連合審査会の議事…………………………………………………32
94 報告書等の配付……………………………………………………32
95 委員会の調査報告…………………………………………………32
96 報告書及び継続審査申出書の撤回………………………………32
97 継続審査の理由……………………………………………………32
98 継続審査中の事件の整理番号……………………………………33
99 常任委員会の所管事務調査及び特定事件の継続調査…………33
100 議会運営委員会の所管事務調査及び特定事
件の継続調査……33
101 特別委員会の継続調査……………………………………………33
102 付託事件の訂正……………………………………………………33
103 付託事件の撤回……………………………………………………33
104 参考人の選定………………………………………………………33
105 委員会視察…………………………………………………………33
106 行政報告申し出の取り扱い………………………………………34
第 3 節 発 言
107 発言の場所…………………………………………………………34
108 出席説明員の発言…………………………………………………34
109 委員長の発言………………………………………………………34
110 委員長の質疑………………………………………………………34
111 年長委員による職務代行…………………………………………34
112 資料要求……………………………………………………………34
第 4 節 表 決
113 表決の方法
① 挙手による表決……………………………………………………34
② 棄権…………………………………………………………………35
114 委員会の議決事件…………………………………………………35
第 5 節 委員会記録
115 記録の方法…………………………………………………………35
116 記録の用字…………………………………………………………35
117 記録の作成期限等…………………………………………………35
119 閲覧用記録の作成…………………………………………………35
120 発言取り消し部分の表示…………………………………………35
第 6 節 議会運営委員会
121 交渉団体……………………………………………………………35
122 交渉団体の届出等…………………………………………………36
123 議事…………………………………………………………………36
124 日程案の提出………………………………………………………36
125 請願・陳情の協議…………………………………………………36
126 委員外議員の出席及び発言………………………………………36
127 決定事項の周知……………………………………………………36
128 本会議への協議結果の報告………………………………………37
129 正副議長の視察への同行…………………………………………37
第 7 節 災害対策委員会
130 委員の出席…………………………………………………………37
131 大規模災害(地震等)時の対応
① 委員会の招集………………………………………………………37
② 災害対策特別委員会への移行……………………………………37
③ 個別処理要請の禁止………………………………………………37
第 3 章 請願・陳情
132 紹介議員
① 紹介議員とならない請願…………………………………………37
② 複数の委員会の所管にわたる請願………………………………38
③ 内容同一の請願の調整……………………………………………38
④ 請願の紹介の取り消し……………………………………………38
⑤ 正副議長の紹介の自粛……………………………………………38
133 請願・陳情書の記載事項等
① 請願・陳情者の代表………………………………………………38
② 請願・陳情の訂正…………………………………………………38
③ 意見書・決議の提出を求める請願………………………………38
④ 代理人による請願・陳情の提出…………………………………38
⑤ 請願・陳情の整理番号……………………………………………38
134 請願・陳情文書表の作成及び配付………………………………39
135 委員会付託
① 請願の受理日と委員会審査………………………………………39
② 委員会付託を省略する請願・陳情………………………………39
③ 請願の議題となる時期……………………………………………39
136 請願の紹介議員及び意見陳述者の委員会出席
① 紹介議員の委員会出席……………………………………………39
② 意見陳述者の委員会出席…………………………………………39
137 審査報告書の意見省略……………………………………………40
138 請願・陳情の委員会議決後の撤回………………………………40
139 採択請願の処理の経過及び結果報告の請求
① 処理報告……………………………………………………………40
② 処理報告書の写しの配付…………………………………………40
140 請願・陳情者への審議結果通知…………………………………40
141 陳情等の処理
① 陳情書の形式………………………………………………………40
② 陳情書の処理………………………………………………………40
③ 要望書等の参考送付………………………………………………40
142 持ち出しの禁止……………………………………………………40
143 請願・陳情署名簿の閲覧、複写及び保存年限…………………41
第 4 章 その他
第 1 節 行政委員の選任
144 常任委員会改選時における行政委員等の交代…………………41
145 選任の方法…………………………………………………………41
146 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙………………………41
第 2 節 就退任のあいさつ
147 議員の辞職…………………………………………………………41
148 正副議長の退任……………………………………………………41
149 理事者等の就退任
① 理事者、部長職就退任のあいさつ………………………………42
② 議会の同意を必要とする行政委員就任のあいさつ……………42
③ その他必要がある場合……………………………………………42
第 3 節 慶 弔
150 表彰の伝達…………………………………………………………42
151 逝去議員に対する追悼演説………………………………………42
第 4 節 一部事務組合等の活動報告
152 報告の時期…………………………………………………………42
153 報告の方法…………………………………………………………43
154 報告者………………………………………………………………43
155 活動報告の内容
① 組合議会等の開催状況……………………………………………43
② 組合議会等の会議概要……………………………………………43
③ 組合議会等の課題…………………………………………………43
156 質疑…………………………………………………………………43
157 一部事務組合等と一般質問………………………………………43
( 別紙 )
代表質疑について ………………………………………………………44
町田市議会における請願者の意見陳述について ……………………45
町田市議会オンラインを活用した委員会の開催について ……………47
第 1 章 会 議
第 1 節 総 則
1 議会の呼称(法102)
(町田市議会定例会の回数に関する条例)
(町田市議会の定例会の招集時期を定める規則)
町田市議会の呼称は、「令和○○年(○○○○年)第○回町田市議会定例会(臨時会)」とし、回数は定例会、臨時会別に歴年ごとに付する。
2 一般選挙後最初の会議の運営
一般選挙後最初の会議の運営に関しては、事務局長が会派代表者を招集して協議する。
3 議席
① 議席の決定(規 4 )
議席は、会派代表者で協議し、会派ごとに議席を割り当て、会派内において所属議員の席を決定する。
② 仮議席
一般選挙後、議長が議席を定めるまでの議席は、仮議席として臨時議長が定める。
③ 議席番号
議席番号は、議長席から見て前列左端から始まり、横に第1列を終わり、順次同様に後列に移る。
④ 議席の氏名標
議席の氏名標は、机の上、右前方に設けられた長方体黒標とし、番号を上、氏名を下に白字で記入する。
⑤ 議席の変更
議席は原則として変更しない。
4 正副議長の任期(法103)
議長及び副議長の任期については、 2年という議会の申し合わせ事項に従って運営する。
5 議会招集の申し入れ(法101)
長は、議会の招集告示前に、議長に議会招集についての申し入れを行う。
6 招集通知の送付(法101)
招集告示がなされたときは、議長は直ちに招集通知を議員に送付する。一般選挙後、最初の議会の招集通知は事務局長名で送付する。
7 議案の配付
長は、招集告示とともに議長に議案を送付する。議長が議案の送付を受けたときは、これを直ちに各会派室の議員の机上に配付する。またはこれを電子ファイルとして送付することにより配付とすることができる。ただし、議員に特別な事由があって登庁できない場合は、速やかに議案を自宅へ送付する。
後送議案及び追加議案のうち、開会日前及び休会中に送付されたものについては、送付書の写しを議員に送付する。
傍聴人の参考に資するため、本会議場及び委員会室の傍聴席に、閲覧用の議案を配置する。
8 出席要求に対する執行機関の報告(法121)
議長の出席要求に対しては、執行機関は、出席説明員の職・氏名を文書で報告する。出席説明員の変更については、あらかじめその旨を議長に文書で報告する。
9 応招通告書(規 1 )
応招の通告は、各議員の署名欄を設けた応招通告書の該当欄に自署することによって行なう。ただし、2日目以降招集に応じた者は、各自応招通告書を提出する。
10 欠席届(規 2 )
会議の欠席届け出は、やむを得ない場合、電話連絡等によることができる。この場合、事務局において届け出文書を作成する。
11 登庁表示板
議員は各自で、登庁時に登庁表示板のランプを点灯させ、退庁時にこれを消灯する。
12 定例会の開議時刻(規 9 )
第1回定例会を除く定例会初日の開議時刻は、原則として午後1時とする。
13 会議開始の放送及び号鈴(規 9 )
会議の開始、再開に当たっては、10分前に庁内放送、5分前に議事堂内放送を行ない、その旨を周知させる。
会議の開始、再開を報ずる号鈴は、議場におけるブザーとする。
14 会議中の呼び出し
会議中、原則として議員の呼び出しは行わない。
15 会期中の文書配付
会期中の議員あて議会関係文書は議員文書棚に配付するか、またはこれを電子ファイルとして送付することにより配付とすることができる。ただし、議事の進行に関連し急を要するものは、議場または会派室に配付する。
16 会期延長の時期(規 6 )
会期の延長は、最終日において行う。
17 資料要求
議員が、議会活動に必要な資料を市長部局等に要求する場合は、所定の調査依頼書を議長に提出する。議長はこの資料要求を認めたときは、議会事務局長名で担当部長あてに文書でその提出を依頼する。ただし、当市関係機関以外に資料要求する場合は、議長名で依頼する。
第 2 節 議案及び動議
18 意見書・決議の提出(規14)
意見書・決議の提出は、原則として定例会において行う。
19 意見書・決議の提案理由(規14)
意見書・決議の案文には、提案理由を付けることを要しない。
20 請願の採択に伴う意見書・決議の提出(規14)
意見書・決議の提出を求める請願が委員会付託省略の上、採択されたときは、当該請願の紹介議員が、議員提出議案を提出する。なお、紹介議員が3 人未満の場合は、他の議員の署名を得て提出する。
21 委員会の議案提出
① 委員会提出議案(法109⑥)
1 委員会提出議案の提出に当たっては全員一致を旨とし、委員長が署名する。(規14②)
2 委員会提出議案の撤回及び訂正は、全員一致をもって委員会の承認を得る。(規19③)
② 委員会の議員提出議案(規14)
委員会において提出することに決定した議員提出議案は、賛成委員が提出する。ただし、賛成委員が3人未満の場合は、他の議員の署名を得て提出する。
22 議案の用紙及び印刷配付
議案は、所定の用紙に記入して提出し、その写しを印刷して配付する。
23 議案の提出期限
議案は、定例会ごとに議会運営委員会で決定する期限までに提出しなければならない。ただし、緊急を要するものとして期限後に提出されたものについては、議会運営委員会でその取り扱いを協議する。
24 類似趣旨の議案の調整
同一会期中に類似趣旨の議案が提出されたときは、議長は提出者とその一本化について協議する。
25 議員の修正案(規17)
議員の修正案は、委員会の修正案と共通部分を持たないようできる限り配慮する。
26 委員会条例及び会議規則の改正
委員会条例及び会議規則の改正に当たっては、議会運営委員会が発議者となるものとする。
27 事件の撤回及び訂正の申し出(規19)
事件の撤回及び訂正の承認を求めようとするときは、提出者から議長に文書をもって申し出る。会議の議題になった事件の撤回及び訂正の申し出については、その取り扱いを議会運営委員会で協議し、会議では理由説明の後、直ちに採決する。
28 特別委員会設置の動議(法109・規16)
特別委員会を設置する動議は、文書による。
29 議案の整理番号
委員会提出議案及び議員提出議案の整理番号は、それぞれ歴年ごとに付する。
30 正副議長の議案提出
議長及び副議長は、議員提出議案の提出者とならない。
第 3 節 議事日程
31 議長の選挙までの議事日程(規20)
議長の選挙までの議事日程は、臨時議長が定める。
32 議事日程の配付(規20)
議事日程は会議の当日、議員文書棚あるいは議席に配付する。またはこれを電子ファイルとして送付することにより配付とすることができる。
33 常任委員会へ付託した事件の議事日程(規20・35)
常任委員会へ付託した事件を議題とするときは、各常任委員会単位で一括議題とする。ただし、除斥等の関係で、議題を分ける必要がある場合はこの限りではない。
34 議事日程の順序(規20)
議事日程の順序は、次のとおりとする。ただし、提案理由の説明は、一括して整理番号順に行う。
1 専決処分の報告
2 その他の即決案件
3 条例・その他の議案
4 予算
5 決算
6 請願・陳情
35 議事日程の号数(規20)
議事日程は、歴年ごとに号数を付する。
会議を開くに至らなかったときは、次回の会議の議事日程は、同号数とする。
36 議事日程の記載事項(規20)
議事日程の記載事項は、おおむね次の事項とする。
1 会議録署名議員の指名
2 議席の指定及び変更
3 諸報告
4 施政方針
5 会期の決定及びその延長
6 一般質問
7 請願・陳情の付託報告
8 閉会中の継続審査及び調査の申し出
9 委員会の審査及び調査の報告(中間報告を含む)
10 法令に基づく選挙
11 正副議長及び議員の辞職許可の件
12 (欠番)
13 (欠番)
14 議案等
① 予算・条例等、団体意思決定の議案
② 意見書・決議等の機関意思決定の議案
③ 地方自治法第100条の調査
④ 選任及び任命の同意等、長の事務執行要件としての議決の案件
⑤ 請願・陳情
15 決算の認定
16 専決処分の承認を求める案件
17 事件の訂正・撤回
18 特別委員会の設置
19 行政報告
37 次回の会議日時の通告
議長は、散会または延会の宣告前に次回の会議日時を通告する。
第 4 節 選 挙
38 立会人(規31)
開票の立会人は、2人とし、それぞれ別会派の議員を指名する。
39 議場の閉鎖方法(規27)
議場の閉鎖の際は、議場の各出入り口を施錠し、そこに事務局職員を配置する。
40 議場の閉鎖後の出入り禁止(規27)
議場の閉鎖後は何人も出入りできない。
41 自席での投票(規29)
身体上の支障により所定の場所で投票を行うことが困難な者は、事前に議長の許可を得て、他の議員の投票が終了した後、自席で投票することができる。
42 議長の投票(規29)
議長は、議長席において最後に投票する。
43 当選の告知(規32)
当選の告知は文書で行う。ただし、当選人が在席する場合は、選挙結果の報告後、直ちに口頭で行う。
44 当選の承諾
当選の承諾は文書で行う。ただし、議長及び副議長については、本会議中登壇して行うあいさつをもって、当選の承諾とする。
第 5 節 議 事
45 提案理由説明(規37)
① 市長の施政方針に関する発言
当初予算を審議する議会において、市長は、「施政方針」について発言する。
② 市長提出議案の提案理由説明
市長提出議案の提案理由の説明は大綱にとどめ、原則として担当副市長が行う。
③ 議員提出議案の提案理由説明
議員提出議案の提案理由説明は、原則として省略する。
46 議案説明会
① 開催日程
提案理由説明後の日程の中で、全議員を対象に議案説明会を開催し、細部の説明を求める。
② 傍聴
議案説明会はこれを公開する。ただし、公開しない場合は議長が会議に諮って決定する。
③ 説明順位
議案説明会は、常任委員会単位で行い、総務、健康福祉、文教社会、建設の順に、定例会ごとの輪番制とする。
④ 司会
議案説明会の司会は、各所管の常任委員長が行う。委員長に事故があるときは、副委員長が当たり、正副委員長とも事故のあるときは、年長委員が当たる。
⑤ 説明対象
議案説明会の対象となる議案は、予算及び条例とする。
⑥ 質疑
議案説明会において、原則として質疑は行わない。
⑦ 資料配付
議案説明会に資料を配付するときは、各所管常任委員長の許可を得る。
⑧ 資料要求
議案説明会において、議員から資料の要求があった場合、全員に配付することを会議において決定しなかったときは、当該要求議員にのみ配付する。
47 全員協議会
① 全員協議会の議題の明確化
市長または議員が全員協議会の開催要請をしようとするときは、文書で議題を明記して議長に提出する。「その他」というような表記はしない。
② 日程の協議
全員協議会の開催については、その日程を正副議長及び正副議会運営委員長が協議して決める。
③ 招集
全員協議会は議長が招集する。
④ 傍聴
全員協議会はこれを公開する。ただし、公開しない場合は議長が会議に諮って決定する。
⑤ 議事整理者及び代理
全員協議会の議事整理、秩序保持は議長が行う。議長に事故があるときは、副議長が議長の職務を行う。
⑥ 「その他」の議題表示
議長が全員協議会に配付する日程中には、議題の一部として適宜「その他」として表示することができる。
⑦ 資料要求
全員協議会において、議員から資料の要求があった場合、全員に配付することを会議において決定しなかったときは、当該要求議員にのみ配付する。
48 委員会付託(規37)
① 付託省略案件
報告案件、人事案件、損害賠償の額の決定、一部事務組合の規約、指定金融機関の指定、意見書、決議等は、委員会付託を省略する。
② 契約案件の付託委員会
契約案件は、予算計上した原課の所管常任委員会へ付託する。
③ 決算
企業会計決算は、所管の常任委員会に付託し、一般会計・各特別会計の決算は、各所管常任委員会に分割付託する。
④ 予算
一般会計予算案は、所管常任委員会に分割付託する。
⑤ 付託がえ
常任委員会または特別委員会が付託がえの申し出を行うときは、委員長から議長に理由を付して文書で申し出る。議長は、議会運営委員会の協議を経て、他の常任委員会または特別委員会に付託がえする。
49 委員長報告(規39)
① 委員長報告の作成
委員長報告は、委員長が作成する。その際書記がまとめた資料を参考にすることができる。
② 委員会の附帯決議
委員会の附帯決議は、委員会審査報告書に記載し、委員長が会議に報告する。
③ 委員会の中間報告(規45)
常任委員会及び議会運営委員会は、委員の任期満了前に、継続審査中の案件について中間報告する。
50 表決
① 表決の方法(規70〜73・75)
起立表決は、原則として電子表決システムにより行う。簡易表決及び一括採決については、議会運営委員会で協議する。
② 投票による採決(規74)
選挙の申し合わせ規定1~5を準用する。
③ 委員会で否決された案件の採決方法
委員会で否決された案件については、原案について諮る。
④ 修正案の表決順序(規77)
同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、その表決の順序を議会運営委員会で協議する。
⑤ 挙手採決
表決の際、身体上の支障により起立し難い者は、事前に議長の許可を得て、挙手の方法によることができる。
⑥ 棄権
表決の際、棄権の意思表示をする場合は、自発的に退場する。
51 除斥(法117)
除斥該当議員は、関係する事件が議題となるとき、自発的に退場する。除斥の規定は、出席説明員にも準用する。除斥された議員は、傍聴することができない。
第 6 節 発 言
52 文書の朗読(規55)
自己の発言として文書を朗読することはできない。ただし、演説の引証またはある事項の報告のため、簡潔に文書の朗読をすることはできる。
53 専門用語・外国語の使用(規55)
専門用語・外国語は、慣用語または表現の必要上やむを得ない場合のほかは、使用しない。
54 資料等の印刷物の配付(規157)
議場において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配付するときは、発言する会議前日の午後零時50分までに提出し、議長の許可を得る。議長の許可を得た印刷物は発言通告書とは別に議場で配付する。
なお、配付に当たっての著作権法等の必要な手続きは、質問・質疑を行う議員がみずから行う。さらに、パネル等を発言の際に使用する場合も、同様の手続きで議長の許可を得る。
55 質疑
① 質疑通告(規51)
質疑しようとする者は、定例会ごとに議会運営委員会で定める期限までに、文書で通告しなければならない。提出期限経過後の新たな項目の追加は認めない。発言通告の方法として、やむを得ない場合は、ファクシミリ及び電子メールを利用することもできる。
ファクシミリ及び電子メールを利用の場合は送信後、上記で定める期限までに、事務局へ電話連絡する。この電話連絡をもって、発言通告があったものとみなす。なお、質疑通告書は、原則として議会運営委員会で定める日までに事務局へ提出する。
② 委員会付託省略の案件に対する質疑(規51)
委員会付託を省略する案件に対する質疑は無通告で行う。ただし、通告があった場合は、これを優先して指名する。
③ 質疑通告書の要旨の記載(規51)
質疑通告書の「要旨」の欄には、答弁する者がこれによって答弁できるように明確に記載する。
「要旨」の欄の記載のないものは受理しない。
④ 質疑の発言順位(規51)
質疑の発言順位は通告した者について、議長がくじ引きで決める。
⑤ 発言順位の交代(規51)
発言順位は、議長の許可を得て交代することができる。交代者が得られない場合の順位は、通告者の最後とする。
⑥ 質疑の回数(規56)
質疑は、3回まで許可する。
⑦ 答弁漏れを指摘する発言(規56)
答弁漏れを指摘する発言は、回数から除く。
⑧ 施政方針に対する質疑
施政方針に対する質疑は、代表質疑を除き行わない。
⑨ 質疑の自粛
所属常任委員会所管の案件(即決するものは除く)及び議案説明会で明らかになった事項については、質疑を自粛する。
⑩ 継続審査申し出に対する質疑(規55)
継続審査申し出に対する質疑は、継続の理由以外に及んではならない。
⑪ 同一会派内の重複した質疑事項
質疑事項は、会派内で調整し、重複を避けること。
⑫ 委員長報告に対する質疑(規41)
委員長報告に対する質疑においては、委員長個人の見解、意見を求めない。
⑬ 通告制による場合の無通告質疑(規52・56)
通告制による質疑において、通告者の発言終了後、発言の通告をしない者が発言しようとするときは、関連質疑に限る。この場合質疑は簡潔に行ない、回数は2回とする。
⑭ 直ちに答弁しがたい場合
直ちに答弁しがたい場合は、当該案件に対する質疑が終結するまでに答弁しなければならない。なお、この答弁に対しては、新たに2回まで質疑を認める。
⑮ 質疑の方法
質疑に当たっては、通告事項について口頭で具体的内容を述べる。
⑯ 登壇(規50)
質疑は登壇して行う。ただし、身体上の支障等により登壇しがたい場合は、議長の許可を得て、自席で質疑することができる。再質疑及び委員会提出議案、議員提出議案、委員長報告、少数意見者の報告、修正案、動議に対する質疑は自席から行う。
⑰ 説明員等の自席発言(規50)
市長、副市長、行政委員会の長、監査委員、教育長、病院事業管理者及び市民病院院長を除く説明員の答弁並びに委員会提出議案、議員提出議案、委員長報告、少数意見者の報告、修正案及び動議に対する質疑に対する答弁は、自席から行う。
⑱ 代表質疑
定例会において代表質疑を実施する場合は別紙「代表質疑について」
のとおり行う。
56 討論
① 賛否の明示(規51)
討論を行う場合は、発言の冒頭に件名・賛否の別を明らかにする。
② 順序(規53)
討論の順序は次のとおりとする。
○ 委員長報告後直ちに討論に入る場合
1 報告可決
原案反対者→原案賛成者
2 報告否決
原案賛成者→原案反対者
3 報告修正
原案賛成者→原案・修正反対者→原案賛成者→修正賛成者
○ 委員長報告、少数意見報告後討論に入る場合
1 報告可決
原案賛成者→原案反対者
2 報告否決
原案反対者→原案賛成者
3 報告修正
修正賛成者→原案賛成者または原案反対者
③ 討論通告者による無通告の討論の禁止(規52)
同一議題において討論を通告した者は、無通告の討論は行えない。
57 質問
① 通告締め切り日(規62)
一般質問の通告締め切り期限は、一般選挙後の第1回定例会及び、代表質疑が行われる定例会を除き、開会日の3日前(土・日曜日及び休日は含まない)の正午とする。提出期限経過後の新たな項目の追加は認めない。発言通告の方法として、やむを得ない場合は、ファクシミリ及び電子メールを利用することもできる。
ファクシミリ及び電子メールを利用の場合は送信後、正午までに、事務局へ電話連絡する。この電話連絡をもって、発言通告があったものとみなす。なお、一般質問通告書は、開会日までに事務局へ提出する。
② 同一会派内の重複した質問事項
質問事項は、会派内で調整し、重複を避ける。
③ 一般質問通告書の要旨の記載(規62)
一般質問通告書の「要旨」の欄には、答弁する者がこれによって答弁できるよう明確に記載する。
「要旨」の記載のないものは受理しない。
④ 発言順位(規51)
一般質問の発言順位は、会派代表者の間において、会派から出た通告者の数に応じ、くじ引きで決定する。会派内部の順位は会派で調整し決定する。
⑤ 発言順位の交代(規51)
発言順位は、議長の許可を得て交代することができる。交代者が得られない場合は、議会運営委員会で協議して措置する。
⑥ 登壇(規50)
質問は登壇して行う。ただし、身体上の支障等により登壇しがたい場合は、議長の許可を得て、自席で質問することができる。再質問は自席から行う。
⑦ 説明員の自席発言(規50)
市長、副市長、行政委員会の長、監査委員、教育長、病院事業管理者及び市民病院院長を除く説明員の答弁は、自席から行う。
⑧ 質問方法(規62)
質問に当たっては、通告事項について口頭で具体的内容を述べる。
⑨ 直ちに答弁しがたい場合(規57・64・66)
市長その他の関係機関が、質問に対し直ちに答弁しがたい場合は、その日の会議時間内に改めて答弁を行う。なお、その際の質問時間は、前の質問の残り時間とする。
⑩ 関連質問の禁止(規62・63)
関連質問は認めない。
⑪ 時間制限(規57・64)
一般質問の発言については、回数に制限はなく、1人60分の範囲内 で行い、答弁者の発言はこれに含める。発言時間が60分に達する前、5分のとき及び60分に達したときはブザーで知らせる。
なお、自席から登壇までの移動時間等は発言時間としない。
⑫ 発言時間経過後の発言
発言時間経過後、なお発言を継続する者があるときは、マイクのスイ
ッチをきる。さらに発言を継続する場合は、議長は休憩を宣告する。
⑬ 緊急質問(規63)
緊急質問をしようとする者は、発言通告書を議長に提出する。その許否及び日程については、議会運営委員会で協議する。再質問は2回まで許可する。
58 発言の取り消し(法129・規65)
発言の取り消しは、次の議事次第による。
1 本人の申し出による場合(規65)
取り消す部分を明確にし(音声データまたは速記録の反訳等による)、議長あてに文書で申し出る。ただし、取り消す部分が簡明な場合は、口頭による申し出も認める。
申し出→許可
2 議長職権による場合(法129)
(1)要求
(2)動議
(注)「調整」は正副議長、発言者、動議提出者で行う。
第 7 節 行政報告、事務報告
59 行政報告申し出の取り扱い
執行機関から行政報告の申し出があった場合、本会議への報告の必要性については、議会運営委員会で協議し、決定する。
60 質疑の自粛
委員会において行政報告がなされたときは、当該委員は本会議における質疑を自粛する。
61 事務報告の対象
議長は、諸般の報告を事務局長に行わせる。諸般の報告事項は、おおむね次のとおりとする。
1 招集告示
2 議案の送付
3 出席要求
4 地方自治法及び地方自治法施行令に基づく報告
5 他の法令及び条例に基づく報告
6 地方自治法及び地方自治法施行令に基づく提出
7 他の法令及び条例に基づく提出
8 採択請願の処理結果報告
9 常任委員の選任及び所属変更
10 議会運営委員の選任及び辞任
11 特別委員の選任及び辞任
12 正副委員長の当選
13 法外委員会(災害対策委員会等)の結成・委員の選任及び変更
14 会派の変更・結成(解散も含む)
15 閉会中の議会活動
16 その他、議長が必要と認めたもの
第 8 節 会 議 録
62 会議録の用字
会議録の用字は、原則として、国会会議録用字例による。ただし「障害」の「害」については、法令等に定められた場合を除き、「がい」と表記する。
63 会議録署名議員(法123・規88)
会議録署名議員は、議席順に2人ずつ、在席する議員について会議の冒頭に指名する。ただし、副議長は指名しない。
64 一般選挙後最初の議会における会議録署名議員
一般選挙後最初の議会における会議録署名議員は、「仮議席の何番何某議員」と指名する。
65 会議録署名議員の署名
会議録署名議員は、議長の定めた期間内に会議録の所定の部分に署名しなければならない。
66 議員が出席説明員として発言した場合
議員が説明員として発言したときは、会議録の出席説明員欄に記載する。
67 発言取り消し部分の表示(規87)
発言取り消し部分及び議長が取り消しを命じた発言は、配付用会議録には記載せず、実線で表示する。
68 会議録付録の記載事項
会議録付録の記載事項は、次のとおりとする。
1 日程一覧表
2 委員会提出議案、議員提出議案、市長提出議案及び請願・陳情の議決結果等
3 委員会提出議案及び議員提出議案の内容(条項、字句等を整理した
ものとする。ただし、議論の対象となったものは原文を残す。)
69 音声データの保存
音声データは、会議録が作成されるまでの間保存する。
70 音声データのコピー
本会議における音声データのコピーは、議員及びその議員の発言に関する質疑、答弁、討論の部分のみ許可する。発言取り消しがあった場合には、コピーは許可しない。
この規定は、委員会にも準用する。
71 「削除」
72 会議録の配付先
会議録については、議長が署名を行った後に関係機関に配付する。
第 2 章 委 員 会
第 1 節 総 則
73 選任方法(法109、条 8 ・ 9 ・14)
① 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。
② 委員の選任に当たっては、あらかじめ会派代表者において協議する。なお、正副委員長及び議会運営委員会の委員は、会派所属議員数に比例して選出する。
74 常任委員の再選の禁止(法109、条 3 )
議員は、原則として任期中引き続き同一の常任委員会の委員に選任されない。
75 常任委員会委員の変更
常任委員会の所属の変更は、議員が死亡した場合を除き、原則として認めない。
76 常任委員の選任の時期(法109、条 3 )
任期満了による常任委員の選任は、現年度の補正予算関係議案の審議終了後に行う。
77 正副議長と議会運営委員、特別委員(法109、条 8 )
正副議長は議会運営委員会の委員とならない。また、議長については特別委員会の委員にもならない。
78 特別委員の交代(法109、条 8 ・14)
常任委員の改選時に、特別委員の交代について会派代表者で協議する。
79 招集の優先権(条15)
同一の議員を、それぞれ構成員とする常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会が同一の日に招集を予定する場合は、原則として議長に対する通知が先順のものが優先して招集する。ただし、一方の委員会にやむを得ない事情のあるときは、両委員長が招集日、時刻等について協議して決める。
80 議長への通知(規90)
委員会招集に関する議長への通知は、招集起案書をもってこれに代える。
81 会期中の招集通知の方法(条15)
会期中開催される常任委員会の招集通知及び出席要求書は、「委員会開催のお知らせ」をもって、これに代える。
82 同時開催の常任委員会
定例会中の常任委員会は、原則として総務・健康福祉及び文教社会・建設の2委員会単位で同時開催し、開催の順位は、定例会ごとの輪番制とする。
83 欠席の届け出(規91)
委員会欠席の届け出は、やむを得ない場合、電話連絡等によることができる。この場合、事務局において届け出文書を作成する。なお、開始時刻までに連絡のない者は欠席とみなす。
84 委員及び出席説明員の表示
委員会における標札は、委員は、氏名を表示し、出席説明員は、その職名を表示したものとする。また、各委員の着席位置は、これを固定する。
85 議長席の位置
委員会における議長席は、委員長席の隣りとする。
86 禁煙
何人も委員会室において喫煙してはならない。
87 説明員の指定(条21)
委員長は、部長職以上の者を指名して説明のための出席を求めることができる。
88 説明員の範囲(条21)
委員会の出席説明員は、原則として管理職以上の者とする。
89 委員会開始の放送(規93)
常任委員会及び特別委員会の開始に当たっては、10分前に庁内放送を行い、その旨を周知させる。
90 委員会の傍聴
① 除斥委員の傍聴(条18・19)
除斥された委員は傍聴することができない。
② 秘密会の傍聴(条19、規112)
秘密会における委員外議員の傍聴の許否については、委員会の決するところによる。
91 懇談会の開催
委員会は、所管事項に関し、議長の承認を得て、関係者との懇談会を開くことができる。
第 2 節 審 査
92 審査順序(規98)
① 常任委員会の審査は、所管部ごとに行い、その審査順序は、原則として定例会ごとの輪番制とする。
② 委員会の審査における議員間討議は、質疑の中で行う。
93 連合審査会
① 連合審査会の開会(規103)
委員会が連合審査会開会の必要性を認めたときは、委員長は、他の委員会の委員長に申し入れる。この申し入れを受けた委員長は、委員会に諮ってその諾否を決定し、相手方の委員長に連絡する。ただし、連合審査会開会の必要性を決定するための委員会を開くいとまがない場合、委員長は、委員の意向を電話連絡等によって確認し、その必要性を決定することができる。連合審査会開会の申し入れを受けた委員長も同様とする。
② 連合審査会の座長
連合審査会に座長を置く。座長は、連合審査会の申し入れを行った委員会の委員長とする。座長に事故がある場合は、他の委員会の委員長がその職務を行う。
③ 連合審査会の議事
連合審査会の議事は次のとおりとする。
1 案件に対する説明
2 質疑
3 両委員会の意見交換
94 報告書等の配付(規108・110・111)
委員会審査報告書、少数意見報告書及び委員会継続審査申出書は、その写しを議員及び出席説明員に配付し、朗読しない。
95 委員会の調査報告(法109、規110)
常任委員会及び議会運営委員会の所管事務調査の報告及び特別委員会の調査報告には、事実の収集のほか、判定意見を付することができる。
96 報告書及び継続審査申出書の撤回(規110・111)
議長に提出された委員会審査報告書及び委員会継続審査申出書は、やむを得ない事情がある場合に限り、本会議において当該案件が議決されるまでの間、委員会の決定により撤回することができる。
97 継続審査の理由(規111)
委員会の継続審査申出書には、具体的に明確な理由を付さなければならない。
98 継続審査中の事件の整理番号
継続審査中の事件の整理番号は、必要に応じ年号を付する。
99 常任委員会の所管事務調査及び特定事件の継続調査(法105・109⑧、規111)
常任委員会は、一般選挙後の最初の定例会において、委員の任期中行う所管事務調査の通知を行う。また、定例会ごとに、特定事件の継続調査の申し出を行う。
100議会運営委員会の所管事務調査及び特定事件の継続調査(法105・109③)
議会運営委員会は、一般選挙後最初の定例会において、所管事務調査及び議員の任期中行う特定事件の継続調査の決定を行うものとする。
101 特別委員会の継続調査(法109⑧)
特別委員会は、議会の議決により付議された事件の調査が終了するまで、閉会中も継続して調査する。
102 付託事件の訂正
委員会で審査中の事件につき訂正の申し出があった場合は、これを委員会に諮り、訂正後の内容に基づいて審査する。ただし、この場合の委員会審査報告書の提出月日は、訂正申し出を本会議で諮る日とする。
件名の訂正を行う場合には、委員会審査報告書及び当該事件を議題とす
る議事日程の件名は、訂正後のものを記載する。
103 付託事件の撤回
委員会付託後の事件の撤回については、議長は本会議に上程する前に当該委員会の委員に通知する。
104 参考人の選定(法109)
委員会において参考人を呼ぶ場合は、参考人が賛成、反対どちらか一方に偏らないよう配慮する。
105 委員会視察(規106)
常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会が視察を行う場合は、委員会において、事前に委員派遣を決定しなければならない。
106 行政報告申し出の取り扱い
執行機関から行政報告の申し出があった場合は、議長と所管委員会の正副委員長で協議し、当該委員会への報告の必要性について決定する。
第 3 節 発 言
107 発言の場所(規114)
委員会における発言は、自席で着席して行う。
108 出席説明員の発言(規114)
委員会において出席説明員が発言しようとするときは、「委員長」と呼び、自己の職名を告げ、委員長の許可を得て行う。
109 委員長の発言(規118)
委員長が委員として発言するときは、委員長席の「委員長」と表示した札を伏せることにより、そこを委員席とみなすことができる。
110 委員長の質疑(規118)
委員長が質疑をする場合は、委員の質疑終了後に行う。
111 年長委員による職務代行(規118)
正副委員長の一方が欠席した委員会において、委員長の職務を行うものが発言するときは、年長委員が委員長の職務を代行する。
112 資料要求
委員会として資料要求を行う場合は、委員会においてそのことを決定しなければならない。
第 4 節 表 決
113 表決の方法(規131・137)
① 挙手による表決
委員会における表決は、挙手の方法によることができる。
② 棄権
表決の際、棄権の意思表示をする場合は、自発的に退室する。
114 委員会の議決事件(法109)
委員会は、議事の進行上必要なもののほか、本会議に報告する案件以外決定してはならない。
第 5 節 委員会記録
115 記録の方法(条30)
委員会の議事は、原則として速記法により速記する。
116 記録の用字(条30)
記録の用字は、原則として、国会会議録用字例による。ただし、「障害」の「害」については、法令等に定められた場合を除き、「がい」と表記する。
117 記録の作成期限等(条30)
記録は、委員会の日からおおむね40日以内に作成する。録音は、委員会記録が作成されるまで保存する。
118「削除」
119 閲覧用記録の作成
記録の閲覧用に一部を作成し、総務部市政情報課において閲覧に供する。なお、議会運営委員会の記録については、付託された案件について審査した場合のみ閲覧用を作成する。
120 発言取り消し部分の表示(条30)
委員会記録の発言取り消し部分は、閲覧用には記載せず、実線で表示する。
第 6 節 議会運営委員会
121 交渉団体
交渉団体は所属議員3人以上とする。
122 交渉団体の届出等
交渉団体は、その名称、代表者の氏名、所属議員の氏名及び結成年月日を議長に文書をもって届け出るものとする。これらに変更があった場合もまた同様とする。
123 議事
付託された案件についての審査を除く議会運営委員会の議事は、協議による決定を旨とする。
124 日程案の提出
議会運営委員会に提出する日程案は、あらかじめ正副議長及び正副議会運営委員長で協議する。
125 請願・陳情の協議
請願・陳情の付託先及び陳情の取り扱いについては、議会運営委員会で協議する。
126 委員外議員の出席及び発言(規117)
① 副議長及び交渉団体に属さない議員のうち1人を委員外議員として、議会運営委員の任期中、委員会への出席を認める。ただし、付託された案件を審査する場合を除く。
② 委員が辞任した会派の議員、委員が会派を離脱した会派の議員及び委員が欠席した会派の議員を、委員外議員として委員会への出席を認める。
③ 交渉団体に属さない議員の中から出席を認められた委員外議員に支障があるときは、交渉団体に属さない他の議員が委員外議員として委員会に出席することを認める。
④ 委員外議員の発言は、副議長を除き、原則として委員の発言終了後に行
う。
127 決定事項の周知
議会運営委員は会派所属の議員に、交渉団体に属さない議員の中から出席を認められた委員外議員は交渉団体に属さないすべての議員に、それぞれ議会運営委員会の決定事項を周知しなければならない。
128 本会議への協議結果の報告
委員長は、委員会の協議結果を本会議に報告することができる。
129 正副議長の視察への同行
正副議長は議会運営委員会の視察に同行する。
第 7 節 災害対策委員会
130 委員の出席(災害対策委規約 2 )
委員は、事故により委員会に出席または参集できないときは、常任委員長は副委員長を、会派選出委員は会派所属議員を、代理者として委員会に出席または参集させる措置を講じ、速やかに委員長に通知しなければならない。
131 大規模災害(地震等)時の対応
① 委員会の招集(災害対策委規約 6 )
災害対策委員長は、災害発生後、直ちに災害対策委員会を招集する。
② 災害対策特別委員会への移行
災害対策特別委員会が設置されたときは、災害対策委員会が同特別委員会に移行する。
③ 個別処理要請の禁止
委員を初め各議員は、原則として市災害対策本部に対して個別の処理要請を行わない。
第 3 章 請願・陳情
132 紹介議員(法124)
① 紹介議員とならない請願
1 同一会期中の本会議または委員会において議決された案件と同趣旨の請願及びすでにその趣旨の実現が明らかとなっている請願については、議員は実情を説明し、紹介議員にならない。
2 議員は、その任期最終の定例会終了後は請願の紹介議員とならない。
3 常任委員会の委員及び議会運営委員会の委員は、原則としてその所管にかかわる請願の紹介議員とならない。また、常任委員会の委員及び議会運営委員会の委員の改選が行われる議会の会期中に受理される請願の紹介については、予定をされる所管委員会にかかわる請願の紹介議員とならない。
② 複数の委員会の所管にわたる請願
請願事項が2つ以上の委員会の所管にわたる請願については、紹介議員が所管委員会別に分割して複数の請願として提出するよう指導する。提出の段階でその措置がとられなかったときは、議長がそれを行い、提出者、紹介議員及び議会運営委員会へ報告する。
③ 内容同一の請願の調整
同一会期中に内容同一の請願が提出されたときは、紹介議員は提出者と協議し、原則として一本化する。
④ 請願の紹介の取り消し
請願の紹介を取り消すときは、議長に文書で申し出、議会の同意を得なければならない。ただし、委員会付託前の請願については、議長の許可を得て取り消すことができる。委員会議決後の請願の紹介取り消しは認めない。
⑤ 正副議長の紹介の自粛
議長及び副議長は紹介議員にならない。
133 請願・陳情書の記載事項等(規139)
① 請願・陳情者の代表
提出者が複数ある同一の請願及び陳情については代表者を定める。
② 請願・陳情の訂正
委員会付託後の請願・陳情の訂正は、字句・数字等趣旨を変更しない範囲に限る。趣旨の変更を要する場合は、取り下げの上再提出するものとする。
③ 意見書・決議の提出を求める請願
意見書・決議を関係機関等へ提出することを求める請願を提出する場合は、可能な限り参考資料として意見書・決議の案文を添付すること。ただし、その案文については審議・審査の対象としない。
④ 代理人による請願・陳情の提出
代理人により請願・陳情を提出するときは、代理人選任届けを添付しなければならない。
⑤ 請願・陳情の整理番号
請願及び陳情の整理番号は歴年ごとに受付順とする。2以上の委員会の所管に属する請願を分割したときは、整理番号に枝番を付す。
134 請願・陳情文書表の作成
請願・陳情文書表は、原本の写しで作成する。請願・陳情文書表作成後の紹介議員の取り下げ、追加及び請願者の署名の追加については、本会議で即決するものについては本会議に、委員会に付託するものについては直近の本会議または所管委員会に報告することとし、請願・陳情文書表にはあらわさない。
135 委員会付託(規141)
① 請願の受理日と委員会審査
定例会初日午後5時までに提出された請願書は、その定例会で審査する。定例会初日の翌日以後定例会最終日の本会議開議前に開催される議会運営委員会の開会時刻までに受理したものは委員会に付託し、閉会中の審査とする。それ以後受理したものは、次回の定例会で付託する。ただし、定例会初日の翌日以降議会運営委員会の請願付託についての協議終了前までに提出された請願のうち、議長が緊急性があると認めたものは、議会運営委員会に諮り、緊急性があると認められたものにかぎり、その定例会の委員会に付託するものとする。
② 委員会付託を省略する請願・陳情(規141)
すでに趣旨が実現されているもの、審議に急を要するもの及び国・都への意見書・決議の提出のみを求めるものについては、議会運営委員会で協議の上、付託を省略することができる。
③ 請願の議題となる時期
請願は、委員会付託のときをもって、会議の議題となったものとみなす。
136 請願の紹介議員及び意見陳述者の委員会出席
① 紹介議員の委員会出席(規142)
委員会において紹介議員の説明を求めるときは、委員長からあらかじめ文書で当該紹介議員に対し請求する。
② 意見陳述者の委員会出席(法109・条29)
委員会において本人の希望による請願者の意見陳述を実施する場合は、参考人として、別紙「町田市議会における請願者の意見陳述について」により行う。
137 審査報告書の意見省略(規143)
委員会は、請願審査の結果、特に必要がないと認めた場合は委員会審査報告書に意見を付けないことができる。
138 請願・陳情の委員会議決後の撤回
委員会の議決後の請願・陳情の撤回は認めない。
139 採択請願の処理の経過及び結果報告の請求(法125、規144)
① 処理報告
採択請願及び陳情の処理の経過並びに結果の報告は2ヵ月以内に行うものとする。
② 処理報告書の写しの配付
議長は、市長その他の関係機関から採択請願及び陳情の処理報告を受けたときは、その写しを議員に配付する。
140 請願・陳情者への審議結果通知
請願・陳情の審議の結果は、定例会ごとに提出者に文書で通知する。
なお、議員の任期満了に伴い、審議未了となった請願・陳情についてはその旨を提出者に文書で通知する。
141 陳情等の処理(規145)
① 陳情書の形式
陳情書の形式は、紹介議員の署名を除き請願書の例による。
② 陳情書の処理
陳情書は、議長から所管委員会もしくは全議員にその写しを参考送付する。ただし、議長が請願の例により処理すべきであると認めたものは、議会運営委員会に諮り、その取り扱いを決定する。
なお、陳情を請願扱いする場合の受理日と委員会審査との関係については、請願の例による。
③ 要望書等の参考送付
議長あてに提出された要望書等の文書で、議長が必要と認めたものは、所管委員会もしくは全議員にその写しを参考送付することができる。
142 持ち出しの禁止
受理した請願・陳情書等は、持ち出しできない。
143 請願・陳情署名簿の閲覧、複写及び保存年限
請願・陳情署名簿は、議員に限り閲覧に供し、複写は認めない。保存年限は1年とする。ただし、当該請願・陳情の審議が終了後、一年間は保存する。
第 4 章 そ の 他
第 1 節 行政委員の選任
144 常任委員会改選時における行政委員等の交代
常任委員会の改選時には、議員から選出された、もしくは議員に委嘱された行政委員等の交代についてを、会派代表者において協議する。
145 選任の方法
議員から選出、もしくは議員に委嘱される行政委員等は、会派代表者において協議し、会派所属議員数に比例して選出する。
146 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙
選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙は、指名推選の方法による。被推選人の決定は、会派代表者の協議または全員協議会における議員の単記無記名投票による。
補充員の順位は、被推選人の決定が投票で行われたときは、その得票順とする。
第 2 節 就退任のあいさつ
147 議員の辞職
会期中辞職した議員は、会議においてあいさつする。
148 正副議長の退任
正副議長は、退任の際、会議においてあいさつする。
149 理事者等の就退任
理事者等の就退任のあいさつは次のとおりとする。ただし、市長、副市長及び教育長を除き、再任の場合は行わない。
① 理事者、部長職就退任のあいさつ
市長、副市長、教育長、病院事業管理者及び市民病院院長就退任
会議時あいさつ
部長(相当職含む)昇格 開会前議場で紹介
部長(相当職含む)退職 閉会後議場で紹介
② 議会の同意を必要とする行政委員就任のあいさつ
代表・常勤監査委員 会議時あいさつ
監査委員(識見を有する者) 議場で休憩時あいさつ
教育委員 議場で休憩時あいさつ
選挙管理委員長 会議時あいさつ
選挙管理委員 議場で休憩時紹介
(年長者あいさつ)
農業委員会会長 会議時あいさつ
農業委員 議場で休憩時紹介
(年長者あいさつ)
③ その他必要がある場合は、議会運営委員会で協議して決定する。
第 3 節 慶 弔
150 表彰の伝達
議長会関係の表彰の伝達は、直近の定例会の閉会後に行う。
151 逝去議員に対する追悼演説
議員が逝去したときは、至近の会議において追悼演説を行う。演説を行う者は、逝去した議員と同一の常任委員会に所属し、会派の異なる地域的に最寄りの議員とする。
追悼演説に引き続き、黙祷をささげる。
第 4 節 一部事務組合等の活動報告
152 報告の時期
報告は、原則として毎年1回、第4回定例会において行う。ただし、議長が認めた場合は必要に応じて行うことができる。
153 報告の方法
報告の方法は、文書または全員協議会での報告による。
154 報告者
報告は、一部事務組合議会等の議員が行う。
155 活動報告の内容
① 組合議会等の開催状況
② 組合議会等の会議概要
・定例会
・臨時会
③ 組合議会等の課題
156 質疑
質疑は、報告内容の範囲で行う。
157 一部事務組合等と一般質問
一部事務組合等の運営についての一般質問は、地方自治法の精神に従う。
◎代表質疑について
1 .範囲と時期
代表質疑は条例・その他の議案、予算、施政方針を範囲として、第1回定
例会のみ行う。ただし、第1回定例会に骨格予算が提案された場合は、第2
回定例会で行う。なお、以下の項目を除き、質疑に関する申し合わせ事項に
従う。
2 .発言時間
発言時間は全体の持ち時間が合計で330分以内となるように、会派の
持ち時間等について、あらかじめ議会運営委員会において協議する。また、
発言時間の計測は一般質問の時間制限に準じる。
3 .個人質疑及び関連質疑
個人質疑及び関連質疑がある場合は、会派の持ち時間内で会派内議員に
認める。
4 .発言順序
会派の発言順序は会派人数の多い順とする。会派人数が同じ場合は結成
順とする。会派内で複数の質疑者がいる場合は、その会派のすべての質疑者
が質疑を終了した後、次の会派の質疑に入る。会派内の発言順序については、
通告書とあわせて文書にて提出する。
5 .発言の回数制限
発言の回数制限は行わない。
6 .会派に属さない議員
会派に属さない議員については、個人質疑とする。その持ち時間について
は、あらかじめ議会運営委員会において協議する。また、会派に属さない議
員が複数いる場合は、相互に賛同を得た場合、持ち時間を譲り受けることが
できる。
7 .その他の事項
その他の事項については、質疑に関する申し合わせ事項に従う。
◎町田市議会における請願者の意見陳述について
1 .目的
この申し合わせは、町田市議会における請願者の意見陳述を実施するた
め、必要な事項を定めることにより、直接に民意が反映する委員会審査を
行うことを目的とするものである。
2 .請願者の意見陳述
請願者の意見陳述とは、請願者が所管委員会委員に対し、提出された請願
書における「請願の趣旨」の説明として、請願を提出するに至った思い、意見
を述べることをいう。なお、意見陳述終了後、各所管委員会委員は、請願者
本人に質疑を行う。
3 .請願者の意見陳述の申請方法
(1)意見陳述の有無 請願者本人の希望制とする。
(2)意見陳述の確認方法 請願者が議会事務局に持参する場合は、請願の
提出時に事務局職員が意見陳述の確認及び説明
を行う。
請願の提出が郵送による場合は、請願者に電話
連絡ができる時のみ事務局職員が意見陳述の確
認及び説明を行う。
4 .請願者の意見陳述の方法
(1)意見陳述の開催時期 委員会開会中に行う。
(2)出席できる人数 2名までとし、請願者のみとする。
(3)意見陳述の時間 5分以内とする。
(チャイムを意見陳述終了1分前と終了時に鳴
らす。)
(4)請願者に対する質疑 委員は請願者に質疑ができる。
(請願者は委員に質疑できない。)
(5)所管する部長等の出席 原則出席し、請願者の意見陳述を聞く。
(6)意見陳述時の傍聴 傍聴を認める。
(7)意見陳述の回数 請願者の意見陳述終了後、再度同じ請願者の意
見陳述は行わない。
(8)資料等の配付について 資料の配付は、原則認めない。パネル等を利用
して意見陳述を行うことはこれを認める。
(9)同趣旨の請願が複数付 請願者同士の発言、誰が質疑応答するか等の議
託された場合 事整理をスムーズに行うため、1件ごとに個別
に意見陳述を行う。
5 .請願者の意見陳述がある場合の審査順序
(1)意見陳述を行う請願の所管部を先に行う。
(2) 所管部内での審査順序は、意見陳述を行う請願を審査の冒頭(条例の前)
とする。
(3)委員長は状況に応じて、審査順序を決定する。
6 .請願者への費用弁償 日当1,000円のみ支給する。
(証人等の実費弁償に関する条例)
◎町田市議会オンラインを活用した委員会の開催について
令和5年(2023年)6月14日決定
(第17期町田市議会改革調査特別委員会)
1 .目的
町田市議会委員会条例(昭和45年2月町田市条例第2号)第15条の2に規定する映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用した委員会の開催について、必要な事項を次のとおり定める。
2 .オンラインによる出席の手続
オンラインで委員会への出席を希望する委員は、原則として、委員会開会日の前日(土・日曜日及び休日は含まない。)の正午までに、委員長宛てにその旨を届け出なければならない。
3 .オンラインによる出席の対象事由
(1)生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症とは、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症とする。
(2)地震、台風その他の大規模な災害とは、町田市議会事業継続計画に規定する震災第3配備態勢、水災第3配備態勢等にかかる災害とする。
4 .オンラインにより出席する委員の責務
(1)オンラインにより委員会に出席する委員(以下「オンライン委員」という。)は、現に委員会室にいる状態と同様の環境を確保するため、常に映像と音声の送受信により委員会室の状態を認識しながら通話することができるようにするとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
① 情報セキュリティ対策を適切に講じること。
② オンライン委員が現にいる場所に当該委員以外の者を入れないこと。
③ 委員会に関係しない映像や音声が入り込まないようにすること。
(2)オンライン委員は、委員会開議予定時刻の30分前までに、議会事務局職員との間で通信環境が良好に保たれていることを確認するものとする。
(3)オンラインにより委員会に出席するために必要な経費は、オンライン委員の負担とする。
5 .オンラインによる出席委員の取扱い
委員長は、オンライン委員について、本人の映像及び音声のいずれも確認できる場合に限り、出席委員と認めるものとする。
6 .表決の方法等
(1)表決は、原則として挙手とし、委員会を招集する場所に現に出席している委員とオンライン委員に対し、同時に行うものとする。
(2)委員長は、簡易表決等について異議の有無を諮るときは、委員会室に出席している委員及びオンライン委員に同時に行うものとする。
(3)表決宣告の際、映像に映り込んでいないオンライン委員は、表決に加わることができない。
(4)投票による表決は、オンラインを活用した委員会においては行うことができない。
(5)オンラインを活用した委員会における選挙は、指名推選の方法で行う場合のみ行うことができる。