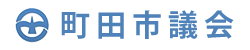
令和6年度(2024年度)町田市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定について
認定第1号
令和7年8月27日
各常任委員会議案審査報告書
【総務常任委員会】
質疑終結後、討論はありませんでした。
【健康福祉常任委員会】
質疑終結後、反対の立場から、審査した所管分については、市民の様々な状況、様々な人生の段階の一人一人の生活を支える事業が全面的に行われていること、また、困難を抱える方をいかに見つけ、アプローチするかの取組の拡充もよく分かった。その点は大いに評価をしている。しかし、質疑の中で、事務事業の見直しで生活保護利用者の方の高齢者調髪利用券の廃止が検討されて、その次の年の廃止という結論を出したことを聞いた。物価高騰の中、ぎりぎりの生活を強いられる方への補助をなくすという結論を出してしまったことは問題と考える。もう1点、2024年度は国民健康保険税の連続値上げが行われ、大幅な負担増となったこと、介護保険料、後期高齢者医療保険料の改定の年であり、これらも引上げとなった。国民健康保険の滞納者は、2024年度現年課税分で4186名、2022年度、2023年度とこちらも連続して増えている。被保険者数は減っているのに滞納の方が増えている状況である。滞納は生活のSOSだと受け止め、丁寧な対応を求める。国民健康保険は構造的な課題を抱えているわけだが、国民皆保険を維持するための重要な仕組みである。国民健康保険を支える赤字補塡の繰入れは必要なことだと考えるし、保険税率を上げ続けることは被保険者の生活に大きな負担となる。よって、認定第1号には反対するとの反対討論がありました。
【文教社会常任委員会】
質疑終結後、反対の立場から、文教社会常任委員会の所管の決算には、小学校給食の無償化、中学校全員給食の実施に向けた給食センターの整備、待機児童解消を目指す保育園増設など、子育て支援や教育の充実、また、市民の学びを保障するための施設整備や情報提供、スポーツ文化の提供など、市民の成長を保障し、心や体を育て、豊かにするために欠かせない数多くの事業が含まれていることを確認した。しかし、2024年度の事業の中で、以下の3点については問題だと考える。第1に、新たな学校づくり推進事業による学校統廃合計画である。学区は拡大して、通学距離は延び、統廃合によって生まれた危険な通学路の安全も保護者や地域の見守りに任せたままで、同時に、学童保育クラブの大規模化を進めることになり、子どもの安心できる居場所を奪っていると考える。第2に、図書館事業の再編も図書コミュニティ施設つるぼんに続いて、さるびあ図書館の統合計画が進められている点で、存続を求める市民の声に応えるべきである。第3に、今ある公共施設を減らしながら、国際工芸美術館整備事業は市民の見直しを求める声にも耳を貸さずに進められていることである。工事費が膨らむ中、見通しも立たないまま、次年度に持ち越された大きな課題となっている。これらの事業に共通するのは、町田市が構想をつくり、そして、それに基づいて計画を立てたら、何があっても計画どおりに突き進む姿勢にあることが、大きな問題の要因だと指摘し、2024年度の決算に反対するとの反対討論がありました。
【建設常任委員会】
質疑終結後、反対の立場から、第1に、野津田公園におけるスケートパーク基本設計業務委託(その2)について、2023年度にもスケートパーク基本設計が行われたが、活用せず、2024年度予算で基本設計をやり直した。公園利用者や市民から湿性植物園を保全してほしいという要望がある中、市は2023年度の設計で東側半分を残す設計を全面スケートパークにする設計に変更した。また、上の原原っぱをバスの転回広場にする基本設計、実施設計が行われるなど、野津田公園の豊かな自然と景観をコンクリートとアスファルトに変えることを市民が反対している中で強行したことは問題である。 第2に、中心市街地開発推進事業に関わる職員が増員され、町田駅周辺開発推進計画が進められたことである。D地区では、公社森野住宅居住者への説明が十分行われていないことや、協議会には半数近くの地権者が参加していないにもかかわらず、再開発事業化に向けた取組が行われている。また、A地区の調査では事業費が1,000億円になるとの試算が出るなど、大型開発に税金が無駄遣いされる危険性がある。多摩都市モノレール延伸を大前提とした町田駅周辺再開発と団地再生、公共施設再編ではなく、誰もが安心して住み続けられるまちづくりが必要だと考える。以上の理由で、認定第1号に反対するとの反対討論がありました。