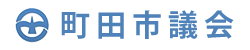
令和7年度(2025年度)町田市一般会計予算
第8号議案
令和7年2月20日
【総務常任委員会】
■政策経営部
●委員 市民意識調査の郵送は、返ってきた分だけ費用がかかるか。
●担当者 2024年度は、回収率が約42.1%、郵送が63.3%、インターネットが36.7%である。送るものと送ってきたものを郵送料として市が支払っている。
●委員 市民意識調査について回収率がダウンしているが、理由の検証はされているか。今回、昨年に比べると若干上がったが、特別な取組をされたか。
●担当者 設問数を増やさないようにして、回答しやすい環境をつくり、回答いただける人の数を増やす視点で作業を進めている。あと、全員に礼状を送付し、忘れている方の気づきの場を提供させていただき、回収率向上に向けた取組を行っている。
●委員 代表電話、イベントダイヤル等の委託で電話の交換について、障がい者雇用の導入しやすい事例としていたが、委託業者を指名するとき、どのように評価されているか。
●担当者 契約書の仕様書や、プロポーザルの選考基準に、うたい込んでない。市役所の契約約款の総則で、日本の法令を遵守するようにということがうたわれているので、そこが担保する根拠である。
■総務部・会計課
●委員 国勢調査の件について、郵送でもいいように変わったようだが、回収率はどうか。
●担当者 国勢調査は、回答の方法として、調査員に手渡しする方法と郵送で行う方法、あとインターネットで回答する方法と3つある。前回の令和2年の国勢調査の回答率は、町田市全体で78.9%、インターネット回答が41.4%、郵送もしくは手渡し回答は37.4%となっている。
●委員 情報開示請求は市政情報課の窓口ではなく、今後は法務課の窓口に行くことになるのか。
●担当者 まず、2025年度につきましては、1階の市政情報課の窓口で引き続き業務を行う予定である。2026年度につきましては、
現在の5階の法制課の執務スペースへ移転する予定である。
●委員 職員募集について、町田市の職員の障がい者雇用率の状況について、来年度どのような状況になるのか。
●担当者 障がい者雇用率だが、2024年6月時点での雇用率が2.51%だった。法定雇用率の2.8%までは約10名分ほどの雇用が足りない状況である。10月には職員課内にワークサポートルームを開設し、会計年度任用職員の採用を行った。また、職員に手帳を取得し、届け出た方もいた。次の4月の採用者数を合わせると、約10名分の採用、雇用ができることとなり、法定雇用率の達成には近づいたと考えている。しかし、これまで分母に当たる部分、全職員の数から10%除外できる特例除外率が来年度から適用されなくなるので、2025年6月の法定雇用率の達成が遠のいている。引き続き、今年度新たに始めたワークサポートルームの拡大など、市長部局のみではなく、市民病院や教育委員会などとも連携し、法定雇用率の達成に向けて努力し続けたい。
■財務部
●委員 公用車について、所有とリースの割合は。
●担当者 財務部所管の庁用車は全部で174台ある。このうちリースの割合は、139台がリースで、約80%がリースである。残りの35台は特殊な車両なのでリースにはしていない。それからEV車だが、現在1台である。
●委員 公用車の件だが、電気自動車を新たに10台導入ということだが、これはリースか、購入か。昨年、公用車の稼働率を見て減車するとのことだったが、今年の台数はどうなったか。
●担当者 10台の電気自動車は全てリースである。あと、減車だが、来年度は6台ほど減車の予定である。
●委員 174台という数字と今回10台増やすという数、それから6台減車したという数が出たが、去年から何台増えたのか減ったのか、10台増えてトータル何台になるのか。
●担当者 2024年の3月31日現在で、庁用車の数が174台、6台に関しては減車ということで来年度減る。10台に関しては、ガソリン車がEV車に変わるので減車ではない。
■防災安全部
●委員 防犯機器等購入費補助金について対象はどのようなものがあるのか。
●担当者 面格子、人感センサー、防犯フィルム、防犯性の高い錠や補助錠、雨戸、シャッター、ダミーカメラ、サムターンカバー、防犯砂利、カム送り防止具、ガードプレート、ガラス破壊センサー、防犯カメラ作動中等の防犯シール、このようなものも対象になる。
●委員 住まいの防犯対策補助事業について、申請の期間はいつからいつまでなのか。あと補助額の上限もあるか。
●担当者 対象となる防犯機器を購入する期間は2025年4月1日以降に買ったものが対象になる。補助申請受け付けは、5月15日から年内の12月25日までの間を補助申請予定で考えている。補助上限額は、物品購入費、取り付け費込みで、補助負担率は2分の1で上限額2万円となる。4万円の買物をすると、上限2万円の補助で対応することができる。
●委員 賃貸に住んでいる方は所有者の同意が必要かと思うが、自己申告でいいのか。
●担当者 都営住宅の場合、模様替え届の書類があり、管理者に出していただく。申請書の添付は求めないが、出した申告をし、補助受付をする。民間の場合も、管理業者、管理会社に、許可を、申請者が申請した上で、町田市に出す申請にサインし、届出したことを証明して出していただくことで考えている。
■経済観光部
●委員 技能功労等表彰負担金について、参加者は仕事を終えてからの参加で、夜で大変だが、改善点を事業計画に組まれているか。
●担当者 夜間の開催は変わってないが、開始まで、軽食とウェルカムドリンク、生演奏で雰囲気を出し、終了後に壇上で記念撮影し、会社のPRに使える場も提供し、改善しながら、喜ばれる表彰式になるよう工夫している。
●委員 ふるさと農具館について、三輪に施設があったが、関連は何かあるか。
●担当者 三輪にある施設の展示物だが、三輪は郷土資料に関するものと伺っている。ふるさと農具館については、地域の農業に関する展示物を展示しており、関連性はない。
●委員 町田駅前の改修について、表通りで終わりか、それ以外も先々活用エリアとして、関連する道路にまで広がるのか。
●担当者 現時点では、町田駅のマツモトキヨシから浄運寺前交差点の辺りまで、拡幅しているところで工事は一旦終了となる。こちらの活用の状況を見て、芹ヶ谷公園のほう、3・4・11号線の道路が延びており、今後、検討していく。
■農業委員会事務局
●委員 体験農業は、どんな内容で場所を決めているか。場所は決めずにローテーションでやっているか。
●担当者 体験農業は、毎年、忠生公園の田んぼを提供していただきながら実行している。
■選挙管理委員会事務局・監査事務局・議会事務局
●委員 選挙管理委員会事務局で他自治体の視察の計画はあるか。
●担当者 新年度は、参議院議員選挙、都議会議員選挙、市議・市長選挙を控えており、視察は難しい状況である。
●委員 開票を翌日にする自治体もあり検討されているか。
●担当者 近隣の八王子市が、翌日開票を取り入れていたが、即日開票に戻している実態がある。選挙の公表は、速やかに選挙人に結果を伝えるところが私たちの使命である。翌日開票する際に、月曜日、全庁的に業務を行う中で、通常の業務にも若干支障があり、即日開票を採用している。
【健康福祉常任委員会】
■地域福祉部
●委員 まちだ福祉○ごとサポートセンターだが、10月に開設された南地域とか忠生地域の状況について聞きたい。
●担当者 忠生と南の地域だが、それぞれ、相談件数で言うと、2024年10月から1月までの4か月間になるが、忠生地域が208件、1か月当たりだと52件、そして南地域が283件、1か月当たりで71件になっている。
■いきいき生活部
●委員 地域密着型サービス施設整備補助金で、多額な金額が補助されているが、これは来年度、2025年度は幾つの整備を考えているのか。
●担当者 地域密着型サービスのうち、高齢者認知症グループホームに対する補助、また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護への補助金、看護小規模多機能型居宅介護の整備について補助金を計上している。初めの高齢者認知症グループホームについては4施設分、計上している。その後の定期巡回・随時対応型訪問介護看護については1施設分、また、介護小規模多機能型居宅介護についても1施設分、計上している。
■保健所
●委員 子どもDXの一環として、母子保健のオンラインサービス、PMHに、今年度、接続予定だと認識しているが、都内では、今年度、町田市を含む6市町が
接続予定だと聞いているが、その取組について、どのような点が変更されて、市民にとりどのように便利になるのかを確認したい。
●担当者 PMHが導入されることにより市民にとって何が変わるのかだが、現在、乳幼児健診においては、自宅に紙の問診票を送り、自宅で記入されたものを、当日、健診会場に持ってきてもらう状況にある。PMHを導入することにより、マイナポータル上から問診票への記入ができるようになるので、健診当日には、
マイナンバーカードを1つ持参すれば、問診票の持参は不要。
質疑終結後、反対の立場から、
本常任委員会で審議した予算は、市民の生活の土台、生まれたときから亡くなるまでという本当に長期の人生に関わる一番暮らしと困難の解消に密着をしている行政の取組であると理解をしている。そうした中、新年度予算には、高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業として補聴器の購入費の助成制度が盛り込まれたことは、市民の要望を受け止め、具現化する町田市の姿勢を評価している。まちだ福祉○ごとサポートセンター全域での実施、避難行動要支援者避難支援体制整備事業の市内全域への拡大など、様々、重要な予算化がされていると認識している。一方、2025年度の予算には、国民健康保険のほうでも議論をしたが、国民健康保険財政の健全化という国の要請の下、一般会計からの赤字繰入れが市の計画に基づき減らされたため、1.7億円が被保険者への負担増となった。国民健康保険会計の予算でも申したが、市民の生活実態に配慮した負担増を行わない対応が必要だと考える。この点の理由から、第8号議案には反対するとの反対討論がありました。
【文教社会常任委員会】
■市民部
●委員 市民協働推進費の相談委託料だが、昨年よりも減額になっている。その内容についてと相談事業はどのような状況なのか。
●担当者 相談委託料の減額については、委託内容を見直して、面接の相談日を月4日から月3日に減らすことを考えている。ただし、月3日に稼働日は減らすが、総体的に相談を受けられる人数については変わらないので、効率化が図られたと捉えている。女性悩みごと相談の現状だが、相談内容としては、日常生活におけるふとした悩み事から、人間関係、体の不調に関すること、それからDVに関する相談まで、内容は多岐にわたっている。また、相談件数については、例年おおむね2,300件程度で、件数は横ばいである。
●委員 町内会・自治会連合会のところで、加入の促進もしていると思うが、どのような形で次年度は予定をしているか、外国籍の住民も町内会・自治会に関わってもらって、地域のイベントなど一緒にしていると思うが、外国籍の方々に対する周知、加入の促進活動などがあれば教えてほしい。
●担当者 町内会連合会と連携しての加入促進は、一般的に、まず転入手続時にチラシを配ることや、新小学1年生の保護者向けに、町内会の加入のお知らせを配っている。町内会・自治会連合会と連携をして、市庁舎で開催をされた「まちだECO to フェスタ」にもブースを一緒に出展し、町内会・自治会が、どういう活動をしているか分からない方への普及啓発として、「まちカフェ!」も含めて、イベントでの普及啓発活動も行っている。2022年から行っている取組としては、デジタル町内会「いちのいち」も行っている。加入促進の方向でも、未加入者が加入できる特徴もあり、町内会に入らない理由として、何を町内会がやっているか分からないという声もあるが、この「いちのいち」を通して町内会の実際に行っている内容を知ることによって、少しでも加入促進につながればという思いである。外国籍の方であるが、前年度、外国籍の方にも分かりやすい易しい日本語で書かれた町内会・自治会への普及啓発チラシ、あとは外国語も含めて、加入促進の普及啓発チラシを町内会・自治会連合会と一緒に作成をした。そのようなチラシも含めて、外国の方についても町内会という取組、加入促進を進めていきたい。
■文化スポーツ振興部
●委員 (仮称)国際工芸美術館整備工事修正設計業務委託料と(仮称)公園案内棟/喫茶/版画工房/アート体験棟の再積算業務委託料について、何を行うのか詳細に教えてほしい。
●担当者 (仮称)国際工芸美術館整備工事修正設計業務委託料については、2025年4月1日施行の改正建築物省エネ法により引き上げられる省エネ基準に適合させるために設計の一部を修正するものである。あわせて、最新の工事単価の反映や見積りの再取得などにより、入札のための工事予定価格の算出を行う。(仮称)公園案内棟/喫茶/版画工房/アート体験棟の再積算業務委託料については、最新の工事単価の反映や見積りの再取得などにより、入札のための工事予定価格を算出するものである。
●委員 CMを行って、金額的な算出や、クレーンの話など様々出ていたと思うが、この参考意見はどのように反映されるのか。今回やることによって影響はあるか。例えば事業者が決まらなかった場合は、アート体験棟などの計画はどうなるのか。
●担当者 2023年度から行ったCMについては、工事費や工法などが適切であるかについて検討し、その過程でクレーンの配置の提案など、いろいろな検討をしている。内容については、今年度行っているCM、設計反映で反映をしているので、その内容を踏まえて、今後工事発注していく。また、スケジュールについては、国際工芸美術館は、修正設計を行った後、下期で整備工事を行う。また、アート体験棟については再積算を行った上での工事で、アート体験棟が先行して工事を行う形でスケジュールを考えている。国際工芸美術館の整備工事の影響がアート体験棟にあるのかというと、基本的に先に工事をやるので大きな影響はなく、先行してアート体験棟の工事ができると考えている。
●委員 パラアリーナで、ブラインドサッカーやパラバドミントンの団体などに対して、300席の観客席になるという話はされているのか。300席では使えないから、利用しませんと言われたら元も子もないと思うが、意見交換などは行われているのか。
●担当者 地区計画で、観覧席を造る場合には200平米の制限がある中で、300席程度までなら設けられるのではないかと考えている。利用者ニーズだが、あそこの立地条件の中で興行をするのは難しい場所ではあるが、様々なパラスポーツの協会や連盟からは、障がい者スポーツをする、練習する場所が非常に足りないことや、普通の体育館であると車椅子は断られてしまうという意見は聞いている。多少遠くても車で移動して、練習しているとの声ももらっているので、ある程度ニーズは見込めると考えている。
■子ども生活部
●委員 ここ近年の子ども生活部の予算の推移としては年々増えているのか、その要因があれば教えてもらいたい。また、児童手当の推移としては、年々増えているのか。
●担当者 全体としては、制度上いろいろ増えているものがある。一例は高校生の医療費の関係等が大きいものではある。児童手当は、2024年度に制度改正があり、12月支給分、10月、11月分から3人目の子には3万円を支給するようになり、その部分が非常に上がった。
●委員 学童保育クラブの育成環境の改善があるが、事業・業務委託料と鶴川中央学童保育クラブ設置工事費の2項目、内容について教えてもらいたい。
●担当者 学童保育クラブにかかる主な事業費について、事業・業務委託料は3点あり、1つが昼食提供の実施にかかる費用で、夏休みの期間中のうち10日間、鶴川エリアの給食センターで調理した昼食を食缶に入れて学童保育クラブへ運搬する実証実験を行う。ここで挙げている事業費は7クラブ分の学童保育クラブに運搬された昼食を受け取り、盛り付け、片づけ、清掃を行う業務を町田市シルバー人材センターに委託する費用として計上している。2つ目は、統合する学童保育クラブの降所の見守りの委託事業になる。これは、本町田ひなた学童保育クラブと成瀬学童保育クラブの安全対策として見守り人員を配置する業務をシルバー人材センターに委託する費用を計上している。3点目は、鶴川中央学童保育クラブにおける夜間の通学路の安全対策を講じるための状況調査として事業者に委託する費用を計上している。鶴川中央学童保育クラブの設置工事費は、視聴覚室を育成スペースとして活用するためにパーティションや扉をつけるなどの設置工事費になる。
■学校教育部
●委員 分教室型学びの多様化学校について、どのような形でスタートするのか、また、生徒は何人ぐらいいるのか。
●担当者 分教室型学びの多様化学校は、今度の4月から開室し、中学校1年生が6名、中学校2年生が1名、中学校3年生が6名、計12名でスタートする。特徴としては、子どもたちの社会的自立を目指し、特別の教育課程等を編成し、基礎的、基本的な学習を行うことや、体験活動等も行いながら、成功体験を積み重ねたりする機会をつくり出すような学びの場であることを
想定して行っていきたい。基本的には数学科と外国語科、理科の3教科を担任が担い、それ以外の教科は、会計年度任用職員の教員の配置や、講師の先生等に協力をもらい、全教科、指導に当たる。それとは別に、スクールカウンセラー、養護教諭、授業の補助員もつけ、支援をしていきたい。
●委員 路線バスの利用をする子どもたちへの見守り指導員は何人をどのような形で配置するのか。
●担当者 バスでの見守りについては、朝は1時間、帰りは2時間、それぞれバス停と学校に2人立ってもらう予定である。各学期の始まりの3週間、慣れるまでの間、それぞれ対応する予定である。
■生涯学習部
●委員 図書購入費については、紙の書籍の購入費ということか。また、去年に比べて費用が減っていると思うが、経年の予算と比べてどうなっているのか、考え方について聞きたい。
●担当者 書かれているのは、紙の図書購入費である。昨年と比べて、減っている事実はある。考え方については、ここで鶴川図書館がなくなって、図書コミュニティ施設に変わるので、その分は減らして、逆につるかわ図書コミュニティ施設に対しての補助金の中である程度、図書購入費は想定している。あと、電子書籍でコンテンツ料を本年度と比べて増やしているので、コンテンツ自体は全体としては維持または向上していると認識している。
●委員 市指定無形民俗文化財の活動に係る経費の一部を助成しますと書いてあるが、具体的にどういったものなのか、後継者、担い手不足もあると思うが、地域の中で担い手を育成する、募集するような費用や考え方、取組があれば、聞きたい。
●担当者 例えば金井の獅子舞や、相原にある丸山獅子舞などに対して補助を出しているので、活動場所や、例えば獅子頭が壊れてしまった際の修理などで使ってもらっている。今年度から取組として、獅子舞の後継者に育ってもらえればと、保存会と一緒に講座を開いて、小学生に来てもらい、興味を持ってもらおうと行っている。まだ金井の獅子舞はやれていないが、そういった活動や、こういった団体がどういう活動をしているのかという周知の冊子などを今後作っていくので、そういった形で応援をしていきたい。
質疑終結後、反対の立場から、本予算には、18歳までの医療費助成の所得制限の撤廃や中学校全員給食の全域でのスタートなどが盛り込まれている。市民にとっても喜ばしい事業もたくさんある。しかし、一方で事業者も仮契約を解除した国際工芸美術館の整備関連の予算や、新たな学校づくり推進計画の学校統合も大きく見直しが行われてはいるが、予算が入っている。いずれも、立ち止まって市民と共に見直しを行うべき事業だと考える。また、学校統合に併せて学童保育クラブも統合され、大規模化されることも重大な問題であり、そのリスクを軽減するための対応策も不十分だと考える。放課後の子どもたちがゆったりできる場所になるのか大変心配する。いずれも市民が見直しを求める声を上げているのに、期限ありきで進められているのも2025年度の予算の中に盛り込まれている。以上の点から、文教社会常任委員会所管部分、2025年度の予算に反対するとの反対討論がありました。
次に、賛成の立場から、今回の予算には、待機児童解消対策事業や学校給食無償化事業など、将来を担う子どもたちへの予算が盛り込まれており、おおむね理解はしている。しかし、芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム推進事業の(仮称)国際工芸美術館整備工事について、以下の点につき、指摘をする。これまで、(仮称)国際工芸美術館整備事業については、住民説明責任や財政投資、設計内容の在り方など、様々な面から本会議の場で議論されながら整備工事予算が可決してきた。また、この間、昨今の資材高騰や労務費などの高騰の影響に伴い、2023年度以降、当初予定だった整備工事費28.5億円に対し3回、増額補正を行いながらも入札中止3回と、非常に紆余曲折をしながら、市議会も都度、増額補正を可決してきた。その後、2024年度の第1回定例会では、3回目の入札中止を受け、急遽、コンストラクションマネジメントの導入をし、より適正な積算を行い、整備工事費は総額約43億8,000万円という予算規模となった。そして、昨年12月議会において、ようやく契約議案が可決され、本契約にこぎ着け、2029年オープンに向け事業を進める予定となった。しかし、本年1月末に仮契約を締結した事業者より、仮契約解除の申出があり、現状に至る。この事業者の行為は全国を見渡しても見当たらないケースであり、契約議案を議決した町田市議会としても到底受け入れられない行為であり、事業者に対して非常に遺憾の念を持たざるを得ない。しかし、だからこそ、今後、訴訟事件となる可能性があるにせよ、しっかりと要因の解明、検証をし、改めて事業者選定を行うことが賢明であると考える。これまでの度重なる増額補正、入札中止を考慮すれば、計画スケジュールを最優先し、整備工事事業の早期情報提供のみの工夫により性急な事業者選定を行うよりも、要因の検証を行い、戦略立てて予算を立てるべきと考える。よって、(仮称)国際工芸美術館整備工事について、今回の契約解除の要因の解明、検証を行った上で修正設計及び事業者選定を行うことを強く求め、賛成討論とするとの賛成討論がありました。
【建設常任委員会】
■環境資源部
●委員 容器包装プラスチック分別収集・資源化啓発事業で、横浜線から北の地域から回収することで、資源化量が4,000トン増えて、温室効果ガスが1万1,000トン減るという理解でいいのか。
●担当者 そのとおりである。
●委員 指標として協力率があるが、今、先行している南がどのぐらいで、新規に始まるものはどのくらいを見込んでいるか。
●担当者 分別協力率としては現在35%程度になるが、それを40%にしていきたいと考えている。
●委員 容器包装プラスチックの回収については、マナーの点に課題はあるか。
●担当者 リレーセンターみなみで、汚れているものとか、刃物とか、実際にはリサイクルできないものが入っているという状況である。
●委員 町内会・自治会の説明会について、どういった説明をするつもりか。
●担当者 まず、何が容器包装プラスチックに該当するのか、どういうふうに汚れを落とすのかだとか、出し方についての説明を予定している。
●委員 町内会・自治会の会員でない方へのアプローチはどう考えているか。
●担当者 町内会・自治会向けと市民センターでの説明会に加えて、全戸配布として、まず9月に収集カレンダーを配布、もう一つ、2月にチラシと併せてピンクのプラスチック専用袋を各対象の地域に配布して、十分な周知を図っていく。
●委員 子どもたちにしっかりとこれを理解していってもらうというのが大きく、重要だと思う。分別を意識させる取組をやるべきだと思うが。
●担当者 2025年度は容器包装プラスチックの内容を中心に出前講座を実施して、子どもたちについて、おうちでも実践してねということで、親御さんにも伝えてもらうような形で周知につなげていきたいと考えている。
●委員 清掃第二事業場閉鎖ということで、年間の運営コストはどの程度変わっていくのか。
●担当者 新たに外部委託すると費用としては上がっていくと考えている。市内の業者では想定している規模は処理できるところがないので、外部の業者にお願いをしていくようになる。
●委員 運営費だとどのくらいなのか。
●担当者 今の施設と外部委託費との比較で、処理費自体は大きな差はないと思っている。ただし、外部委託のほうが、市外の施設に運ぶ運搬費の分が大きく、大体、単年で2,000万円から3,000万円ぐらいかと考えている。
■道路部
●委員 無電柱化ということで、来年度は何を行うのか。
●担当者 町田37号線(文学館通り)は、来年度、一方通行化工事と支障物移設、ガス、水道、東電だとかの支障物施設の工事を考えている。
町田835号線、通称中央通りは、引き続き本体工事を続けるのと、ガスの支障物の移設工事を予定している。
●委員 いつ完全に無電中化できるのか。
●担当者 実際に開通できるのが中央通りは2029年度完了を目指している。町田37号線は、事業認定期間が2030年度までとなっている。
●委員 道路維持費で道路の傷みとともに予算はたくさん取れているのか。
●担当者 道路維持事業は、道路以外にも橋梁、エスカレーターといったところも劣化が進んでいるので、バランスを考え、今回の予算構成になった。市民要望を100%満足するには、足りていないが、交通の安全を担保するには、きちんと確保した予算であると考えている。
●委員 野津田公園南側アクセス環境改善で、整備工事が行われた場合は、通行止めなどは生じるか。
●担当者 もし通行止めが必要な場合は、改めて沿道の方々に説明していこうと思っている。基本的に、なるべく通行止めはしない方向で考えている。
●委員 本事業に当たって、バスがどの方向から入るか、検討したか。
●担当者 今現在はまだどこから、どう入ってくるかは決まっていない。
●委員 警察との協議がなされているのか。
●担当者 警察とは協議をしていて、状況は、都道の部分がまだ拡幅されていないところで、そこから進入する際にはガードマンを立てようという話と、大型バスが2台すれ違える幅員にはなっていないので、上のほうでもガードマンを立てて、バスのすれ違いを調整していく必要があるということで、調整している。
●委員 町田駅周辺について、駐輪場が足りているか。
●担当者 駅全体では空いている場所はあるが、止めたいところは集中して、場所がないといった現状は認識している。
●委員 何か対策のようなものは考えているか。
●担当者 既存の自転車駐車場の施設の中で、例えば100台置けるところを120台置けるようにするとか、既存の配置の見直しが一つ考えられ、あとは、例えば森野第一駐輪場のところで空いている土地があったりするので、少し拡張できないかというような対策を考えている。
■都市づくり部
●委員 新バスセンター等概略検討委託料はどういう使い方をする予定か。
●担当者 現在あるバスセンターを、A地区と呼んでいる街区まで拡張する形で検討しており、今回の開発の中でバスセンターに全部集約をかけて、分かりやすいバスセンターをつくっていくのが開発の目的の一つとなっている。
●委員 スケジュールを教えてほしい。
●担当者 各地区が開発しないと、今の道路の範囲を広げるとかは物理的に不可能で、ある程度、モノレールが実現する2030年代後半といった時期が一つ目安になると思っている。
●委員 集約したことによって影響を受ける商店街が出たり、いろいろな問題があると思う。どういった議論になっているか。
●担当者 単にバスセンターだけで考えるよりは、周辺の道路とかペデストリアンデッキも含めて、どういうふうに動線として乗り換えさせるのか、町なかに人を流していくのかも併せて検討をしていくので、必ずしも全部を1か所に集約かけることを絶対の目的にしているわけではない。
●委員 森野住宅周辺地区道路概略設計委託料はどういう使い方か。
●担当者 JRの下をどれぐらいの高さを取りながら、くぐっていけるのかとか、相模原側に接続するときにどれぐらい橋の構造を見直さなければいけないかとか、詳細を詰めていく費用になっている。
●委員 横浜線のアンダーパスの道路設計の予算について、目的は。
●担当者 今回、開発に合わせて、そこにしっかりとした道路を造って、安全な交通環境をつくっていくのが一番の目的である。
●委員 どの程度、具体的な検討をすることになるのか。
●担当者 今、この地区でまちづくり協議会を開催しながら、地権者の皆さんとどういう土地利用にしていくかも同時に検討は進めている。ただし、土地利用の検討のほうは、まだ具体的な絵まで出てくるような段階ではないので、少し道路の設計のほうが先行している形になる。
●委員 小田急多摩線の延伸事業で共同調査負担金が約3倍に増えたが、次期の交通政策審議会の答申が出るまでこのような感じか。
●担当者 2025年度、2026年度で債務負担を組み、その中で需要予測をしていく予定でいる。恐らく2027年か2028年頃から始まる交通政策審議会の部会みたいなものがあるので、資料を提出して、最終的には、明確に整備すべき路線というような答申が出るように目指してやっていきたい。
●委員 町田市中心市街地まちづくり推進事業について、シネマコンプレックス、ライブホールなどの施設については、基本的に公費を投入していく考え方か。
●担当者 基本的には、各4地区とも民間投資による開発を前提として今検討している。ただし、エンタメ系の施設は、なかなか民間投資だけで実現がしづらい部分もあるので、一定の市の投資というのも考えられる。
●委員 野津田公園スポーツの森整備事業で、スケートパーク整備事業と南側入口転回広場について、説明会で出た多くの意見も反映されない状況をどう捉えているか。
●担当者 スケートパークの場合は、希少植物については、直接動かせないようなものは線形を変えて設計をするという工夫を、既に内容としては反映をしており、説明会の意見で新たに変えたものはないというのは、もう既に反映をしていると理解をしている。
●委員 話合いの場だとかを、もっと設けていくべきだと思うが、いかがか。
●担当者 説明会に来る方はそれぞれの意見を持っているので、それについて聞いて、反映できるものは反映したいという思いで毎回臨んでいる。市ができるところとできないところは明確にし、理解いただけるよう丁寧に対応をしてきている。
●委員 南側入口転回広場について、実際に工事に入ると思が、それに当たって、住民や利用者に対して働きかけは今後予定しているか。
●担当者 地域の方に具体的な工事の施工方法とか、工事車両のこともあるので、丁寧に説明していきたい。
●委員 今後の説明会については、もっと幅広く周知してもらいたいが、いかがか。
●担当者 世帯数で言うと大体3,200世帯に周知ができるように考えており、公園の中の部分的な施設を整備する際の説明会としては、適切だと考えている。
●委員 転回広場の利用について、改めて、なぜ必要なのか。
●担当者 野津田公園が避難施設として指定をされている施設であり、基本計画策定時に、防災上の役割、機能として、野津田公園に大型車両が入れるアクセス口をつくろうというのは基本計画の中で考えている。
●委員 鶴川駅周辺街づくり事業について、ポプリホールに向かう商店街が影響を受けないよう何か対応策はあるのか。
●担当者 駅の北口の南北自由通路から和光大学ポプリホール鶴川に至る動線を、賑わい回遊動線と位置づけて、にぎわいをいろいろな形でつくっていきながら、西側の商店街のほうにも動線を流していくことを考えていきたい。
●委員 多摩都市モノレールまちづくり推進事業について、木曽山崎団地地区において、「暮らしやすい」エリアのところで、今ある5階建ての団地ではなく、もっと高層の住宅を集約していくのか。
●担当者 まだ案の段階ではあるが、基本的に多世代にとって暮らしやすいエリアというのは現状の団地を残すようなイメージでいる。今、新たに高層のマンションなどを建てる議論は行っていない。
■下水道部
●委員 市町村総合交付金はどういう位置づけで補助を出されるものなのか。
●担当者 総額が都から提示をされて、特に下水道部として、こういう事業があるから予算要求をするという形ではなく、振り分け先が下水道部になったと理解している。
質疑終結後、反対の立場から、第1に、多摩都市モノレール延伸事業と連携して行われる町田駅周辺開発推進事業についてで、4,000億円規模が予想される8.4ヘクタールの大規模な民間再開発に、多大な市民の税金が投じられることである。また、約400世帯の公社住民が暮らすD地区において、道路設計が先行して行われていることは、この地区の住民の住まいや生活を保障する対策がきちんと示されていないことと併せて問題である。デベロッパーや大規模地権者の利益優先のまちづくりではなく、住民と地域商店街に寄り添ったまちづくりへの転換を求める。第2に、モノレール延伸事業の採算性について検討しているとのことだが、内容を市民に公開し、徹底した検証を行うべきである。また、現在の市民生活に寄り添った路線バスなど公共交通の充実に取り組むべきである。木曽山崎団地などでの団地再生計画については、安心して住み続けられる団地への見直しを求める。第3に、野津田公園スポーツの森事業のスケートパーク整備事業と南側入口転回広場とアクセス道路の整備については、野津田公園の自然を守ってほしいという市民の声が広がっている。また、スポーツイベントでの大型バスの通行についても、道路渋滞への影響に対する市民の不安は解消されていない。市民の声に基づいて事業内容を再検討すべきである。以上の理由から、第八号議案に反対するとの反対討論がありました。
次に、賛成の立場から、今回の一般会計予算においては、資源やごみ処理施設をはじめとした環境向上に関する予算、また、各道路や駅の整備における住民の利便性の向上に資する予算及び中心市街地開発推進事業をはじめとした市内経済の活性化やにぎわいの創出に関する予算が計上されており、一定の理解をしているところである。しかし、野津田公園スポーツの森整備事業については、以下の点を指摘せざるを得ない。まず1点目、スケートパーク整備実施設委託料についてで、本事業については、2023年度に基本設計が行われたが、それでは不足があったということで、2024年度にも再度基本設計がなされたという、ほかでは例を見ない異例の事業となっている。2024年第3回定例会時の本委員会における行政報告によると、2023年度時の基本設計では、調整池全体の約半分がスケートパークとして利用される形となっていた。これは従来より議会でも答弁がなされていたとおりの設計であった。しかしながら、2024年8月時点での基本設計では、調整池をほぼ全域使用してのスケートパーク設置という大幅な変更がなされた。これは従来の議会での答弁とは全く異なったものであり、2024年度当初予算の審議時における答弁からも想定できない設計変更となっている。この変更は議会だけではなく、市民や公園利用者にも大きな衝撃をもたらした。実際に市民向け説明会の際にも、多くの反対の意見が挙げられていた。しかしながら、市は今回の答弁のとおり、あくまで基本設計に基づいて進める、説明会での意見については対応しないということだった。市民や公園利用者の理解がほとんど得られていない状況にもかかわらず、このままの状態で基本設計から実施設計を進めることは、行政の専横と言わざるを得ない行為であり、市民や公園利用者を無視していることは明らかである。このような市民協働とかけ離れた行為は、町田市の基本構想・基本計画であるまちだ未来づくりビジョン2040にも反しており、許されることではない。したがって、あくまで基本設計どおりに進める前提ではなく、市民や公園利用者と建設計画に対する協議を幅広く行うこと、さらには建設スケジュール、計画の変更も含めた柔軟な対応を行っていくことを求める。次に2点目、南側入口転回広場整備工事費及び野津田公園南側アクセス環境改善整備工事費・用地購入費についてである。南側入口転回広場整備工事費についても、野津田公園の豊かな環境に負担を与えるものであり、その影響を最小限にすることを我が会派はこれまでの議会でも求めてきた。さらに、公園利用団体等からの意見もあり、結果としてススキの丘側の斜面地や草地ビオトープ部分が残されたものだと解釈している。また、防災機能向上の点を含め、本事業については一定の理解をしている。しかしながら、スケートパーク整備事業と同様に、市民や利用者への周知や説明、協議がほとんどなされていないという状況にある。そのため、本事業の必要性が伝わっておらず、先日、行われた説明会でも多くの反対や不安の声が上がった。整備工事に当たっては、同様のことを繰り返さないよう周知や説明、協議を徹底することが必要である。特に説明会等開催の際には、周知範囲を広げ、広く市民や公園利用者に伝わる方法とすること、また、説明会の時間帯や場所、回数について、多くの市民や公園利用者が参加できる形式とすることを求める。なお、野津田公園南側アクセス環境改善整備工事費・用地購入費は、南側入口転回広場整備工事費に付随するものであり、同様の対応を求める。以上2点を条件に賛成するとの賛成討論がありました。
次に、賛成の立場から、公園の予算に関しては、市民の意見が反映されずに計画が進んでいる部分があるので、市民の意見を反映させてまちづくりを進めるためにも、予算の修正案を提案することを前提に予算に賛成するとの賛成討論がありました。