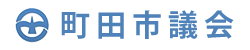
令和4年度(2022年度)町田市一般会計補正予算(第1号)
第45号議案
令和4年6月2日
【総務常任委員会】
■政策経営部
●委員 町田市いじめ問題調査委員会について、2021年度内の終結を想定していたが、広範囲にわたったことで時間を要している、引き続き調査を要するということだが、どのような要因が遅らせている背景にあるのか。
●担当者 実際に調査を進める中で、調査委員からこういう資料はないか、資料に書いてあることはどういうことかという、いろいろオーダーがあり、調査が広範囲にわたると申し上げた。
●委員 2022年度6月補正における取り組みで、調査は非常に丁寧に進めていただいたほうがいいが、再発防止策は早急に取りまとめて、教育委員会等に付託すべきだが、これは別で取りまとめるということは難しいか。
●担当者 調査の中で事実確認をしながら、委員会としての評価をしていく。それを踏まえた上で教育委員会の対応を検証し、今後是正すべきところがあるのか、お示ししていただくことになろうかと思う。実態の確認が必要なので、その後に再発防止に向けた部分を委員会としてお示しいただく。
●委員 2022年度6月補正における取り組みということで、市職員を対象とした研修・講座を実施するということだが、どのくらいの対象人員、講座内容なのかお知らせいただきたい。
●担当者 1つは、プレスリリースの添削講座を予定している。これは、プレスリリースの発信内容や発信するタイミング等のリリースのコツを学び、実際にリリースして効果を検証するような内容である。もう1つは、最近SNSが非常に有効なので、SNSの勉強会である。全庁の職員を対象にしたのがSNS、プレスリリースの添削講座は、担当者に特化する。
■財務部
●委員 健康福祉会館の改修工事について、医師会と歯科医師会等々と話合いをきちんとされているのか。
●担当者 医師会等と話をしながら相談をし、施設に影響がないような形で、工事工程を組んでいきたいと考えている。
●委員 調査等委託料についてだが、エレベーターの構造耐力上の安全性確保は全ての公共施設で調査に入るのか。段階的に、分けてやるのか。
●担当者 今年度、想定しているのは5基程度の調査をすることで考えている。営繕課で更新対象となるエレベーターは、全体で50基程度あるので、10年程度で調査が完了して随時更新することで考えている。
●委員 エレベーターの点検だが、調査を行うことにした理由は何か。
●担当者 建築基準法が改正され、国から、エレベーターなどに対する脱落防止などの地震対策が要求されている。そこで、地震に対するエレベーターの構造的な安全性を確かめる必要があり、更新時期を直近で迎えているエレベーター施設について、事前に設計や構造的な強化が必要かどうかを判断するため、調査を行う。
■経済観光部
●委員 小山田小学校北側の民有地の山林の整備のための測量予算だが、今回、ここがなぜ対象となったのか。
●担当者 町田市では、里山環境活用保全計画を定め、民有地も含めた形での山林の再生と活用を進めていくことを方針として掲げており、市有地の山林の活用と併せて、民有地の山林も含めて、再生、活用について一緒に進めたいという話があれば、そこも併せて進めていくということが大きな考え方である。既に民有林の部分で地元の方が小山田の森委員会という形で活動し、山林の下草刈(したくさか)りや、そこを整備した後を活用する動き、今後、そこを広めていきたいという動きが地元にあり、そこからスタートした。
●委員 作業路に関してだが、400メートル延長することで、幅はどれぐらい確保しなければならないといった決まりがあるのか。
●担当者 約1.8メートルの幅で400メートルを整備していくという考え方である。
【健康福祉常任委員会】
■地域福祉部
●委員 地域福祉コーディネーターだが、どういったところに委託するのか。相原地区と小山地区をモデル地域にして地域福祉コーディネーターなどのアウトリーチ支援をすると言っているが、この2つの地域を選んだ理由は。
●担当者 地域福祉コーディネーターについては、1つの分野に限って動くというよりは、様々な高齢者、障がい者、子ども、保健、あとは地域の、例えば活動も含めて様々な点から相談を受けることを想定しているので、福祉の分野の多くのまたがった知識を持った方、そして地域に根差して活動を行っているような事業所、そういった方を抱えている事業所を業務委託先として検討している。また、相原地区、小山地区をなぜモデル地区として選んだかであるが、相原地区においては人口に占める介護認定率、また障がい者の割合が市平均よりも高い状況にある。そして、小山地区においては人口に占める年少人口の割合が最も高いということで、これから子どもに係る相談が増えてくるだろうと考えている。それと、相原地区においては、昨年度、相原地区 社会福祉 協議会が立ち上がり、地域に根差したボランティア活動をしてもらっていると考えている。地域福祉コーディネーターは、地域で活動している方たちと連携しながら情報をもらって支援につなげていく動きも取っていくので、地域活動が盛んな地域というところでもある。あとは、モデル地区として進めていくに当たって、人口規模の多いところで進めてしまうと検証として難しい部分も出てくると考えており、相原地区、小山地区は人口規模的にも適しているところでもあるので、総合的に勘案してモデル地区を選んだ。
●委員 地域における福祉の困りごと相談支援体制 強化事業で、拠点のようなものを考えていると言っていたが、928万2千円で拠点まで確保できるのか。
●担当者 地域福祉コーディネーターの活動拠点として、モデル地区の中に拠点を置いて、地域から直接相談も受けられるような窓口も併設したい。地域福祉コーディネーターの動きとしては、どちらかというとアウトリーチ型になるので、地域に出ていって情報を取得して、その方を支援機関につなげていく動きを取っていくが、電話での相談も出てくることが想定される。さらに窓口に来る方もいる。今回、1月から3月までの事業費として持たせてもらっている。年間で考えると約4倍になるので、3か月分としては適正な金額と認識している。
●委員 継続したアウトリーチ事業ということで、いろいろな福祉の総合的な問題というのは、支援は欲しいが、なかなかそれを自らすることができない方のサインをいかに拾い上げていくのかが大事だと思うが、どういうものを想定しているか。
●担当者 継続的なアウトリーチという形を今回示したのは、特に地域の中で必要な支援につながっていない方の事例として、自ら支援が必要であることを認識していない方も含まれてくると思うし、また、支援自体を拒否している方もいることを認識している。そういった方においては、1回訪問してすぐに支援機関につながるよりは、長い月日をかけて関係を構築して、信頼関係を得てからやっと支援機関につながる動きになってくるので、継続的に、定期的にアウトリーチをして関係を構築して支援機関につなげていく役割をコーディネーターが担っていくものである。
●委員 今はあんしん相談室もあると思う。重なる部分はどうなのか。
●担当者 コーディネーターは分野を限らないので、重なる部分があっていいものだと認識している。役割を分けてしまうと、地域の中のアンテナが少なくなってしまうので、地域福祉コーディネーターが先に把握した場合は、初動になった上で、専門の支援機関と連携しながら動いていくことを想定している。
●委員 相当高いスキルが要求されるが、できる方は簡単に見つかるのか。
●担当者 地域福祉コーディネーターは、様々な専門機関と連携しながら進めていくので、1人で全てが解決できるとは認識していない。地域福祉コーディネーター自身は様々な経験を積みながら事例を蓄積して動いていくので、まずは、様々な事例を重ねて、その上で、コンシェルジュのような動きをしていく。例えば、その方はどういった課題を抱えているのか、その課題を整理して専門機関につないでいく役割を担うので、様々な分野の制度を認識しているというところが大事と思っている。そのため、そこから先の専門的な支援となると、コーディネーターの部分で不足してくる部分もあるので、難しいとは思っているが、そういった事例を重ねることで、多くのことを学んでいくものと思っている。
●委員 協議体を新しくつくって相談支援体制を考えていく中に、市が今考える相談支援の、地域福祉のコーディネーターを置いていくようなイメージを持っているのか、全体の枠組みを示してもらいたい。
●担当者 地域福祉コーディネーターは、どれだけ広いネットワークを持っているかによって支援のつなげる先が増えてくると認識している。そのためには、地域の中のネットワークを構築するために顔の見える関係性をつくっていく必要があると思っているので、コーディネーターを中心として様々な支援機関が入った連絡会を地域の中で立ち上げていきたい。また、全てコーディネーター任せにならないように、現在、市の中では、相談支援体制を検討していくに当たっての包括的 相談支援体制 検討委員会を立ち上げて、横の連携を深めていこうと検討を進めている。
●委員 今、制度も、いろいろな施策も複雑化してきて、重複していく中で、少しスリムにしていくような、点検がきちんとされているのか。
●担当者 様々な制度があって、重複してどちらを選んだらいいかといったことも出てくると思っている。そういった場合、本人の話を聞いて、庁内の中で、分野をまたいだ支援会議を開いて、担当部署が集まって話し合って、本人にとって何がよりよいものなのかを検討した上で支援を展開していこうという考えを持っている。
●委員 イメージとして民間機関が入るのか確認したいのと、既存の体制で解決ができない問題が出てきたときに、地域福祉コーディネーターはどういったところをよりどころにして対応していくのか。何か枠組みを設けて、その中で意思決定をしていくのか。
●担当者 支援会議の中に民間機関が入ってくるのかだが、重層的 支援会議と国では言ったりするが、個人情報の問題があるので、本人同意を取った上で民間の機関を入れて支援会議を開くことも想定している。民間機関には、民間の社会福祉法人だけではなくて、例えばNPO法人や町内会・自治会も考えられる。あとは警察、医師や弁護士ということで、その方の事例に合わせて必要な方をお呼び立てして会議を開いて支援を行っていくことを想定している。それでも、公的支援では解決できないものもあると思う。その場合については、例えばひきこもりの方であれば、地域で清掃活動をしている自治会・町内会があれば、そこに一緒に入ってもらって最初の軽作業からやってもらうなど、様々なパターンがあると思うが、地域の活動団体に協力を仰ぎながら進めていこうという考えである。それでも難しい場合においては、その方の経過観察が非常に大事だと思っている。公的支援を受けられるようになった時期を決して見逃してはならないと思っているので、地域福祉コーディネーターは、その方を継続的に見守っていくところを担っていけたらと考えている。
●委員 一人一人に寄り添った丁寧な対応をしていくということだったが、恐らくそれぞれ個別支援計画のようなものをつくっていくと思うが、モデル地区での運用では何名程度を想定しているか。
●担当者 今回のモデル地区の中での人員だが、地域福祉コーディネーター業務に関わる人員として、2地区に合計で4名 配置する予定である。その中でコーディネーターとして中心的な役割を担うのが2名で、補助を行っていく職員として2名を想定している。
●委員 これから恐らくたくさんの制度のはざまと対峙することになると思うが、1名が主担当で1名が補助というところで、とても大きなものを担っていくと思うが、それを補完する役割として地域のNPOや地域活動団体だが、それがない場合に新たに立ち上げたり政策提言するのも地域福祉コーディネーターの役割になっていくというイメージか。
●担当者 例えば地域の中における地域活動を生み出していくのも一つの役割と認識している。地域活動を受け入れてくれるような動きがないと、支援機関は増えていかないので、高齢者の分野で言えば生活支援コーディネーターが地域活動も生み出していくような動きをしてくれているが、そういったコーディネーターと連携しながら様々な地域におけるメニューをつくっていくのが一つと思っている。先行導入市の事例で言えば、例えばサロン活動をつくったり、ひきこもりの当事者会のような会議体を立ち上げたりとか、地域の中の活動の要望も聞きながら、個別支援だけではなくて地域づくり支援にも携わっていくのが地域福祉コーディネーターの役割となっている。
●委員 今回、モデル地区で年明けから検証するということだが、来年度以降のイメージが決まっていれば教えてもらいたい。
●担当者 当事業においては、町田市 5ヵ年計画 22‐26の重点事業として位置づけられており、2025年度までに市内の町内会・自治会 連合会 単位の10地区にエリアを拡大して、市内全域への整備という形で進めていきたい。
●委員 地域福祉コーディネーターの役割について、専門機関につなぐような役割は民生委員も今 担っていると思うが、活動内容で重複する部分があるので、不足している民生委員の補完的な意味合いがあるのか。また、地域福祉コーディネーターの身分について、市が直接雇うのか。
●担当者 民生委員の負担も増えてきており、継続的に関わらなければいけない状況も大きく増えてきている中で、不足している民生委員の欠員を埋めるということではないが、負担を軽減するというところも一つの目的である。また、複合化、複雑化した困り事にコンサル的な役割を果たして、しっかりと課題を整理して適切な支援機関につないでいく役割も一つである。そして、市が直接、地域福祉コーディネーターを雇うというよりは、委託先の機関でそういった方を雇ってもらう、また、そういった方を育成していくことも委託先の機関では役割として出てくると考えている。
●委員 民生委員は活動費、実費はもらえるものの無報酬でやっていて、仮に同じようなことを報酬をもらっている人がやると、民生委員から見たときに不公平感のようなものが生まれて、さらに、やめようという形で民生委員が減ってくる事態を不安視しているが、そのようなことがないように、民生委員以上のことをやってもらえればいいと考えているが。
●担当者 民生委員と地域福祉コーディネーターの違いとして、地域福祉の専門職という形になるので、民生委員では難しい案件を地域福祉コーディネーターが担っていく。そのため、民生委員にも現状やってもらっているところはこれまでどおり担ってもらいたいという考えの中で、民生委員が、例えば地域の中のアンテナとして活動している中で、どうしたらいいか分からないときに、一つの相談場所となる。そして、コーディネーターが課題を整理して支援機関につなげていく、その後の担い手となっていくというところも想定しているので、民生委員よりも困難ケースを抱えていくことが想定されている。
■保健所
●委員 子宮頸がんワクチンの関係で、接種機会を逃して任意で接種した方の助成はどういうルールで行われるのか。例えば金額的なこと、ワクチンの種類の制約、あるいはどのくらいの期間までか。どういったものを根拠として事務手続上は費用を助成するか。また、その周知啓発についてはどのように行うのか。
●担当者 今、市は医師会と事務手続について協議を進めている。現状、国から示されているのは接種記録証と領収書に基づいて助成するということだが、町田市が助成している金額が1回につき1万8,300円である。そのため、同額のものを上限として、申請があった場合についてはお返しする予定になっている。また、接種対象のワクチンについては、定期接種が現状、サーバリックスとガーダシルというものが認められているが、そちらを接種された方を償還払いの対象と考えている。また、周知方法については、現状、任意で打たれた方は市で把握できていない。今回、キャッチアップ接種について予算の補正をしている。それ以降について、また7月に入ってからになると思うが、対象になる9学年の方に対してキャッチアップ接種の案内を送る。その中に償還払いの話も記載して対象者の方に周知を図るということを考えている。
●委員 新型コロナウイルスワクチンの供給量について確認したいが、昨年、自治体への振り分けについて少しワクチンの確保が危惧された時期があったと思うが、その点について今の状況は。
●担当者 ワクチンは十分確保できているので、安心して接種してもらえると考えている。
●委員 ワクチンは、例えば集団のほうに予定していたものが個人病院に転用される使われ方は認められているのか。
●担当者 ワクチンについては、個別の医療機関のほうがニーズが高ければそちらに振り分けるとか、柔軟に対応できる。
●委員 目標は立てているのか。
●担当者 目標設定は特にしていない。特に小児の接種については努力義務が外れているので、勧奨については、受けることができるという形で伝えている。ただ、12歳以上の方の接種については東京都の水準を上回るレベルを維持していくというところは目安として置いている。
【文教社会常任委員会】
■市民部
●委員 南町田 駅前連絡所を閉鎖する中で、例えばおむつ専用袋やボランティア袋の配布などの窓口や機能については他のところでやりとりができるようになるのか。
●担当者 行政窓口の機能、いろいろ申請をお預かりするものについては、2023年4月までに南町田グランベリーパーク駅近く、周辺に機能を移転する。そちらのほうに店舗を構えている事業者に委託をしていくということを考えている。委託の内容の中には、例えば妊娠届のお預かりや、マル子の医療費の申請のお預かりも含まれているが、同時に、おむつ袋、ボランティア袋の配付も含めることで進めている。市民の方(かた)には、窓口に寄っていただくことになるが、比較的利用が多いため、なるべくお手間をかけないような形を考えており、その受取り方法をそのまま駅周辺でも行えるように準備を進めている。
■文化スポーツ振興部
●委員 芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム推進事業について、今回 基本設計と実施設計合わせて予算が出ていると思うが、どういった意図があって合わせて上程しているのか。
●担当者 今回は基本設計、実施設計を一連の作業の中で一体的に計画していくこと、今後の整備スケジュールなどを考慮して、基本設計と実施設計を併せて予算計上している。具体的には、工房・アート体験機能や喫茶機能について、専門家や工房利用者の方を含めて、実施設計段階で反映するような具体的なご意見までいただいている。基本設計に入った際、これはまだ実施設計だから今後検討するということではなく、検討できる部分は実施設計の部分であっても、一部でも検討する。今回かなり具体的なご意見をいただいているので、基本設計と実施設計を一体的に進めていきたいと考えている。
●委員 今回基本設計と実施設計を一緒に債務負担行為で予算を出しているが、一緒にする大きなメリットはあるのか。
●担当者 今まで工房利用者の方、近隣の方々のお話を伺う中では、まだ基本計画なので、基本設計が始まり次第、お示ししていくということを発言したことで、それを本当にやってくれるのだろうかと思われる部分もあった。そうした意味で実施設計の中で検討すべきものを含めて少しでも提示をしながら、一体的に進められるのではないかと考えている。
■子ども生活部
●委員 コロナウイルス感染症対策の休園等をした場合の措置について、今、臨時休園するというのは、具体的にどういう状況で臨時休園が起こっているのか。
●担当者 休園になるケースというのは、ほとんどが職員、保育士が複数名 濃厚接触に該当して保育が継続できないような状態になったときに、休園という形にさせていただいている。濃厚接触以外にも、発症された方(かた)が大勢出ているというケースが一番休園になりやすく、そのときも、基本的には園内や姉妹園で何とか融通をつけてもらってやっているが、どうしようもないケースのときだけ、基本的には休園という形にしている。
■学校教育部
●委員 中学校給食センター整備事業費について、今回、PFI、リース方式でこれからプロポーザル等を出していくと思うが、公募において、業者選定で重視すべき点が、給食センターの整備運営の方針になってくるかと思うが、どのように考えているか。
●担当者 プロポーザルで重点的にPFI事業者等に求めていく能力については、公募を通じて、事業者に対しては、まずは町田の重視する施設のコンセプト「食を通した地域みんなの健康づくり拠点」をしっかりと理解していただくことが前提になってくる。その上で、市が求めるサービス水準を企画していく事業提案力、そして、食を通した地域健康づくりの活動を幅広に具現化し、実施していく事業展開力、この事業企画力と事業展開力という2つの能力を公募の中で重視していきたいと考えている。
■生涯学習部
●委員 電子書籍サービスの導入について、これから事業者決定になっていくと思うが、どんな利用方法 またはどれぐらいの図書、本の数、種類が対象になっていくのか。
●担当者 今年度については、3,500冊程度 導入したいと考えている。使われ方については、まずは今回、デジタルデバイドの解消に向けて導入したということもあるので、いわゆるデジタルサービスに不慣れな高齢者の方に使ってもらえるところをまずは進めていきたいと考えている。その後は来館しなくても使えるという利点が電子の場合にはあるので、今まで図書館自体に来られなかった方などのアクセスや子どもたちを想定して今後展開していきたいと考えている。
質疑終結後、まず、反対の立場から、本補正予算には、学校給食の食材費物価上昇に対応する予算や保育士への賃金改善の予算、学校・保育所新型コロナ感染対策、またデジタルデバイドの解消など、喫緊の課題への重要な予算が組まれていることは大いに評価をする。一方、南町田 駅前連絡所の閉所、機能移転について、場所を借りていた相手の都合のため仕方がないことであり、機能の代替については対応を今後も含め取られていることは理解をするが、利用の多い連絡所であること、マイナンバーカードを持っていない方にとっては大きなサービスの低下になってしまうため、窓口対応のできる代替など、さらに再検討をお願いしたいと思っている。予算については、本予算の中で芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム推進事業では、(仮称)公園案内棟/喫茶/工房・アート体験棟の基本・実施設計 等の予算において、工房利用者や、また関係者の合意のないまま、国際版画美術館から版画工房の移設という形で計画が具体化されているということが審議の中で明らかになっている。理解を得られた段階ではない中で、基本設計・実施設計を計上することは問題だと考え、以上の理由により第四十五号議案に反対とするとの反対討論がありました。次に、賛成の立場から、今回の予算には、保育士の処遇改善や学童保育など、子ども生活の環境整備に関する予算や中学校給食センター整備事業、図書館機能・サービスの充実などが盛り込まれているなど、一定の理解はしているところである。しかし、芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム推進事業について、何点か指摘する。初めに、(仮称)公園案内棟/喫茶/工房・アート体験棟基本・実施設計業務委託料について申し上げる。この設計業務は、基本設計と実施設計が同時に提案されていることである。本来であれば、議会審議基準である1億7,000万円の事業予算規模の場合、基本設計完了後に実施設計の審議に入るのが通常であると思う。これは基本設計を行った上で実施設計に入るまでの期間でしっかりとした収支計画やコンセプト、整備計画について議論し、より充実した実施設計を行うためである。しかし、今回の予算計上では、基本設計と実施設計が同時に提案されており、委員会での質疑では、基本設計と実施設計を同時に提案することにより包括的な意見対応ができるとの提案理由が述べられているが、さきに述べたように、基本設計と実施設計を分けて提案しても対応は可能であり、特段納得ができる提案理由とは言えず、スケジュールありきと指摘せざるを得ない。これは以前に、地域住民との協議に入るときの協議中については、スケジュールに関しても柔軟に対応するという当初の市の姿勢に相反する行為であり、協議を行う本来のしっかりと政策面、財政面を議論し、実施設計に入るという意義が抜けていると考える。もう1点は、令和2年度3月議会で審議された(仮称)国際工芸美術館 及び国際版画美術館との一体的整備の予算が提案された際にも、基本設計予算と実施設計予算が同時に提案されたという点である。このときにも我が会派では今回同様の意見を申し上げた。結果として、新型コロナウイルス感染症の影響で基本設計が大幅に遅延し、当初予定していた時期に予算規模が示せなくなった。また、設計事業者が行った基本設計を経て(仮称)国際工芸美術館 及び国際版画美術館の一体化工事部分の予定金額が倍額との設計結果になったにもかかわらず、当委員会には行政側から具体的な行政報告がなされなかった。また、スケジュールありきで基本設計と実施設計を進めた結果、地域住民などとの協議不足が明るみになり、結果、地域住民との協議の場を設けなければならない状況となった。これはまさに基本設計と実施設計の予算を抱き合わせで予算を可決した弊害であると考える。最後に、今回の委員会において(仮称)国際工芸美術館 及び国際版画美術館の一体的整備の附帯決議である実施設計における予算規模に対する根拠を示すことに対する理解が得られるような削減計画や維持管理費の計画などが全くなされていない点である。事業規模については、実施設計時にしっかり削減していくという答弁を繰り返していたにもかかわらず、実施設計を再開している中で事業規模の削減計画が示されないことは遺憾と言わざるを得ない。このように、これから議論するべき事項が多い中で、基本設計と実施設計を抱き合わせで予算提案することは、令和4年度3月定例会の文教社会常任委員会 附帯決議の内容に対する逸脱行為であると判断する。以上の点については早急な対応と説明を強く求めるものである。よって、我が会派は、(仮称)公園案内棟/喫茶/工房・アート体験棟基本・実施設計業務委託料予算については、基本設計と実施設計を分けて提案するべきであると表明し、さらに地域住民などに継続した協議を行うことを条件に、賛成討論とするとの賛成討論がありました。
【建設常任委員会】
■環境資源部
担当者の説明をおおむね了としました。
■道路部
●委員 無電柱化チャレンジ支援事業について、制度の概要を少し教えていただきたい。
●担当者 東京都で持っている無電柱化推進計画、また、町田市の無電柱化推進計画の基本的な考え方としては、防災とか安全とか景観という主な考え方があり、歩行の邪魔になるという意見もあるかと思うが、路線として寄与するところを選んでいくということになる。歩道の幅員が2.5メートル以下になってしまうと、地上機器も置けないとなると、生活道路、小さな道路というのはなかなか難しいというところで、12メートル以上の幅員のところを主に選ばせていただいている。地域防災計画とか都市計画マスタープランに基づいた路線として考えられるところであったり、都市計画道路というお話があったが、第4次事業化ということで事業を推進しているところ、あと、まちづくりに寄与するというところで中央通りとか文学館通りというところを選ばせていただいているので、生活道路に対応できる性格にはなっていない。
●委員 無電柱化チャレンジ支援事業について、埋設管情報を、道路の工事等を含めた中で情報提供があるので、それを収集して一つの地図情報まちだの中でそういうことをやってくれると、そこが一つの基準になると思う。どこの誰の管だとか、整理できてくると、将来の無電柱化の業務効率が上がってくるのかなと思っているが、それはどう考えているのか。
●担当者 今回行う無電柱化のこの3路線については、当然事業が完了したときには、埋設物台帳という形で台帳を整備する予定としている。委員おっしゃるとおり、そういった埋設物の情報がきっちり市でも把握できるという状況が大切なのかなと思っている。
●委員 道路維持費について、路面性状調査を堺地区で実施しますとあるが、この方法について伺いたい。
●担当者 機器を搭載した車両で路面を実際に走って、路面の状況を確認するというものである。
■都市づくり部
●委員 公園緑地費について、蓮田緑地の件だが、2023年にプレオープンということで、先行して開花時期に合わせて駐車場を造るとあるが、これは何台で、これは有料か。
●担当者 台数については30台弱ぐらいになろうかと思う。ただ、常時駐車場として造るのではなくて、花が見られる時期だけ開放する。それ以外は多目的広場として使うということで運用を考えている。駐車場代は無料である。
●委員 モノレール沿線基礎調査支援委託料について、モノレールを延伸させていく上で、町田市に求められていく採算性などを確保するため、まちづくりを進めていくために行われる調査かと思うが、目的、算出根拠と期待される成果物、併せて調査内容について説明いただきたい。
●担当者 沿線人口とか土地利用の状況、建物の立地状況など現状把握をしたいと思う。関係計画などの基本的な情報を収集する予定である。
質疑終結後、反対の立場から、まず第1点目の理由だが、多摩都市モノレール町田方面延伸のための基礎調査委託料が入っていることである。小野路方面への延長ルートが決定して、事業予算を大幅に増額することが予想される。そういう中で町田市に求められる採算性を上げるためのまちづくりを進めるための調査であり、採算を確保することを前提とした基礎調査ということになると思う。地域住民の利便性を優先的に考えるのであれば、道路整備とほぼ同時にスタートできるBRTのような手法も検討すべきと考え、反対する。第2は、芹ヶ谷公園芸術の杜パークミュージアム推進事業の関連の予算についてである。芹ヶ谷公園の緑、また現在ある国際版画美術館との景観が市民の皆さんの大事な資源として、また愛されている施設の一つである。市がこれから資源として市民合意を十分得ないことによって、こうした環境を壊すことは問題だと考える。また、芹ヶ谷公園芸術の杜整備計画自体についても、市民の方々が見直しを求める声を上げている。住民合意が図られていないという整備計画の一体の予算であり、この予算について反対するとの反対討論がありました。