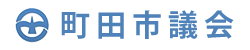
令和3年度(2021年度)町田市介護保険事業会計補正予算(第1号)
第49号議案
令和3年6月7日
●委員 デジタルデバイド対応促進事業において、「地域の自主グループの代表者等を対象に講座を実施し、オンライン活動サポーターを養成します」とあるが、オンライン活動サポーターの対象とすべきものも含めて、どのぐらいの人数を養成したいのか。
●担当者 まだ仮称だが、このオンラインサポーターの養成は、既に活動している自主グループの代表者の方が主な対象になっている。スマホのオンライン等の技能は、今、習得しているものがどこまでかということは問わないつもりでいる。講座修了後にほかの方々に教える意欲のある方を対象にするつもりでいる。その人数だが、高齢者支援センターが市内に12か所あるが、そちらの地域の複数のグループの代表者を対象に考えており、詳細な数は未定だが、1回の講座で約5名から10名程度できると想定している。各12の高齢者支援センターで1クールずつ行うので12講座、およそ10人と考えると大体120人ぐらいの方を想定している。
●委員 目的に、「誰もがデジタル社会の恩恵を実感できる“まちだ”を実現します」と書いてある。スケジュールも来年の3月までということが示されている。そうすると、来年の3月までに誰もがデジタル社会の恩恵を実感できる町田を実現できるという想定の下に行われている事業なのか。
●担当者 想定をしているところ、主にいきいき生活部では、自主グループの方々に講座を行っていきたいと考えている。オンラインサポーターが大体120人前後と話したが、今、町田で行われている自主グループで、特に運動のグループとか、いわゆる町田を元気にするトレーニング、町トレを行っている自主グループを対象に考えているが、たしか164グループだったと思う。中には、希望されない方もいるとは思うが、おおむね今年度で行き渡ると思っている。その状況を見ながら、また来年度以降も引き続き検討していきたいと考えている。
●委員 高齢者の方にオンラインのサポートということだが、高齢者の方々が何をできるようになってほしいのか、例えば、自宅で買物ができるようにしたいとか、町田市のLINE登録をしてもらって、何かあったときに町田市からの連絡が簡単にできるようにするとか、サポートを受けた高齢者の方にこれだけはできるようになってほしいというような、何か具体的な目標はあるか。
●担当者 いきいき生活部のこの事業については、既存の、もしくは新規の自主グループで、今、外出自粛だとか運動不足になっていて、そういった方々の身体とか認知レベルの低下が懸念されているので、そういったグループの活動を促進するところを目標にしている。一方で、例えば、個人個人でオンラインツールを使って、買物とか、市の情報を得るといったところは生涯学習部のほうで個別に対応していくものと考えている。
●委員 今回、ほかにもタブレット端末の貸出しというのが生涯学習部の予算であるが、こことの連携はどのようになっているか。
●担当者 基本的に、対象者として、いきいき生活部と生涯学習部とすみ分けをしながら、連携も必要と考えている。対象者としては、いきいき生活部では、基本的にスマホを持っている方、生涯学習部では、年齢を問わずにスマホを持っていない方、それだけではないが、そういった形で主に区分けをしている。その中で、例えば、スマホを持っていない方である程度グループ活動とかをされたいという方であれば、こちらの事業を活用してもらっても構わないし、そういった方で、グループとかは望んでいないけれども、基本的な操作が必要だ、習得したいという希望の方であれば、生涯学習部が実施しているところに案内をしていきたい。また、メインのグループの活動だけではなくて、そこから派生した効果というのはあると思う。例えば、買物の情報提供とか、情報の交換とか、場合によってはLINEを使って日常の安否確認とか見守り的な効果もあると考えているので、そこはやりながら、色々な効果を期待したい。
●委員 今回の歳入だが、全額都の支出金を使って行う事業だが、この予算の内訳、算出根拠について聞きたい。
●担当者 算出根拠だが、3つあって、まず1つ目のオンライン介護予防・フレイル予防活動 自主グループ育成事業委託料279万円だが、市内に12か所ある各高齢者支援センターで1回の講座、単価として2万7千円を見込んでいる。連続講座を考えており、オンラインの技能を習得するのに3回程度、また、介護予防のアクティビティーといった内容を習得するのに4回から5回程度、大体8回ぐらいを想定しているので、2万7千円掛ける8回掛ける12センター。あわせて、ポータブルのWi-Fiのレンタルが必要になってくるので、それを5千円程度で、8回だから3か月分として12センターで、合わせて279万円と考えている。それと、2つ目のオンラインサポーターの養成だが、講座の単価は2万7千円を想定している。オンラインの技能習得は既に活動しているグループが主体であるので、オンラインの技能習得のみで考えると3回を想定していて、2万7千円掛ける3回掛ける12センター。また、同様にモバイルのWi-Fiレンタルが5千円で、これは3回だから1か月を想定して、12センター分ということで103万8千円。最後に3つ目、相談拠点の設置を考えているが、年度の後半、10月から3月の半年間、週1回程度で計算をして、具体的に市内の事業者等に見積りを伺って、例えば相談員の派遣の人件費とか技術料、または交通費等を含めて564万円。合わせてこの予算という形になっている。
●委員 まず、自主グループの育成事業だが、基本、スマホを持っている方や、町トレとか、色々な事業をやっている団体を対象にということだったが、持っていない方は、結構いると思う。今あるサークルとかの中でスマホにアクセスできない方がはじかれていくような心配というのはないか。それから、オンラインツールの、高齢者支援センターに拠点を設置するという説明で、週1回開催されるとある。どのような方がどのような形でそこにアクセスしていくのか、どういうサービス提供を行っていくのか。
●担当者 まず1つ目、スマホを持っていない方も多いのではないかということで、そういった方が排斥されていかないかだが、本当に持っていない方でスマホの基本的な操作が分からない方の場合は、例えば、生涯学習部の事業だとか、場合によってはシルバー人材センターでもスマホ教室、パソコン教室、または個人レッスンもやっていると聞いているので、そういったところを踏まえながら丁寧に案内をしていきたい。オンラインのサポーターを、例えば市とかで設定するというよりも、養成講座を受けてもらって、身近な方、またはグループ内の方にオンラインサポーターになってもらうというところを狙っているので、自分の身近にいる方が寄り添って丁寧に教えていくことによって、もともとオンラインに拒絶反応を持っている方もいると思うが、そういった方々の考えも少しずつ変わってくると思っている。基本的なところとしては、介護予防のグループ活動の支援ということになっているので、例えばLINEとかZoomの双方向の通信で、1か所に集まらずに自宅にいながら複数のところで町トレができるということを想定している。LINEとかZoomの講習は、1回ではなかなか習得できないと思うので、繰り返すことが大事だということで、我々もオブザーバーの方にいろいろ意見を聞いている。そういった方々の意見を基に、繰り返し分からないところを伝えていくということを考えて相談拠点を置こうと考えている。
●委員 今後、スマホとかデジタルの環境を高齢者の方も整えていくというのが、いろいろな活動をする上でも必要と思うが、なかなかアクセスできないというのと、負担の重さでなかなか購入できないという場合もあると思うが、そういう支援というのは検討されているのか。
●担当者 スマホを購入する補助みたいな意味合いだと思うが、そこは考えていない。今、3大キャリアもあるが、ほかにも格安スマホとかも出ているので、その方のニーズに合わせて、情報の提供はしていきたいと考えている。
●委員 オンラインツールの使用相談拠点の設置ということで、これは高齢者支援センターに設置ということか。
●担当者 市内12の高齢者支援センターのエリアごとに想定はしているが、センターの中に設置できるかどうかは、検討が必要であるので、近隣のほかの施設も含めて考えていきたい。
●委員 支援センターの中につくるとなったときに、今のセンターの方々がどう受け止めるか、業務が増えてしまうことがないのか、日々大変忙しいと聞いているので、センターで働いている職員の話をよく聞いて、負担にならないように進めてもらいたい。
●担当者 高齢者支援センターの職員と共に、生活支援コーディネーターという人材を配置しているが、そういった方々と会議を重ねながら、どういった形なら実現可能なのか、現在、検討を続けているので、尊重しながら進めたい。
●委員 今回、特別会計においては10分の10、都の支出金となっているが、補助金を最大限使っているのか。
●担当者 都の規定としては、1市町村につき上限が1千万円になっているので、積算していけばぎりぎりと考えている。
●委員 総務省のデジタル活用支援員の検討はしたのか。
●担当者 国の事業、デジタル活用支援員というのがあるが、市に対する補助とか、市が直接活用するというような事業とは違って、国が一般の通信事業者とかと連携しながらデジタルの技能を普及させるような、そういった方を育成するという事業だと聞いている。なかなか直接的には活用できないところではあるが、例えば、我々が行う講座の講師とか、相談拠点の相談員とか、そういったところでデジタル活用支援員も活用できるといいと考えているので、検討しながら、できるところは活用していきたい。
●委員 相談拠点について、少しイメージがまだ湧きづらいところがあり、具体的にどういった形なのか。
●担当者 主に想定しているのは年度の後半で半年間、週に1回程度、常駐をして、そこに相談員がいて、講座等を受けてオンラインを活用したグループ活動をしている方々が、分からないこととか、つまずいてしまったことに対して相談対応をするといったところがメインで考えている。また、グループ活動をされている方以外にもそういった相談拠点があるという情報が伝われば日常的に相談に来られると思うので、そういった方も来られた場合は、相談対応をする必要があると考えている。
●委員 デジタル活用支援員という制度を渋谷区が取り入れて、恐らく有償ボランティアみたいな形でやると聞いている。町田市の場合は、協力をしてくれる方に対してどういう形でやってもらうのか。
●担当者 デジタル活用支援員の方、またはそのほかの一般の方も相談員として考えているところだが、デジタル活用支援員にお金がかかるのか、まだ分からないところである。ただ、その方にせよ、一般の方にせよ、ある程度の謝礼はこちらで支払いながら、それが有償ボランティアと言うのか、まだ細かいところは設定していないが、謝礼をしながら、継続的に拠点に来てもらえる方が条件になるので、人選をしていきたいと思っている。
●委員 例えば、場所が必要となった場合の対応も、今後検討の範囲に含まれるのか。あと、一人でも多くの方にこの事業の利益を享受してもらいたいところだが、自主グループに入っていない方の扱いがどのようになるのか。
●担当者 場所というと、個人の方が自宅にいながらできることを想定しているので、自宅でもしできない環境があれば、そのオンラインサポーターの方、代表の方と相談をしながら、あまり密にならない、大人数にならない程度で、友達とか仲間のところに可能な部分で感染対策をした上で集まるといった助言も必要と思う。あとは、仮にグループに入っていない方であっても、個人単位、例えば友達同士とかも含めて、ご希望であれば、対応可能にしていきたい。
●委員 例えば、この事業とは別だが、渋谷区ではスマホの貸出しも行っているということで、今回、都の補助金の中でもスマホの貸出しもできたと思うが、検討したのか。
●担当者 今回、いきいき生活部で行う事業に関しては、基本だが、スマホを持っている方、タブレットを持っている方を対象にしている。スマホを持っていない方がそういった技能を習得したいという場合は生涯学習部の事業を案内するという形ですみ分けをしている。検討はしたが、分かりやすくするために、いきいき生活部では原則スマホ、またはタブレットを持っている方ということで決まった。