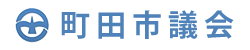
令和3年度(2021年度)町田市一般会計予算
第29号議案
令和3年2月22日
総務常任委員会
■政策経営部
●委員 広報費について、シティプロモーションに関してウェブのサイトが乱立している気がするが、どうか。
●担当者 入り口はなるべく一つに入っていて、そこから必要な情報を取捨選択できていくという流れをつくるということは非常に重要であり、必要であると感じている。今、必ず少なくとも市の公式ホームページにその情報を載せて、そこからリンクで外部サイトに誘導するよう各課にお願いしている。また、ヒットしやすい言葉を入れるなど、検索の機能の精度をさらに、積み重ねの中で改善につなげていきたい。
●委員 広報費について、まちだ○ごと大作戦で、コロナ禍が続くと、延期の想定はしているのか。あくまで今年で終わりということなのか。
●担当者 延期は想定していかなければならない。現に今、実施中の作戦が少なからず影響を受けている。一件一件丁寧に検討を進めて対応を考えていく。
●委員 企画費について、民間活力導入可能性調査、サウンディングをずっとやっているが、今年度、2021年度もやるのか。どの辺まで対象にして考えているか。
●担当者 民間とのコラボレーションをしていきたい思いがあり、今回のサウンディングは、民間ならではの視点やアイデア、意見が、大変有効であったと考えている。今年度、9者の事業者にサウンディングに参加していただいたが、さらにより詳しい情報を聞きたいので、来年度はその9者に追跡調査的にヒアリングをしたい。
●委員 企画費について、公共施設の再編においてきちんとした官民連携を明確に打ち出した部署が必要なのではないか。公共施設の再編を担当されているところではどういうふうに考えているのか。
●担当者 今回、公共施設の再編ということで先行して官民連携の手法をサウンディングで行った。これを一つの事例として、市がプラットフォ―マ―的な役割を果たして民間とコラボレ―ションしていく、新しい手法で考えていきたい。
●委員 秘書事務費について、市長会の会長職というのを活用、利用して、三多摩の実情を伝える取組をしてほしい。発信はどのようにしていくのか。
●担当者 町田市のホームペ―ジ中に市長室というコ―ナ―があり、市長会の活動を紹介する形でアップしている。 より一層取組が市民に届くかは、今後も引き続いて検討していきたい。
■総務部・会計課
●委員 情報システム費について、OCRを導入していくということだが、そもそも入力の段階から手書きではなく、タブレットとかパソコンを使い電子化、デジタル化していく。e-まち実現プロジェクトの実現できるところからだと思うが、ロードマップの中では想定はあるのか。
●担当者 窓口について、明確なロードマップというのはないが、窓口支援システムのようなものを入れて、極力、手書きの申請書等を書いていただかなくても済むような取組を進めていくという方向性は間違いなく強く出している。
●委員 人事管理費について、これまでハラスメントがあった際はどう対応していて、今回体制が整備されてどう変わるのか。あと、有識者はどういう立場の方を想定しているのか。
●担当者 これまでの対応は、ハラスメントを受けた方が各部の総務担当課を窓口に申し出るようになっている。あとはハラスメント防止対策委員会を設置して審議をしている。外部窓口ということで相談のチャンネルを増やす。委員会の体制強化については、有識者は今まで7人のうち6人が庁内の職員だったが、外部の委員、臨床心理士や弁護士、あるいは産業医など4名ほど予定している。あと副市長が委員長になり外部の意見をいただくということで、より体制を強化する。
●委員 総務費委託金について、自衛官の募集事務は予算がついている。紙媒体で名簿を出すのは、新年度もやるのか。
●担当者 2021年度についてはまだ要請が来ていないが、防衛大臣から要請があれば、それに基づいて行う。
●委員 人事管理費について、在宅での勤務で庁内にいない職員について市民には誰が在宅勤務なのかというのが分からない。いない職員のことを今日は休みですというケースがないのか。そういう受け答えについて総務のほうで何かしているか。
●担当者 休みですとは基本的には言わず、テレワークですと話をしている。テレワ―クをする際には、出張の伺いを自宅でテレワークとして出して、どういう仕事をするのか事前に出した上で、実績を全て報告するようになっている。 開始と終わりのときには、必ず職場に連絡をするということはル―ルとしてやっている。随時、職場から職員にチャットで連絡を取り合い、中継をしてお答えする。
●委員 人事管理費について、昨年の決算で「人材育成については、自治体間交流でリ―ダ―シップをとれる職員の育成を目指し、更なる充実を図られたい」ということで意見をつけたが、次年度はどういうことを考えているか。
●担当者 コロナの関係で2020年度は実施できなかった。来年度以降、リモ―トでも対応できるかと思っている。
■財務部
●委員 資産税等賦課管理費について、2021年度においての自治体間ベンチマーキングについて、具体的に教えてほしい。
●担当者 土地評価業務、家屋評価業務の現場調査の方法の見直しを実施する。具体的には、航空写真を併用した土地の現場調査や、家屋評価においては図面等の資料や外観調査による現地調査を推進し、業務の効率化を図る。
●委員 納税管理費について、BPOを導入することにより期待される効果というのはどういったことか。
●担当者 一番特徴的なのが一次的な受電というところである。最初に納税課に入る電話を委託業者が受け、簡易なもの、例えば納付書の再発行や、銀行からの納付の連絡などは、そこで委託業者が完結する。あと、納税相談は、速やかに担当の職員に電話を引き継ぎ、職員が最初の電話を受ける分を丁寧な納税相談に費やせるようになる。
●委員 BPOを開始する市税徴収補助業務は、納税課のどういった仕事になるか。
担当者の説明によれば、BPOで委託する範囲は、定型業務である。収納金の消し込み、納税されたお金の整理、口座振替、督促状や催告書の発送業務、還付等の業務、あと、オペレーターによる電話催告、それからショートメッセージ催告と納税課へ最初に入る電話を受けていただく、こういったものが代表的な業務になる。
●委員 資産税等賦課管理費について、自治体ベンチマーキングを行って改善されて、今回予算に反映されたというところはあるか。
●担当者 2021年度予算の中では、特に成果としての歳出は見込んでいない。ただ、これまで成果の一つとして、土地評価資料の保存方法の見直しを他団体との意見交換会の中で気づき、紙資源の削減と保存場所のスリム化を図ることができた。
■経済観光部
●委員 商工業振興費について、中小企業融資利子補助金の減少理由は何か。
●担当者 昨年5月に増額補正もしたが、その後、国のほうで無利子無担保融資、東京都においても制度融資などが盛り込まれ、今回はそこまでの伸びがなかった。さらには、前倒しの繰上返済等もあり、2021年度はその継続分がやや減ったことと、新年度の増分を見ても今年度の予算よりは下回る。
●委員 今回の予算の中に団体などの補助はついているが、個人、中小企業者への直接補助というのは何か入っているか。
●担当者 特許や知財の関係などの補助は継続してやっている。拡充したものについては、新商品・新サービスの開発支援が直接補助に当たる。
●委員 町の活性化という中で事業者としては期待をしていると思うが、何も支援が当初予算にないのは、いかがか。
●担当者 今回、あくまで当初予算の審議、議論ということで、コロナの緊急事態宣言という状況も込みでの予算ではないということは事実である。ただし、国や東京都で様々な支援、協力金の配付、給付なども行っている中で、今後、市としても資金繰りの支援や、経済活性化については、これまでと同様に国や都の状況を注視し、または一番大事な財源の部分を確保しながら、適宜適切に対応していきたい。
●委員 商工業振興費について、新商品・新サービス開発支援事業は新商品の担当課としての想定としてどのようなものか。
●担当者 2020年度にやった実験で申請があったものでも想定のものは幾つかあった。例を言うと、精密機器から電気的な製品、そのほかにサービス、デリバリーの仕組みをつくるだとか、あとはAIを使ったシステムをつくるなど、そういった多岐にわたるものを想定して、特に何が駄目といったものは考えていない。
●委員 商工業振興費について、新商品・新サービス開発事業補助金を拡充したのは、すごく良いことである。働き方の改革も含めてだと思うが、そういう中でコロナゆえに有効な点があるか。
●担当者 2020年度も、まず事業についてまさにコロナ禍における実験を後押しする補助金を始めたが、今回は前段の開発というところにも大きな経費がかかっていることから、ウィズコロナなどをにらんだ開発をしっかりしていただいて、将来のトライアル認定商品になっていってほしい。
■農業委員会事務局
担当者の説明を了としました。
■選挙管理委員会事務局・監査事務局・議会事務局
●委員 選挙費について、今回、3つの選挙が重なることによって経費削減できるような取組というのはあるのか。
●担当者 新型コロナウイルスの対策費につきましては、都議会議員選挙、また衆議院議員選挙であらかじめ市議・市長選も含めておきたい。あとは備品購入を、新年度は4つの選挙を予定しているので、有効活用するためにも、新たな交付機を先に都議会議員選挙で購入し、後の選挙に有効活用していきたい。
質疑終結後、反対の立場から、
第1に、政策経営部が中心となり進めてきた町田市5ヵ年計画17-21が最終年度となり、それに基づく公共施設再編計画が民間活力導入を是として次々と公共施設マネジメント支援の名の下に集約化や統廃合の方向に進んでいる。20年、30年先の都市像を民間企業のプランニングに丸投げする(仮称)まちだ未来づくりビジョン2040の策定においても、住民福祉の増進という地方自治体が果たすべき視点を欠いていると思い、問題である。第2に、町田市の市内事業者がコロナ禍の影響で営業継続に不安を抱えている中で、当初予算に市独自の支援策が盛り込まれていないことは大問題と考える。業者の困難に寄り添った積極的な支援策が必要と考える。また、第3に、デジタル化を推進し、業務の効率化という名の下に納税課の窓口業務などが外部委託され、
定員管理経営計画の削減などで今、公務労働が民間委託に置き換えられようとしていることは大問題と考える。最後に、自衛官募集事務に関して、当該年齢の若者の個人情報を紙ベースで提出していることは、個人情報保護の観点からやめるべきと考える。以上の理由で第29号議案に反対するとの反対討論がありました。
健康福祉常任委員会
■地域福祉部
担当者の説明をおおむね了としました。
■いきいき生活部
担当者の説明をおおむね了としました。
■保健所
●委員 がん検診の件で、実績に基づいて、検診の予算等も減額されているが、今回新型コロナウイルスで検診を控えざるを得なかった部分も含めて、コロナウイルスが落ち着いた年度に、検診の年齢とかも柔軟に対応して、むしろコロナ禍で検診できなかった人たちもできる、プラスして検診をしてくださいと予算も減るのではなくて、今回受けられなかった人の分を繰り越す、そういう考え方だと思っていたが、そこの考え方を伺いたい。
●担当者 コロナウイルスの関係で、もっと啓発をして受診者をという話だと思うが、いろいろと検討はした。ただ、この予算を要求する際に、その根拠は、非常に難しいものであるので、今回は2019年度の実績をベースにし、なおかつ、当然その検診の状況は逐次確認が取れるので、予算内で厳しい状況下であれば、受ける希望のある方についてきちんと受診ができるように対応していく方法を考えて、予算を計上した。
質疑終結後、反対の立場から、
この予算全般を見ると、事務事業の削減の中で、市民の命や暮らし、営業を守るために、これまで行われてきた町田市の事業が大分削減され、また廃止されたことが問題だと考える。第1に、補助金及び扶助費の見直し方針のうちで障がい者施設借り上げ費補助なども、国の補助金のカットの中で運営が困難になってくる放課後等デイサービスなどの補助金を5%引き下げたことは、大きな問題だと考える。担当部でもかなり努力したとは思うが、こうした方針を進めさせたことは大きな問題がある。また、身体障がい者の訪問入浴補助金が減額されていることについて、障がい者の生活の質を保つ上でも、今後影響がないとは言えない。第2に、生活困窮者の生活を支える上で、市の唯一の貸付制度である生活資金貸付金が費目存置のような予算になったことは、問題だと考える。さらに借りやすい制度に改善することこそ今は必要である。第3に、ひかり療育園について、コロナ禍でなかなか民間委託も事業所等も見つけるのも困難な中、職員の採用なども困難だという説明があったが、そういう中で民間委託ありきの予算になっていることも問題だと考える。通所している障がい者、家族の権利を奪うことにもなり、大きな問題だと考える。第4に、充実が求められるがん検診のメニューから前立腺がんが削られたこと、また、予算的にも減額されたことは、問題だと考える。最後に、繰出金についてである。国民健康保険事業会計への繰出金について、3億5,000万円の法定外繰り出しを減らすために保険税値上げが行われた。市民へのさらなる負担増となる。また、市民病院繰出金が法定で定められた金額よりも少なく、前年度よりは9百万円も減額して決められたことである。病院経営が困難な中、病院を支える市の役割が求められていると考える。以上の点で反対とする。との反対討論がありました。
文教社会常任委員会
■防災安全部
●委員 大雨があった際に、防災無線が全く聞こえないなど、防災無線の内容について、デジタルにあまり明るくない弱者の方にしっかりと内容を伝えられるシステムというのはもう少し充実しないといけないと思うが、来年度に予算化したり、何か取組をしたりしないのか。
●担当者 無線の聞き取りづらい、聞きにくいということについては、よくそのようなご意見はいただいている。実際に、雨音や、または雨で窓を閉めてしまっていると、余計に防災行政無線は聞こえないことがある。それに対して今行っていることとして、電話で、フリーダイヤルで情報を聞けるとか、そうしたことを周知していく。来年度の予算においては、ハザードマップを改定する中で、地図だけではなく、学習面として、情報伝達手段について書いて周知に努めていければと考えている。
●委員 民間交番について、こうした駆け込める環境や機能が広くあれば、安心感、安全、牽制につながる中で、今後、どのように拡大していくのか。ピンポイントでこのままいくのか、または、観光を織り交ぜることで、人も寄りつきやすくなり、複合化で効率的な運営にもつながることから、色々なことが成し得るかもしれないと考えられるがどうか。
●担当者 民間交番については、定着して、市民の方々からも十分認知されているので、市役所として継続していこうということで、市役所が運営実施主体になって運営してきた。もともと防犯の役割を強く打ち出していたものだったが、非常に立地がいいことから、観光拠点という役割も付加して、市役所のほうでリニューアルオープンしたという経緯がある。今後の活用方法については様々な方からご提案をいただいており、一番いい形が何なのかということは、いろんな方と相談してからでないと答えは出ないと考えている。拡大については、そうした経緯があるので他にも増やしていくことは今のところ考えていない。
■市民部
●委員 マイナンバーカードと健康保険証・運転免許証との一体化を今後、国が進めていく予定だが、目標は何年ぐらいなのか。そうした情報が入れば、より早く市民の皆さんがマイナンバーカードに移行すると思うが、どのように考えているか。
●担当者 健康保険証については、いつまでにどのくらいというのはまだ示されていないので、回答はできないが、保険証のマイナンバーカードを読み取る機械の設置等を医療機関にしていただく必要があるので、当面の間は紙の保険証と並行で進めるという形になるのではないかと思う。保険証の利用をPRして、マイナンバーカード取得につなげていくよう、努力していきたい。また、運転免許証については、報道による情報ではあるが、2024年度までに導入すると聞いている。情報が入り次第提供していき、ぜひマイナンバーカードを取っていただくように進めていきたいと考えている。
●委員 今年度はほとんどの町内会や自治会がコロナの影響で活動ができなかったと思う。コロナの様子を見ながらではあるが、来年度以降は、少しずつでも活動を再開していくべきであり、それに対する支援も市役所として行っていくべきであると思う。「市民部予算のポイント」の5にも、町内会・自治会に対する支援を行うとあるが、町内会離れを起こさないために、その辺のアドバイスや支援というのはどういうことを考えているのか。
●担当者 町田市としては、市内全域で組織されている町内会・自治会への支援を引き続き行っていきたいと考えている。例えば、活動に当たっての原資となる資金については、今年度、東京都の新型コロナウイルス感染拡大防止普及啓発事業助成金などが急遽決まり、市からの情報提供に加え、町内会・自治会連合会のホームページでもその情報が掲載されている。今後も市民の皆さんと意識を合わせて、町内会・自治会活動が引き続き活性化するように支援していきたいと考えている。
■文化スポーツ振興部
●委員 成人式について、来年もオンラインでの開催で進めていく中で、コロナがもし収束していれば、集合して開催するということだと思うが、来年、集まってできるとしたら、今年の20歳の人もぜひ集まっていただきたいと思うが、そうした考え方はどうか。
●担当者 今年の1月11日に二十祭まちだに会場で集まるはずであった世代の市民に対しての対応として、コロナが落ち着いた後にということにはなるが、会場開催ができなかったことの代わりに何か企画をということで、実行委員のほうも前向きに考えてくれている。ただ、実際にこうしていくという話に至るには、もう少し議論の積み重ねが必要であり、コロナの収束が見通せない中で、なかなか難しい議論になるかと思う。いずれにしても、実行委員には、アイデアが出てきたら、遠慮せずに市役所の事務局を務めている我々に言ってきてほしいと重ねてお願いをしたところである。
●委員 これまでの国際版画美術館の歴史と芹ヶ谷公園のコンセプトが大きく変わることについて、どう理解を得たのか。版画工房の関係者、国際版画美術館運営協議会の方々、あるいは元設計をされた方、当時の建設に関わった方々にもという話も出ていたと思うが、どういう話をされ、どういう理解を得たのか。
●担当者 その後、版画工房のご利用者の方々とは、代表の方等とお話はさせていただき、コロナが落ち着いたところで、もう一度、集まりませんかという話はさせていただいている。長年使っていただいている方々なので、国際版画美術館については強く思っていただいており、愛していただいているので、すぐに気持ちの整理をするのは難しいかと思うが、市長が版画工房の機能そのものは移転していくと説明していたとおり、版画の制作をするということについては問題がないので、そうした説明を今後もより丁寧にしていきたいと思っている。
●委員 今回の国際版画美術館と国際工芸美術館の一体化工事の概算内訳書を確認すると、合計で約7.6億円となっている。
去年の12月の議会では、一体化工事の費用は大体3.6億円だったと思うが、何が変わったのか。
●担当者 12月議会の行政報告では、一体化工事について、3億6,700万円と報告をしている。これは、東京都市建設行政協議会の単価を基準に、平米あたりの工事費を算出した数字で、建物の予定工事費を算出する際は、この数字を参考にしている。設計事業者から提出された基本設計の成果品に記載の7億6,049万6,000円については、仕様等について、市の一般的な基準に比べ高額なものが用いられており、まだ市で精査をしていない段階の金額である。今後、仕様や施工箇所の精査を行い、3億6,700万円を予定工事として進めていく。
●委員 今回の計画については、今までコロナ禍の影響で、地域住民、利用者との話合いが十分にできていないと思う。これからその辺の話合いをしないと、いろいろ問題があると思うが、どのように考えているか。
●担当者 具体的には、3月20日と3月23日、土曜日と平日の火曜日に地域の方々にご案内をして、報告の場として設けることを考えている。もちろんそれ以外にも、関係団体や、個別に説明をという団体については、機会を設けていく。
■子ども生活部
●委員 このたび大蔵学童保育クラブとどろん子学童保育クラブが改修工事に入るということで、トイレの増設や床の張り替え、児童用ロッカーの修繕がなされるが、子どもたちの居場所というのは、改修時にはどのように確保していくのか。
●担当者 改修工事自体は秋ぐらいから4か月程度を予定しており、その期間、かなり大規模な改修をすることになる。施設自体は利用ができなくなってしまうため、今、大蔵小学校と、その期間の代替の保育場所ということで、基本的には特別教室を放課後の保育のスペースとして活用することを相談している。
●委員 今回、給食センターが旧忠生第六小学校の跡地にできることになったが、給食センターができた際には学童保育クラブとしても、学校教育部と連携を取っていただきたい。町田市では、基本的には保護者がお弁当を作っていくが、ある学童保育クラブでは、他のところからお弁当を頼んでいるところもある中で、給食センターができた際には、お昼の提供もできるような取組も前向きに考えていただきたいと思っている。そうした連携について、どのように考えているか。
●担当者 給食センターについては、教育委員会でこの先進めて、その中でいろいろな活用について議論していくところかと思う。学童保育クラブも含めて研究していきたいと考えている。
●委員 ショートステイとトワイライトステイについて、こうした機能は備えとして安心環境をつくるという要素があるので、通常の施設よりは低い稼働率というのも容認をした運営になるというのが普通だろうと思うが、稼働率の標準的なスコアはどの辺に見ているのか。
●担当者 利用率の基準については、特に定めていない。例えば、ショートステイ・ベビーCoCoの利用率は2019年度が11%で、これは他の施設等の利用率から考えると低く、市民に負担がかからないような形を取らせていただいている。マルガリータの利用率については、平均大体40%台を推移している。町田市としては、こうした利用率に関わらず、社会的に必要な事業という認識の下、来年度については、実態に見合ったというところでこのような形になった。あくまでも市民に負担がかからないような形でやっていきたいと考えている。
●委員 その一方で稼働率というのは、委託料の考え方に大いに関係してくると思うが、委託料と稼働率の関係というのはどのようになっているか。
●担当者 ショートステイは365日24時間体制なので、基本の部分については利用人数等の体制に関係なく、基本の料金としての1定員幾らという考え方でやらせていただいている。
■学校教育部
●委員 給食を子どもに取ってもらいたいという声がある中で、アイデアや知恵を絞って、お弁当の子どもとの時間的格差をなくすべきと考えるが、市はどう考えているのか。
●担当者 配膳に時間がかかるというお話は確かに聞いている。運んでいくところでの時間差については、確かにそうしたご意見をお持ちの生徒もいると思うが、それが全てでもないと考えている。学校に届いた給食を適正な温度の中で食べていただくまでの温度管理、あるいは衛生管理が必要ということを考えると、誰か作業をしてくださる方を単に雇って教室まで運べばいいという話でもないと思っている。正式にそういうことができる人を雇うことについて、業者との調整をしたこともあるが、継続性や、短時間のために人を雇っていくということについては難しさがあるということで、具体的に今取り組めるというようなところまでには至っていないという状況である。
●委員 給食センター方式が決まった中で、次の給食センターができるまで今の併用方式をやっていかなければならない。しっかりと喫食率が上がるように取組をしていただきたいと思うが、どのように考えているか。
●担当者 まず、現行方式の給食については給食センターが稼働するまでは継続していく。給食を利用したいと考えられる方が利用しやすい環境を整えていくというのはこれまでと変わらず、取り組めるところは取り組んでいく。どうしても難しいところ、限界があるところなども、これまでの協議なども踏まえて給食センター方式で全員給食というような形に方向づけをせざるを得なかった部分もあるかと考えているが、いずれにしても取組については進めていきたいと考えている。
■生涯学習部
●委員 今回もうすぐ改修が終わり開放される町田第一中学校について、その開放の中には図書館が含まれるが、図書館の運用はどのようになるのか。
●担当者 学校の図書室の地域への開放の詳細な運用の形については、まだ決定はしていない。学校開放制度について検討を行う会議体として、学校開放制度検討委員会というものがあり、最終的には、そこに諮るような形で詳細な事業の内容について決定していく。図書室についても、他の部屋と同様に、学習の場という形を優先に市として考えており、学習スペースとしての開放を考えている。
●委員 図書館の考え方というのは過渡期にあると思う。そういった意味では、これから公共施設の統廃合や再編だけを進めるだけではなく、今ある能力や機能をもう少し活用勝手のいいようにしていくことも並行して必要であると思っている。こうした考え方は、他の小学校、中学校の学校図書館にも進めていけるものなのか、またはそうした考えがあるのか。
●担当者 今回、町田第一中学校の建て替えということで、設計の段階から地域への開放に当たって動線の分離等を考えて設計した上で、開放の準備を進めている。既存の学校において学校図書館の開放を進めていくというのは、そうした面での難しい点もあるため、今後、設計段階から動線の整備や環境の整備を進めることができれば、開放というものも少しずつ進んでいくのではないかと考えている。
質疑終結後、反対の立場から、
本予算には、中学校全員給食実施に向けた予算や小中学校体育館エアコン整備、また学童保育クラブの高学年受入れに関する予算など、子どもたちの要求に応えた予算には大いに評価をする。一方で、以下の問題点を指摘する。第1に、(仮称)国際工芸美術館整備費についてである。建設費が当初の30億円から40億円に増大したこと、芹ヶ谷公園内の樹木が伐採され、国際版画美術館から歴史ある版画工房と市民に親しまれてきた喫茶けやきを外に出すなど、これまでの芹ヶ谷公園と国際版画美術館の位置づけを住民や関係者、専門家の理解と合意を得ずに推進していることは問題である。計画は抜本的に見直すべきである。第2に、図書館のアクションプランに基づく鶴川図書館、さるびあ図書館の集約、鶴川駅前図書館の指定管理者導入は行うべきではなく、市立図書館8館を直営で維持すべきであると考える。第3に、小学校給食と学校用務員の民間委託はやめるべきである。第4に、学校統廃合については、今年度の審議会の答申を受けて教育委員会が方針を決めるとのことであるが、少人数学級の流れを見通し、学校統廃合はやめるべきで、少人数学級を推進すべきと考える。最後に、デジタル化の推進の中で市民センターの人員削減の方向ではなく、対面での市民サービスを重視すべきである。以上の理由で第29号議案に反対する。との反対討論がありました。
次に、賛成の立場から、
今回の一般会計予算については、新型コロナウイルス感染症対策関連事業や防災対策費用、小中学校の空調設備設置事業や教育の情報化事業など、緊急性が高い事業や多くの将来に向けた投資予算が盛り込まれており、評価するところである。しかし、(仮称)国際工芸美術館整備事業について、以下の指摘をせざるを得ない。まず1点目に、この新型コロナウイルス感染症の影響下で50億円以上の税収が減少し、今後数年は経済的な影響が予想されている状況にもかかわらず、適正とは言えない大規模な財政投資を行う点である。今回委員会審議で明らかになったとおり、町田市立国際版画美術館と(仮称)国際工芸美術館一体化工事で当初3.6億円との報告であった。しかし、実際には設計事業者から基本設計において積算された金額は7.6億円という当初の予算規模の倍以上かかることが判明した。担当部は、積算単価は東京都の積算より高騰しているとのことだが、価格の高騰だけで倍額になることは考えづらく、もともと報告された予算総額が妥当でなかったことは明らかであると考えざるを得ない。このような状況にもかかわらず、緊急性の乏しい(仮称)国際工芸美術館整備関連事業は40億円以上という大規模な税金をつぎ込むことになる。また、国や東京都からの助成は現段階ではほぼ見込めず、この財政投資が適正かどうか大いに疑義を持たざるを得ない。また、建設予定場所にいたっては、当初設計事業者から3つの建設候補地が提案されていたにもかかわらず、各案の予算規模や地域住民からの要望である利便性の高い快適な生活道路の確保の観点などが比較にほとんどされておらず、本当にこの建設予定地が、予算規模が適正かどうか判断できず、予算規模の縮小を本気で目指しているものとは到底思えない。2点目に、地域住民からの理解が全く得られていない点である。先日、芹ヶ谷公園近隣の町内会・自治会を中心に多くの関係諸団体が代表者の連名で、町田市に芹ヶ谷公園パークミュージアムに対する要望書が提出されている。その内容は、基本設計を見直してほしい旨の記載がほとんどであり、改めて地域住民、関係諸団体への理解が全く得られていないことが明らかになった。しかし、町田市は今回の答弁のとおり、あくまで基本設計に基づいて進める、要望書の内容については対応できないとのことであった。近隣住民や関係諸団体の理解がほぼ得られていない状況にもかかわらず、このまま基本設計から実施設計を進めることは、行政の横暴と言わざるを得ない行為であり、明らかな住民無視である。このような市民協働とかけ離れた行為は、町田市の行政経営改革プランの基本方針にも反しており、許されることではない。以上2点の観点から、新型コロナウイルス感染症の影響により財政状況を鑑み、建設スケジュール計画の変更、あくまで基本設計どおりに進める前提ではなく、一から地域住民や関係諸団体と建設計画に対する協議を行うこと、そして建設費用のさらなる削減や地域住民の生活道路の利便性を考慮した建設予定地の変更を条件に賛成討論とするとの賛成討論がありました。
建設常任委員会
■環境資源部
●委員 循環型施設整備費において、資源化ごみ施設について、2021年度の相原地区、上小山田地区の整備はどういったスケジュールを考えているのか。
●担当者 相原地区の2021年度の状況だが、ただいま地権者との交渉を行っている。この施設整備については、大戸広場と併せて整備をするところが地元の方々との約束になっているため、その対象区域の地権者の方々と交渉を行っている。2021年度中に都市計画決定まで運べればと考えている。
●委員 環境・自然共生費において、水素ステーションについては、1か所誘致しますというのは、水素ステーション事業者及び土地所有者の方たちへのアクションというのは、今どうなっているか。
●担当者 2021年度までに誘致すべく、地権者への訪問、あるいはステーション事業者への交渉を行っている。現在接触ができない状況なので、緊急事態宣言が解除されたら、直ちにまた再開をしたいと考えており、地権者への交渉、事業者への調整というような活動を取っている。
■道路部
●委員 道路維持費において、道路等修繕料については、同年度に処理できないものが、70件ほど発生しているとのことだが、こういった不足についてどのように補っていくのか、来年繰り越して先延べしていくのかどうか、これは解決していかなくてはいけないと思うが、どのように考えているか。
●担当者 1件ごとの数字についても、なるべく予算を無駄なく使うようにして、積み残しがないようにしていくように努力していきたいと考えている。
●委員 道路整備費について、予算が減額されているということだが、道路整備課においても20億円あったものが10億円になったその経緯を教えてもらいたい。
●担当者 10億円の主な減額についてだが、特に大きなものとしては用地の購入費及び物件の補償費が大変大きく減っている。継続的な地元の皆様との話合いの中で、来年度、用地購入の見込みが立っている路線が少ないこととか、歩道整備工事のように用地取得が2020年度でおおむね完了した路線ができたというところもあり、そうしたところが大きく、特に用地費が減少した。工事関連としては、優先順位の中で事業の見直しや延期を行い減額した。
●委員 街路整備費において、鶴川駅北口交通広場について無電柱化というのは、町田835号線、町田623号線を終えた後、または、ある程度途中から導入し始めるエリアとして考えているところなのか、または、次のさらなる無電柱化を図る場所をもう決めているのか。
●担当者 2020年3月に町田市無電柱化推進計画が策定されている。鶴川については、都市計画道路ということで道路の整備と併せて、無電柱化をしていくという形になっている。また、既存道路については、原町田中央通り、それから、消防署前の町田623号線をやっていくという形だが、また文学館通りも既存道路として記載されているので、引き続き検討していく。
■都市づくり部
●委員 土木費が36.9%前年対比減額になって、減額の90%が都市づくり部の予算だと見られる。都市づくり部は総額で56億5,000万円減っているが、どういう状況の中でこのような大きな金額になったのか。
●担当者 減額の一番大きなものは、陸上競技場の増設工事が40数億円減っているかと思う。その他、事業清算という形で満遍なく減額をしている。
●委員 多摩都市モノレール基金積立金は今年はどうなっているか。
●担当者 2021年度については、積立てを見送るような形になっている。
●委員 交通事業推進費について、今年度もホームドアの整備がされたかと思う。来年度も引き続き実施していくということだが、来年度は場所的には、約10万人以上と書いてあるが、どこの駅をにらんでいるのか。
●担当者 2021年度については、JR町田駅のホームドアの分が主な内容になっている。
●委員 都市計画管理費において、モノレールの整備について、市民生活とか、環境に与える影響、また、町田駅周辺だけではなくて新たなほかの駅を設置するに当たっての環境への負荷とか、財政への負担というところについては、どのように認識しているのか。
●担当者 周辺への環境については十分配慮すべき事業だということは理解している。また、事業については、ルートが決まって設計に入る段階で周辺環境への影響を調査することになるので、その辺については具体的に決まり次第説明させていただきたいと思う。
●委員 公園緑地費において、野津田公園の多目的グラウンドの整備工事について、3月の補正予算で債務負担行為が廃止されて、今回、多目的グラウンドの整備工事費が債務負担行為で廃止になった部分の一部が新たに計上されたという理解でよいのか。
●担当者 債務負担行為は1度廃止をして、この多目的グラウンド整備工事が単年度で終わる工事になったので、今年度新たに計上しているということである。
■下水道部
担当者の説明をおおむね了としました。
質疑終結後、反対の立場から、
新規に始まる居住支援協議会相談窓口は大変重要な事業だと認識しているし、必要な道路整備や補修、衛生事業、下水道事業、耐震化の促進予算など、市民生活に欠かせない事業がほとんどだということについては、事業を推進していただきたいと考えている。また、コロナ禍での財政状況により、事業の厳選について工夫しているとも認識をしている。一方、野津田公園の多目的グラウンド整備については、ばら広場の跡地にテニスコートを前提に残土が移されることが計画されている点だとか、また、まちづくりについては、基幹交通としてモノレールありきで全てのまちづくりが検討されていること、新たな駅の開発も含めて検討されていること、他の交通システムの検討がないことなどについて、問題があると考えている。以上の理由から、第29号議案に反対するとの反対討論がありました。
次に、反対の立場から、
質疑の中で、モノレール促進事業に関して基金の積立てが今年度は見送りという方針が立てられた。非常に残念なことである。モノレール推進は全市民的に要求されている。モノレールの基金に関しては、全会派一致して当時進められて、全員が賛成しているものだと思っていたが、そうした方針が今回見送りということになると、市の交通政策を非常に疑うものである。 そういうことで、ほかの交通施策も残念ながら先進的なものが見られないので、今回の第二十九号議案に反対するとの反対討論がありました。
町田市基本構想・基本計画調査特別委員会
担当者の説明を了としました。