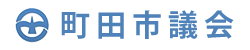
平成26年度(2014年度)町田市一般会計補正予算(第1号)
第50号議案
平成26年6月3日
総務常任委員会
■政策経営部
● 委員 私立学校誘致検討事業について木曽山崎団地地区のまちづくり構想で位置づけられた文化、教育の関連拠点として私立学校の誘致を選択した理由はなにか。
● 担当者 一つは、この大きな土地をどうやったら使い切れるのか、民間事業者が参入したときにどういった事業が考えられるのか、駅からバスで二〇分ぐらいの立地にあってどういうところが参入できるのかを総合的に勘案した中で、最終的に私立学校の誘致が一番好ましいのではないかという結論に至った。
● 委員 団地再生という検討の中での学校跡地ということだが、公有地の有効活用に聞こえてくる。地域の活性化のために必要な活用ということを検討する場合、地域にとって何が求められるかという議論や要請がまずあるのではないか。
● 担当者 まちづくり構想を策定するに当たり、木曽山崎団地地区の連絡協議会とまちづくり検討会で二年にわたって検討を続けてきた。その中で、この話はいろいろ出ている。まちづくり構想という中では、私立学校の誘致まではうたっていないけれども、その後に行政として、この連絡協議会とまちづくり検討会で議論した内容を踏まえながら私立学校の誘致を決定した。
● 委員 『まちだ自慢』推進事業について、町田市の魅力を単純化すれば、内外に非常にわかりやすいが、単純なものを見つけ出すということは、非常に難しい。複数の魅力を見つけ出し、アピールする場合は表現の仕方が難しい。
● 担当者 町田のイメージを市民にお聞きすると、やはり総合力がある町という意見をよく耳にする。今回、町田らしさというものを、総合力がある町、多彩な魅力がある町と位置づけ、その多彩な魅力を市民とともに情報発信していくことによって、そこからブランドが生まれるということを狙ってシティプロモーションを展開するということで、『まちだ自慢』推進計画を策定した。
● 委員 まちだ自慢推進事業は何を持って成功とするのか。
● 担当者 町田市民であることを誇りに思い、町田に住み続けたいという意欲を醸成していくことが目標になる。 市外の方に対して、憧れを生み、町田に住んでみたいという意欲を高めるには、活動の積み重ねが必要になってくると考える。短期目標としては、市民発の情報発信強化。市外の方に対しては、町田への来訪促進ということを目標に掲げている。短期目標の目標値に関しては、今年度、調査を行って、進捗状況を検討していきたい。年度ごとのターゲット、テーマ、目標値については、今年度、シティプロモーション推進に関する委員会の中で検討して、市民の方に明らかにしていきたい。
● 委員 何をもってこの事業の成果物としていくのか。
● 担当者 『まちだ自慢』推進計画は、市民が主役になり、シティプロモーションを推進していく体制をつくるということに軸足を置いている。「まちだ自慢サポーター」が数多く情報発信している状況というものが成果物になっていくと考える。
● 委員 まちだ自慢をどれだけ集めるのか、対外的にどれだけ発信したかを捉えられる準備はできているか。
● 担当者 その成果物をはかる方法として、インターネット調査を二年に一度やっており、その中で数値をはかっていきたい。また、「まちだ自慢サポーター」の数、「まちだ自慢サポーター」が町田の自慢を発信した数というものを数値としてはかっていきたい。
● 委員 オリンピックキャンプ地等 招致事業についてオリンピック、パラリンピックのキャンプ地に名乗りを上げている自治体はどのくらいか。
● 担当者 五月の段階での調査だが、二十六市の中で本部会議を立ち上げているのは町田市だけである。また、四市が本部会議を立ち上げる準備を検討している。
● 委員 市内の宿泊施設について。
● 担当者 担当者の説明によれば、オリンピック、パラリンピックを招致するには、アクセス、宿泊、施設の課題をすべてクリアしなければならない。施設については陸上競技場や総合体育館があり可能性があると考えているが、アクセスと一番課題となる宿泊については今研究している。
■財務部
担当者の説明をおおむね了としました。
■経済観光部
担当者の説明をおおむね了としました。
健康福祉常任委員会
■地域福祉部
● 委員 成年後見制度推進費について、後見人になった場合、行政としての支援はあるのか。
● 担当者 現在、市民後見人としてお願いするのは、東京都の基礎講習を受けた方である。社会福祉協議会を後見監督としてつけるので、市民後見人の後ろには社会福祉協議会が絶えずいて、市民を支える構造になっている。
● 委員 成年後見制度推進費について、シンポジウムを開催する費用ということだが、どのような方を対象とするのか。
● 担当者 市民を中心に、広くこの制度に関心のある方(かた)を対象としている。
● 委員 今回のシンポジウムだが、回数、開催時期、会場について、現時点での想定を教えていただきたい。
● 担当者 開催回数は一回、日にちは十月二十五日 土曜日の午後、場所はホテルザ・エルシィを予定している。
● 委員 参加人数の計画をお聞かせいただきたい。
● 担当者 四百人を想定している。
● 委員 事業費の半分が会場費だが、どうしてもホテルザ・エルシィでないといけないのか。
● 担当者 今回の企画については、早くから成年後見制度に取り組んで先駆的だと言われていることを、全国に発信していきたいという意志が強くある。市内で一番発信力を持つ場所としてはホテルザ・エルシィではないかという判断で選ばせていただいた。
● 委員 費用対効果を考えれば、会場費を抑えることによって、例えば広報に力を入れるとか、もっと発信できる予算もできてくるのではないか。
● 担当者 費用対効果等を考え、今後、会場の設定に関しては慎重に行っていきたいと思う。
● 委員 就労自立給付金の内容について。
● 担当者 就労収入を得るようになると生活保護脱却という形になるが、脱却直後の不安定な生活を支え、再度保護に陥ることを防止する制度である。
● 委員
● 担当者
■いきいき健康部
担当者の説明を了としました。
文教社会常任委員会
■市民部
● 委員 消火栓移設負担金について、これは何カ所分の負担金なのか。
● 担当者 百三十一カ所である。
● 委員 消火栓の移設は今回の百三十一カ所で完了するのか。
● 担当者 現在、東京都水道局で水道管の耐震化を毎年進めているところであり、今後も出てくることが想定される。
● 委員 災害対策費について、帰宅困難者対策の備蓄倉庫はどの辺に設置するのか。また、帰宅困難者の受け入れ場所はどこを想定しているのか。
● 担当者 防災備蓄倉庫は町田駅周辺の帰宅困難者用の備蓄品をおさめる場所として、ちょうど線路と反対側あたりに設置を予定している。帰宅困難者を受け入れる施設としては、市民ホール、生涯学習センター、市民フォーラム、文化交流センターである。
● 委員 災害対策費について、帰宅困難者対策の件については、そういう計画をつくるに当たって学校や企業とどのような形でやっているのか。
● 担当者 企業については、三十万以上の乗降客がある駅については、協議会を設置して企業と行政と駅で一緒に協議会をやっていくということになっている。私立の学校については、都条例で、そこの学校で帰宅困難者の抑制や帰宅困難者用の備蓄を進めることになっているので、その範囲で適切にやっているものと考えているが、正確な情報は持っていない。
■文化スポーツ振興部
● 委員 市民ホール費の音場(おんじょう)支援システムについて、音が生の音ではなくてデジタルの音になると、わざわざホールに行って聞くという良さがなくなってくるのではないかと思うが、その辺はどうなっているのか。
● 担当者 建築基準法の改正があり、大空間の天井の落下に対して耐震化を図らなければならないといったところがあり、さまざまな方法論を検討してきたが、やはり現状のホールの天井形状を変えざるを得ないという結論に達した。そういったところから音響に影響が出るだろうということがわかり、それを補正するためにということと、市民ホールでは色々な演目が開催されているので、そういったものに対応するために音場補正装置の導入を考えた。
● 委員 文化芸術ホール整備費について、座談会のメンバーに市長、副市長が含まれているのは適当ではないと思うが、この座談会の性質はどういうものなのか。
● 担当者 この座談会において何らかの考え方をまとめて答申や報告という形では考えていない。今後、基本構想を本格的に議論していく上での素材や基本構想のアウトラインみたいなものをご教授いただきたいと考えている。そういう意味であえて理事者も加わる形で幅広い議論をしていきたいと考えている。
● 委員 そういう性質の座談会で、予算規模としては余り適当ではないように思われるが、どうか。
● 担当者 内容としては、座談会の運営に関する経費、それから、調査に係るコンサルテーションというものも含めて計上している予算額である。
● 委員 文化芸術ホール整備費について、この文化芸術ホールというのはこれまでの構想と変わっているのか。
● 担当者 音楽コンサートや演劇などが中心になると思うが、多目的な利用を想定したホールという意味では、これまでの考え方と変更したところはない。
● 委員 市民ホール費について、公共工事設計労務単価の引き上げとあるが、この労務単価は大体どのぐらいなのか。
● 担当者 計上している予算額のうち、労務単価の上昇分にかかわる経費が三千二百万円強である。工種によって切り分けているが、5%から10%程度の上昇分を見込んで積算している。
■子ども生活部
● 委員 冒険遊び場事業補助金について、補助対象活動に常時プレーリーダー二名以上の配置とあるが、その辺については今後見直していく可能性があるのか。
● 担当者 必要があればということでは、もちろん見直しをすること、あるいは再検討することももしかしたら出てくるかと思う。
● 委員 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助について、実際に保育士に渡っているかどうかについて確認ができるようになっているのか。
● 担当者 各保育園で処遇改善の計画を立てて、それを職員に周知し、支払っていただくという形をとっている。また、支払ったものについては実績報告を受けるという形になっている。
● 委員 保育所用地整備事業費について、旧本町田西小学校のプール解体工事はいつになるのか。
● 担当者 現在、工事にかかる進入路等の調整などもしているところだが、今年度中に着手をして、なるべく早い時期に解体していきたい。
● 委員 民間保育所整備事業費補助金について、認証保育所の認可保育所への移行に伴い、現在いる子どもたちはどうなるのか。
● 担当者 国のほうの説明を聞いた限りにおいては、期間は限定されるが、以前、施設のほうで保育が必要だという認定をしているのであればというところの話で、いきなり行くところがなくならないように配慮しなさいという話があったので、そういう形で配慮していきたい。
● 委員 子どもクラブの整備計画について。
● 担当者 まずは子どもがふえている地域、現に多い地域ということ、それから、現在ある子どもセンター、子どもクラブから距離が離れているところという二つの観点から七つの校区を選んだ。
● 委員 子どもクラブの施設の機能について。
● 担当者 現在、既に運営している玉川学園ころころ児童館、南大谷子どもクラブと同じような活動内容を今のところは想定している。
● 委員 学童保育クラブ整備費について、今後、国からの指針で四年生以上をふやしていかなければならない状況で、人や場所の確保の見通しはどうか。
● 担当者 一年生から三年生の児童を受け入れることで手いっぱいの状況なので、四年生以上に一度に広げていくというのは大変難しい状況にあると言わざるを得ない。
● 委員 子どもセンター整備費の(仮称)小山地区子どもクラブ整備事業について、三月十九日の文教社会常任委員会の時点では民間マンションの一部を借り上げる方向で協議中ということだったが、マンションの最初の販売時期が三月の下旬である。このマンションの販売の際に、この子どもクラブが附帯施設として事業者のほうから買い主のほうに説明があったと聞いているが、その点について確認したい。
● 担当者 協議の段階でそういうことを説明しなければならないというような話があったとは聞いている。
● 委員 市のほうは知っていてそれを看過するということは、やはり大変なことになるのかと思うが、その点についてはどうか。
● 担当者 決まっているということで載せるという話ではなく、あくまでも予定だということでという話だと記憶している。
● 委員 市として、この子どもクラブをここの場所でいくと決定したのはいつの時点なのか。また、それを事業者のほうに伝えたのはいつだったのか。
● 担当者 最終的に決定したのはことしの四月の半ばである。これは市としての意思決定ということである。事業者と正式に意思決定ということになると、それは契約を締結してからということになると思うので、現在のところはまだ契約は何ら締結していない。
● 委員 立地や規模について、地域の意見を聞くことなく進めるというのはなぜなのかと思うが、それについてはどうか。
● 担当者 説明の時期が大変遅くなったことについては大変申しわけなく思っている。マンションの中に公共施設を入れるということについて、その準備がかなり長引いて、なかなか説明に伺うことができなかった。
■学校教育部
● 委員 小学校給食調理業務委託事業について、具体的には何校で始まって、それぞれでどのような準備をするのか。
● 担当者 2015年の四月から、六校の小学校で委託を予定している。事前準備としては、保護者への説明、給食調理室内の備品などの確認や引き継ぎなどの準備も必要になってくるかと思う。
● 委員 今後もこの民間委託は進めていって、全部委託になってしまうのか。
● 担当者 正規調理員の退職の動向に合わせて今後も委託を進めていくという方向性である。全校を委託するのかということに関しては、一部直営校を残すという考えでいる。
● 委員 一部直営を残すということだが、どのぐらい残す考えなのか。
● 担当者 今現在考えているところでは、六校程度は直営校を残し、あとは調理業務委託を進めていくという方向性である。
● 委員 小学校給食調理業務委託事業について、センター的な学校にいる職員がほかの学校に手伝いに行ったりするというのは同じくやっていくという理解でよいのか。
● 担当者 職員がグループ内のほかの学校に行くことは、それは巡回というような形でやっているが、それに関しても、より良い給食を提供するために行っていると考えている。
質疑終結後、反対の立場から、第一に、コンベンションホールから文化芸術ホールへ名前は変わったが、本質は中心市街地の新たなにぎわいを創出するためにゼロからのスタートと市長も言っているように、大規模ホール構想を策定するための座談会を開く予算がある点である。場所も総事業費も座席数も機能もこれから決めていくという、ホールをつくること先にありきで市民の理解を得られてもいない。町田市内は、町田市民ホールやポプリホール鶴川など身近で安い料金で市民が豊かな芸術に触れる機会があり、近隣自治体にも二千人規模のホールがたくさんある。急いで町田が大規模ホールをつくる必要性は見出せない。 第二に、債務負担行為補正の中に来年からの小学校の給食調理業務委託が入っている。正規職員が足りないからというが、市のこれまでずっと退職者不補充を進めてきたことが原因である。給食を民間委託することは、人件費のコスト削減を民間に委ねることであり、給食が子どもたちの体や心をつくる食育の一環という位置づけが弱められる。 よって、この二つの理由から第五十号議案に反対するとの反対討論がありました。
建設常任委員会
■環境資源部
● 委員 し尿処理場 管理費ついて、境川クリーンセンターのし尿処理場を解体するということだが、今後の活用の仕方はどうなるのか。
● 担当者 解体した後の用地としては、地元の要望を踏まえた施設、現在あるし尿投入施設、調節池の三点を計画している。
● 委員 資源化施設整備費について、熱回収施設等建設事業者選定事業の等とは何か。
● 担当者 一点目が焼却、二点目がバイオ化施設、三点目が不燃・粗大ごみ処理施設であり、これらをあわせて熱回収施設等という形で表現している。
■建設部
● 委員 相原駅 西口広場 築造事業費について、今回の工事のレベルで最低限、今のバスの折り返し所は使わなくて済むようになるのか。
● 担当者 この事業が終われば、バスについても全て駅前広場に乗り入れられるため、今使っているバスの折り返し所は使わなくなる。
● 委員 都計道3・4・22(小野路)築造事業費について、都市計画変更の手順について教えていただきたい。
● 担当者 まず 今年度おこなう 自然環境調査や、線形についても もう一度確認する必要がある。その後、警視庁との協議を経て、線形がまとまった時点で東京都と調整をおこない、都市計画変更の手続きに入っていく。
● 委員 道路維持費のペデストリアンデッキ調査・設計委託料について、今回の改善事業によって具体的にどういうところを手直しするのか。
● 担当者 今回、町田バスセンター周辺デッキにおける詳細設計を進めており、具体的にはペデストリアンデッキ下の照明、そして歩道舗装、また柱の改善を考えている。
■都市づくり部
● 委員 都市公園費について、今回の改修に当たって、薬師池公園の階段、園路整備はどの程度 解消されるのか。
● 担当者 今回、バリアフリーという観点で、薬師池の西園路の階段を整備する。今後、全体的に薬師池公園の整備をしていく中で、バリアフリールートを設けていきたい。
● 委員 都市公園費の三輪緑地の用地買収について、町田市としては、この土地について横浜市と調整を図りながら、緑を残すような整備を考えているのか。
● 担当者 特に横浜市との調整はしていないが今後も開発せず、あの風景をそのまま残していきたいと考えている。
● 委員 都市計画事務費の南町田駅北口広場の整備について、今回、町づくりの点では、公園を南町田と一体として考えていくということだと思うが、具体的に官民連携とはどういったことなのか。
● 担当者 官民連携については、民間の創意工夫によるこれまでにない新たな魅力を備えた空間整備、その魅力ある空間に多様なアイデアを盛り込んだ運営によって、高質で、きめの細かいサービスの提供ができるような手法について検討する。具体的には、指定管理等も含め、PFIの導入や、いろいろな形での手法を検討して、鶴間公園の整備と南地域にある公園の包括的な管理運営等の手法について検討していく。
● 委員 市計画事務費について、具体的に小山田周辺まちづくり検討の対象区域というのはどの辺までを対象としているのか。
● 担当者 小山田周辺まちづくりの具体的な範囲については、新駅の構想や 農免道路の整備等も視野に入れて、まちづくりを検討していきたい。
● 委員 都市計画公園整備費の三輪緑地用地購入について、今回で何パーセントぐらいの取得率になるのか。
● 担当者 二〇一四年度末で二十九,八パーセントになる予定である。
■下水道部
担当者の説明をおおむね了としました。
質疑終結後、賛成の立場から、今回の補正予算に関しては、計上されている資源化施設整備費等については、建設事業者の選定に係る事務資料作成のための費用、事業者選定 審査委員会の運営に係る費用となっている。熱回収施設については、現在の施設の老朽化や排ガスの排出基準が下がることで健康への影響や環境に与えるリスクも弱まることを考え、進めるべき事業と考えるが、併設のバイオガス化施設については、災害時の対応や現在考え得る生ごみの活用法の一つとして一定の理解はするものの、長期にかかるコストは未知数であり、まだ検討の余地があると考えている。このことを踏まえ、今後も資源化と環境負荷とコストとの兼ね合いについて、さらに研究協議を続けていただきたいという要望を添えて賛成討論とするとの賛成討論がありました。