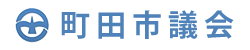
令和5年度(2023年度)町田市一般会計予算
第7号議案
令和5年2月21日
【総務常任委員会】
■政策経営部
●委員 情報システム費について、国の指針として、機密性を有する情報や個人情報を取り扱わない場合は各行政主体におけるLINEサービスの利用は許容されると認識している。その中で、「国が定めた標準仕様に準拠した国民健康保険システムの利用を開始します」とある。国民健康保険は個人情報ばかりだと思うが、LINEの中でどこまで取扱うのか。
●担当者 今のところ、国民健康保険事業をLINEで申請をするという検討はしていない。基本的には、標準化に関してはマイナポータルを活用した申請が標準化の中で検討されている。
●委員 広聴費について、庁舎内の総合案内業務の確認だが、コンシェルジュがいるエリアと、玄関口の受付窓口の組合せは広聴費で行われているのか。
●担当者 総合案内業務については、コンシェルジュのブースと正面玄関、あと南口の駐車券の無料化の作業、その3つが一体となったものである。
●委員 広報費について、メディアプロモートの委託先等の内容について。
●担当者 メディアプロモートに関しては、町田市の情報をメディア、テレビ、それからプリント媒体やウェブ媒体、広く情報発信できるような露出を獲得するための委託になっており、来年度は競争入札でこれから業者を決定していく。
■総務部・会計課
●委員 人事管理費について、多様な人材を確保するための職員採用試験について、昨年7月に総務省が「就職氷河期世代支援の『第二ステージ』に向けた地方公共団体での中途採用の取組の一層の推進について」という通知を出しているが、次年度の就職氷河期に対する中途採用の取組の状況、予定などはどうか。
●担当者 就職氷河期世代の採用については、2022年度から行っている。今、就職氷河期世代の支援プログラムの集中強化期間であり、2023年度まで国のほうで進めているため、引き続き来年度も、就職氷河期の方たちについては採用試験を行ってまいりたいと思っている。
●委員 会計年度任用職員人件費について、職員数はどのような状態になっているか。
●担当者 一般会計は1803人、国民健康保険事業会計は36人、介護保険事業会計は55人、後期高齢者医療事業会計は14人ということで、合計で1908人となっている。
●委員 総務管理費の郵便料について、3か年で比較すると今回2億円を超えている。郵送料削減の取組を伺っているが、それを反映しても増えているのか。
●担当者 来年度は、新規で学校教材費の学校徴収金の公会計化が始まる。保護者の方に市から通知を出す作業が入るため、これで大体1000万円新規で見込んでいる。このような新規事業があると、削減をしても追いつかない。
■財務部
●委員 公共施設等維持保全事業について、この基準は、財務部がやる基準と担当がやる基準はどういうことなのか。
●担当者 基準だが、中期修繕計画を営繕課で策定しており、施設所管課で修繕計画を作成し、それに基づいて修繕をしている施設、学校、病院、工場、市営住宅以外で、延べ床面積で500平米以上の規模の大きい施設を対象とした修繕計画を営繕課で立てている。財務部の中期修繕計画以外は、例えば学校であれば町田市立学校個別施設計画など、それぞれ個別施設計画を定めたものがある。
●委員 財産管理費について、再生可能エネルギーを市庁舎に導入するのは良いが、市のほかの施設に関して検討されているのか。
●担当者 環境資源部で再生可能エネルギーの導入の計画を立てており、それに基づいて、市庁舎で先行的にやる。
●委員 市税収入の伸びについて、700億円を超えたのは初めてかと思うが、具体的に、市民税納税者が増えたのか。あと、法人についても同様にどういう形で増えたのか。
●担当者 個人市民税については、2022年度の課税実績だが、給与所得による納税義務者数が16万5612人と、前年よりも2361人増えており、納税義務者が増えていることで、歳入見込みが増加している。あわせて、収入額というのも平均給与で約5万7000円増加しており、こちらも個人市民税の増加要因となっている。法人市民税についても、一部、金融業や保険業、こちらが2021年度決算は増益となっているので、増額している。
■防災安全部
●委員 安全対策費について、民間交番の閉所が迫っているが、今まで民間交番が担ってきた道案内業務や、防犯拠点としての機能は、どうなるのか。代替できる予定はあるのか。
●担当者 道案内の機能については、今度整備される新たな交流拠点に引き継ぐ予定である。また、官民協働パトロールなどの防犯拠点としての機能については、ぽっぽ町田にその機能を移転する方向で、町田まちづくり公社と協議を進めている。
●委員 安全対策費について、運転に不安を覚える方がいるが、町田市内は車がないと生活ができない不便なエリアもあり、誰かに相談したいという方がいたときに、自分の運転を見詰め直したい市民に対しての対処の仕方があるのか。
●担当者 運転に不安を感じた方の相談先として、警視庁の安全運転相談ダイヤルをご案内している。全国統一で♯8080になるが、こちらを活用いただくようにご案内している。また、自分の運転を見詰め直したいといった方には、加齢に伴う判断能力や身体能力の衰えに気づいていただくための施策として、65歳以上の方を対象とした安全運転実技教室を実施していく。
●委員 消防施設費について、消火栓設置負担金で約2億円の金額を計上されているが、これは東京都の補助等を受けられるのか。
●担当者 消火施設整備事業で2億500万円の起債で計上しており、東京都の補助はない。
■経済観光部
●委員 観光振興費について、町田薬師池公園四季彩の杜魅力向上推進事業で、計画策定委託料が計上されているが、この基本計画を策定する課はどこか。
●担当者 この基本計画の策定については観光まちづくり課が事務局となり、策定を進めていく。
●委員 里山環境整備事業について、農地等整備で、小野路町ほか2か所整備されるということだが、整備地のおおよその面積と、どういった作業を行うのか。
●担当者 大きく3点ある。まず、一番大きいのが小野路町の市が持っている農地で約1100平米の農地整備工事を行う。現場は竹が侵入し、あるいは竹の中に樹木が生えていたりするので、そういったものの伐採、抜根等を行い、農地として使えるような整備を行う。2点目は、小山田のエリアの中で農道整備を80メートルほど予定しており、
こちらの舗装工事を行う。3点目は、小山田エリアで、5、60年前に整備した水路に少し不具合があるので、約5メートルの補修工事を予定している。
●委員 観光コンベンション協会補助金について、毎年4150万円の補助金を提供されている。コロナで3年動きが止まっているにもかかわらず、なぜこの金額が定着して支出されているのか。
●担当者 コロナ禍で、オンラインでの業務の進め方であったり、デジタル部分の整備をしながら、これからの新しい働き方という協会内部の組織づくりをしていたという状況である。補助金としては、運営費も含めた補助金なので、金額としては妥当だと考えている。
■農業委員会事務局
●委員 農業委員会サポートシステムとは具体的にどういうものか。
●担当者 農業委員会サポートシステムは、新たに国が農地台帳のシステムとして整備しているシステムである。このシステムは、農業委員会等が農地法により定められている法定業務を行うための様々な行政手続がオンライン化できたり、農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、これから行う事務について、サポートシステムを使って効率よく業務ができるものである。
■選挙管理委員会事務局・監査事務局・議会事務局
●委員 選挙費について、「小・中学校、高等学校等で行う選挙出前講座などを実施します」とあるが、町田市内に小中学校、高等学校はたくさんあるが、どのような割り振りでやっているのか。
●担当者 2022年度の実績で、出前授業は、高校は4校実施する予定である。中学校と小学校合わせて12校と1施設ということで、小学校中心である。庁舎見学については、大半が小学校3年生なので、小学生中心である。サイクルは、町田市内の小学校、中学校、高校、大学等に、選挙管理委員会として出前講座をする旨の文書を出し、
各学校から季節に偏りなく依頼が来て、それに対して出向いている。
【健康福祉常任委員会】
■地域福祉部
●委員 緊急援護費だが、市内の緊急援護が必要な方が増えて少し金額を増やしているのか。
●担当者 緊急援護費の支給については、要件はいろいろある。一般的に考えやすいのは、生活保護の申請をしたいということで相談に見えた段階で、少ない金額しか持ち合わせがなくて、今晩の宿泊すら困る場合など、あるいは食べ物に困る場合に適用している。一方で、相談、申請というレベルではなくて、受給中にあっても、いろいろ病気が背景にあったり、丸々紛失してしまって、保護費を受けたけれども、その後、あと何週間も次の支給日まであるが、どうしようもないときに、会議に諮り、総合的にどう対応したらいいのか決定をして対応している。そういう部分の重なったものが増えてきた傾向があるので、予算としても、それに合うような形を考えている。
●委員 貸付金などは利用しにくいことがあると思うので、予算措置が少なくなってきているが、緊急援護費では、総体的に窓口で相談しながら、緊急な援護をする状況が増えているから実態に合わせて今年度約1.2倍増やしたということでよろしいか。
●担当者 実態を見て、計算をしている。
■いきいき生活部
●委員 ふれあい館について、コロナが蔓延したときに、お風呂施設が廃止になり、お風呂を楽しみにしていたお年寄りなどががっかりしているが、今ふれあい館はまだ午前、午後の入替え制を取っているのか。お年寄りは一日行って日がなのんびりというのが今までの利用状況だったと思うが、入替え制になってしまうと、お昼に1回 帰っていかなければならない。そうすると、なかなか行くのも億劫になってしまう状況を見ているが、お風呂がなくなって高齢者がそれでもふれあい館に行けば魅力的で一日過ごせると思えるような施設にする工夫は、町トレだけなのか、今年度、どういう計画になっているのか。
●担当者 現在も入替え制となっている。これはコロナ禍もあり、感染症拡大防止で進めている。今後のコロナの感染状況を見ながら、入替え制をやめて、また一日通していられるようになるか、それは今後の検討とさせてもらいたい。また、ふれあい館の今後の在り方についてだが、2022年の10月1日から、アンケートを行っており、シルバー人材センターや老人クラブ連合会、それから介護予防サポーターの方、また、ふれあい館の利用者の方からもアンケートを取っている。そちらのアンケートから、高齢者の皆さんのニーズを整理すると、体力の維持向上、健康づくりを行いたいという意見や、仲間や友人とよりよい関係を持ちコミュニケーションを豊かにしたい、より身近な場所で活動に取り組みたいという意見があったので、そういった意見を基に今後の取組を考えていきたい。その意見の中からは、介護予防の健康づくりをふれあい館における今後の重点取組項目に位置づけることがよいだろうと考えており、次年度については、そのような取組を進めていく。
■保健所
担当者の説明をおおむね了としました。
質疑終結後、反対の立場から、
2023年度の予算には、国民健康保険財政の健全化という国の大号令の下、赤字繰入れ解消のための4.6億円が被保険者への負担増になった。また、連続する税率改定により、国民健康保険税の滞納者に対する年に1度発行する医療費10割負担の資格証の郵便料金も計上されている。コロナ禍、物価高騰で市民の暮らしが脅かされる今だからこそ、住民の福祉増進という自治体の本来の役割が求められていると思う。よって以上の理由から第7号議案に反対するとの反対討論がありました。
【文教社会常任委員会】
■市民部
●委員 性の多様性への理解促進事業について、市民への広い周知、理解が必要になってくると思う。なかなか予算が難しいかとは思うが、多くの人が通るところで、大々的にPRすることも重要かと思うがどうか。
●担当者 条例が可決された後、制度が来月からスタートしたら、4月、5月の連休のところで、市内で虹色のライトアップをすることを計画している。今後も色々な予算を利用しながらPRを続けていきたいと考えている。
■文化スポーツ振興部
●委員 文化振興費に(仮称)町田市文化芸術のまちづくり基本計画とあるが、具体論としてはどんなことをやるのか。
●担当者 まちだ未来づくりビジョンの中において、文化芸術に触れる機会の創出、市民主体の文化芸術の活動支援、身近に文化芸術に親しめる環境づくりを行うことで、ありのままの自分を表現できる町になることを目指している。その中で、なりたい姿、いつでも、どこでも、だれでも、あらゆる文化芸術を楽しめるまちの実現に向けて、文化芸術施策を体系的に整理して計画的に進めるための計画となっている。
■子ども生活部
●委員 高校生医療費補助については所得制限も23区を中心に撤廃する動きがある中で、多摩地域は厳しいと言われているが、3年後等を見越して何か検討していくようなものがあるのか。
●担当者 補助については恒久的なものを引き続き求めていくというところは、市でも働きかけをしている。東京都などで何かしらの動きがあれば、各自治体との情報共有をしながら、市としても、そういった動向を的確に捉えて、適宜状況に合った施策を行っていきたい。
■学校教育部
●委員 保健給食費について、「予算概要説明書」の2023年度の取り組みの中で「中学校給食では、現行の選択制・ランチボックス形式を継続しつつ制度の充実を図ります」と書かれているが、具体的にどんな充実を図るのか。
●担当者 今年度実施したゼルビア×キッチンとの献立を活用した給食の提供や 産地直送のうみのごちそう給食などを引き続き行っていくことで、魅力を向上していく。また、申請に関しても、中学校でも、申請が紙になっているものを電子化していくことで、そうした充実をして皆さんに利用していただこうと考えている。
■生涯学習部
●委員 リアルな本とデジタルの本の費用対効果について、実際の本自体は在荷しておくスペースであったり、メンテナンスもかかってくると思うが、その点では、電子のほうが場所も取らず、物もすり減らない点でよいかと思うが、どのように捉えているか。
●担当者 回転数で言うと、やはり電子のほうが蔵書に対して回転が非常によく、そこが強みかと思っている。紙の本のよさもある一方で、電子の、時間や場所にとらわれないというよさもあるので、そこは状況を見ながら、蔵書構成を考えていきたいと思っている。
質疑終結後、反対の立場から、
今回の予算には、新たに高校生等医療費助成制度、(仮称)子どもにやさしいまち条例制定に向けた取組、子どもの参画を具体化するための予算、また市民の悲願である中学校全員給食に向けた整備の具体化、さらに市民部では性の多様性を尊重する条例のスタートに関する予算など、そういった点については大いに評価をしている。また、審査した各部において、市民生活、子育てに欠かせない予算が組まれていると認識をしている。一方、今委員会においては、学校統廃合の見直し、(仮称)国際工芸美術館の整備の見直しを求める請願審査が行われ、市民の合意と納得が得られていない事業があると問題点を指摘したいと思う。芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム、(仮称)国際工芸美術館の整備について、そもそもなぜ今の斜面地が選択をされたのか。工事費が増えていることもあり、スタート地点に立ち戻って市民からの疑問の声が出されている。昨年行われた建築審査会の公聴会では、参加者の9割が反対というのが現状である。また、国際版画美術館の版画工房をアート体験棟に移し、鑑賞と制作を一体のものとしてきた理念が壊されてしまうこと、利用者の納得が得られているとは考えられず、市民、地域の方、専門家も交えた抜本的な見直しが必要と考える。新たな学校づくり推進事業の学校統廃合については、請願審査の中でも適正規模・適正配置の基準への指摘、通学距離が延びること、学童保育クラブの大規模化など多くの問題が指摘された。何より子どもたちへの負担への心配が解消されていない。特に本予算で具体化をされている3つの地区については、周知期間の不十分さも指摘をしてきた。統廃合の計画の見直しが必要だと考える。公共施設再編での図書館再編について、鶴川図書館に続き、中央図書館とさるびあ図書館についても、集約方法の検討が始まるということだが、採択された請願の趣旨に基づく対応をすべきと考える。学校給食業務の民間委託推進による専門性の担保の課題、また、子ども発達センターの民間活力導入の検討についても、直営のメリットについてもきちんと検討、検証されるべきと考える。以上の理由から第7号議案の反対討論とするとの反対討論がありました。
次に、賛成の立場から、
今回の予算には、子どもにやさしいまちづくり事業や高校生等医療費助成事業、性の多様性への理解促進事業などが盛り込まれており、一定の理解はしているところである。しかし、芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム推進事業の(仮称)国際工芸美術館 整備工事費について、以下の点につき指摘をする。現在、新型コロナウイルス感染症の影響が収まりを見せる中で、昨今の世界情勢や急激な円安などによる物価資材、原油などの価格高騰の要因により、市民生活、市内事業者の経営が圧迫されている。特に物価上昇による影響は、低所得者層ほど負担が大きいとされ、全国的にも生活保護の申請件数が増加する等、市民生活に大きな影響が出ている。この価格高騰の影響は公共事業にも及び、令和4年度第4回定例会中の本委員会で示された行政報告によると、建築費指数は2020年11月の基本設計時に比べ、2022年10月の実施設計時には約18%上昇し、(仮称)国際工芸美術館整備工事費への影響はさらに高く、約19%の上昇であり、約5億4,000万円の増額となっている。これまでの本会議や委員会審査で(仮称)国際工芸美術館整備工事費について、当初予定されていた28.5億円からの削減を繰り返し求めてきた。整備工事費の削減については、本会議においても市長も削減努力について答弁され、担当課からも同様の答弁がなされていた。さらに、昨年12月の本議会では、(仮称)町田市立国際工芸美術館整備計画の工事費削減努力を継続することを求める決議に対し、多くの議員の賛同をいただいた。これまでの努力により1億8,000万円の費用を削減したのは評価するが、この削減の中には、スロープを階段に変更するというバリアフリーに反した項目もあり、災害時などエレベーターが緊急停止した際の対応について疑義が残る。また、削減努力を行ったにもかかわらず、最終的な予算は、令和4年度の提案時より約4.8億円の増額となった。現在の価格高騰は当面高止まりするだろうという見解が一般的な状況下で、資材等高騰分を上乗せした増額予算をそのまま提出することは、市民からの理解は得られないと考える。よって、(仮称)国際工芸美術館整備工事費について、資材価格等の高騰が収まるまで事業計画を見合わせることを求め、賛成討論とするとの賛成討論がありました。
次に、賛成の立場から、
第7号議案について、芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム推進事業費に反対をし、その他の予算案に賛成の立場で討論をする。昨年の第1回定例会にて、実施設計については、その内容も審議できる段階ではない状態であるにもかかわらず、そして市民との話合いも継続している最中であるにもかかわらず、建設を進めるための予算を提案したり、委員会での附帯意見も、一体化工事についての意見がついていたにもかかわらず、話合いを継続するのは(仮称)公園案内棟/喫茶/版画工房/アート体験棟のことであったり、28.5億円から少しでも費用を圧縮すると市長は答弁していたが、建築資材の高騰や労務単価の影響で28.5億円から下げるどころか、2016年に高いからという理由で修正案が可決された当時の計画の32億円を超える33.4億円という金額、さらに版画工房が移動する別棟や一体化工事の計画も含めると、当初40億円だったものが今現在の段階で約44.71億円、資材や労務単価の高騰があれば、さらに超える可能性もある状態など、これまで議会から出た意見などもないがしろにした結果であり、一連の進め方は議会軽視甚だしい対応と考える。なぜそこまで急に急がなければならないのだろうか。切りよく2026年4月開館ではなく、なぜ3月開館なのだろうか。今現在の市長の任期は2026年3月8日までである。もし、開所式に自分が出たいという市民からすればどうでもいい、くだらない理由で市民の声を聞かず、反映させず、計画を急いでいるとするならば、これは到底許されるものではないと会派としては考える。自転車も使える別のエレベーターの設置やもみじ園のデッキスロープ見直しなど、ごくごく一部の要望のみを取り入れ、それ以外の市民の声を聞かず、反映させず、話合いの機会をつくってほしいという市民の声すら通らないで、計画を強引に進めるのではなく、市民の声をしっかりと聞き、それを計画に反映させていく。資材も労務単価も高騰している現状で建設を急ぐのではなく、本来あるべきプロセスで、この計画自体を見直す必要があると考えるため、第7号議案に対し、現状では芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム推進事業費については、修正案を出さざるを得ないことを前提とし、ほかの予算に対する賛成討論とするとの賛成討論がありました。
【建設常任委員会】
■環境資源部
●委員 循環型施設整備費の上小山田地区の測量委託料について、今の現状での地元住民との協議状況について教えてほしい。
●担当者 関係者との調査、調整等に時間を要している。そちらのほうが完了したら、直ちに測量を行っていきたいと考えているので、このたび計上させていただいている。
●委員 環境衛生費について、トイレを貸していただくといったところで、店舗に市から公共トイレの設置も依頼するとあるが、何店舗ぐらい予定をされているのか。
●担当者 公共トイレは現在71店舗あるが、5店舗増やす予定である。今までは、町田市公共トイレ協力店になりたいと手を挙げていただいた事業者には、やっていただいた。来年度からは、協力金を2万円出すということになっている。ある程度、お願いするということが今回の趣旨である。今後については、地域的には相原と小山地区にはないので、そちらのほうを推進していきたいと思っている。
■道路部
●委員 無電柱化推進事業について、文学館通りだが、将来的には一方通行になるのか。
●担当者 全てが一方通行というわけではないが、一部一方通行になる。具体的には、サウスフロントタワーのところから駅前通りに向かっての部分は相互通行になるが、サウスフロントタワーから町田街道側に向かって一方通行になるというような形で今計画している。
●委員 道路維持費において、ペデストリアン1号デッキについて改修工事を行っていると思うが、完了予定と工事内容を確認したい。
●担当者 ペデストリアンデッキの改修工事の完成の時期になるが、令和5年12月を目指している。それから、工事内容は、上屋の塗装の塗り替え、横のパネルが傷んでいるのでパネルの交換、照明の交換を予定している。
●委員 道路総務費について、東京都の急傾斜地崩壊対策事業として20%の補助はあるが、どれぐらいの規模でやる予定の計画になっているのか。
●担当者 急傾斜地崩壊対策事業は、急傾斜地崩壊による災害の防止に関する法律に基づいて東京都が指定した区域の崩壊の防止の工事を行うものである。2023年度は詳細設計を行う予定になっている。
●委員 都市計画道路築造事業において、都計道3・4・11号線の延長については、形態も含めて、今後、地域の方への説明はどうされていくのか。また、この計画自体は今後どのような見通しになっていくのか。
●担当者 今年の2月に東京都で道路区域として、この整備範囲が編入されている。この3月に用地説明会をさせていただいて、いよいよ来年度から用地取得に入っていくという段階である。
●委員 相原駅周辺街づくり事業について、相原駅東口アクセス路の進捗状況と今後のスケジュールについて。
●担当者 現在、用地取得を進めていて、2023年2月末時点で用地取得率が38%となっている。今後のスケジュールについてだが、2023年度も引き続き用地取得を進めていき、2024年度から順次工事に着手をしていきたいと考えている。
●委員 準幹線補助道路新設改良事業において、堺109号線の進捗状況と今後のスケジュールを教えてほしい。
●担当者 今年度に用地測量を行い、用地取得に必要な図面や資料を作成している。来年度は、用地取得を進めていきたいと思っている。2024年度の着工を目指している。
■都市づくり部
●委員 地域交通推進事業について、交差点や横断歩道至近にある危険なバス停の改善に向けて、必要な道路改修をやるとあるが、今現在、何か所あるのか。
●担当者 市内に今年度初めで11か所あった。2022年度に一応4か所改善ができ、残りが7か所という形になっている。
●委員 中心市街地まちづくり推進事業について、2022年度に作成した運用ルールに基づき、試行的に運用及び検証し、運用体制を確立します、また、沿道空間利用マッチング機能を備えた業務専用ホームページを構築しますとあるが、具体的な内容とホームページ作成のスケジュールも教えてほしい。
●担当者 運用ルール、ガイドラインを社会実験などを通して、試行的な運用を行った上で、そのガイドライン及び運用ルールがしっかり機能するかといったところを検証するための委託費という形になっている。また、専用のホームページも来年度つくっていこうというところで、沿道空間のマッチングを兼ねたカレンダー方式の予約システムみたいなところになっていて、使いたい方が専用のホームページを活用しながら予約をしたりだとか、地域のほかの方々も、どういう取組がどういうところでやっているのかというところを分かるようなホームページで、来年度の策定を目指して取組を進めていくというところである。
●委員 多摩都市モノレールまちづくり推進事業において、木曽山崎団地地区調査測量についていつ頃から始めて、どのエリアで、どのような方法で、最終的な目的は、どういうことを目指していこうとしているのか。
●担当者 モノレールとバスが快適に乗り継ぎできるような交通広場の検討をしたいと考えており、基本的には木曽山崎団地全体になる。目標としては、都市づくりのマスタープランに基づくプロジェクトなので、最終的には2040年を見据えた形で今検討しているところである。
●委員 都市計画管理費についてモノレール沿線の新たなまちづくりを推進していくということで、そこで需要を創出する、あるいはにぎわいを創出するような取組が行われていくということだが、都市計画として、その辺の整合性というか考え方について、どのように考えているか。
●担当者 モノレールの沿線については、都市づくりのマスタープランの中でも都市骨格軸に位置づけており、にぎわいをもたらすための機能誘導をうたっているので、そういった中でも、立地適正化計画でも、当然その考え方を踏襲していきたいと考えている。
●委員 野津田公園スポーツの森整備事業について湿性植物園を活用して、スケートパークを整備するということだが、湿性植物園の自然環境について、市民の方の合意、一般の方々の声というのはどのように聞いていくのか。
●担当者 今現在、直接、スケートボードをやられている方だとか、公園の事務所とかにもアンケートを置いて、回収箱を設置している。自然環境を大切にしてほしいというような意見や、きちんとしたものを造ってほしい、プロができるようなものを造ってほしいなど、いろいろな意見をいただいている。いただいた意見を整理した上で、設置をする場所の面積でどこまで何ができるのかということもレベルの決定には関わってくるので、その基本設計の中で最終的には方向性を決めていきたいと考えている。湿性植物園としての価値、利用者、市民合意ということだが、今、意見収集をしている中で、そういった意見も集まってくるとは思っている。あそこは水辺の環境ということがあり、水辺の環境ならではのものがあるということも、承知しているので、施設整備と、そういった自然環境の保全をバランスを取りながら設計していきたいと考えている。湿性植物園としての価値、利用者、市民合意ということだが、今、意見収集をしている中で、そういった意見も集まってくるとは思っている。あそこは水辺の環境ということがあり、水辺の環境ならではのものがあるということも、承知しているので、施設整備と、そういった自然環境の保全をバランスを取りながら設計していきたいと考えている。
■下水道部
●委員 し尿処理費について、くみ取り便所だが、年々減少しているかと思うが、ここ3年ぐらいの推移はどのようになっているか。 また、今後、水洗トイレへの移行をどのように進めようと、考えていくのか。
●担当者 くみ取り世帯については年々減ってきているところである。 直近の3年の推移だが、大体5%ずつ減ってきているような状況である。これからの水洗化への移行ということだが、町田市は公共水域改善10ヶ年計画において、2026年までに水洗化率100%を目指しているので、それに向けて利用啓発と公共下水道への切り替え等の啓発をしていきたいと思っている。
質疑終結後、反対の立場から、
本予算には、省エネルギーや再生可能エネルギーの普及、廃棄物処理や資源化、道路維持補修整備、災害に強いまちづくりや下水道会計を支える企業会計への繰入れなど、また市民の憩いの場である公園整備など、市民の安心安全な生活や環境を守るために必要な予算が多く盛り込まれている。 しかし、一方で以下の点で問題があると考える。 まず第1に、みちづくり・まちづくりパートナー事業のうち、原町田5丁目から都計道3・3・36号線までの3・4・11号線の延伸である。モノレール延伸ありき、先行整備される事業であり、多くの住宅が張りついている地域で、住民への情報提供や合意形成はまだこれからだと考える。また、反対の声もあるということで、十分合意形成が図られていないと考える。2点目に、多摩都市モノレール町田方面延伸事業に伴う沿線まちづくりについてである。新たな拠点づくりや採算確保のために乗客の需要を無理につくり出すことは、コンパクトシティーへの再編の考え方とも相反するのではないか。また、町田駅周辺の4か所の再開発を同時に進めていくことは、今後、町田市の多額な財政投入が求められることにもなる。市民の暮らしや教育の充実など、自治体として本来優先すべき事業を困難にすることにもなると考える。3点目に、野津田公園スポーツの森湿生植物園へのスケートパーク整備事業についてである。パークセンターゾーンに位置づけられた湿生植物園存続を求める市民の声もあり、自然環境を存続というのは大変重要な課題だと思う。市民への情報提供と合意形成も必要だと思う。また、スケートボードは中高生なども大変愛好者が多く、実際には、そういった若い世代も活用できる場所に、もっと交通の便のいいところ、あるいは公園の中でもほかの場所を検討すべきではないか。 4点目には、芹ヶ谷公園の土壌調査が検討されていないという点である。芹ヶ谷公園の斜面地の土壌に対して、市民から不安の声が上がっている。今後、新たな施設を整備していく上でも、樹木の状況や土壌の中の湧水の状況など、専門家の知見も借りながら十分な調査を行い、安全性を確認すべきだと考える。以上の点から本予算には反対をするとの反対討論がありました。